
2012年11月18日 高井戸駅 写真:こぱふぅ

2012年11月18日 高井戸駅 写真:こぱふぅ
1000系は井の頭線としては初の20メートル級車両で、VVVFインバータ制御を導入。3000系の3扉から4扉となったため、ホームの乗車位置が異なっている。

2012年11月18日 高井戸駅 写真:こぱふぅ
5両編成の車両はステンレス製だが、先頭部のみ普通鋼製となっている。
先頭部には8色(ブルーグリーン、アイボリーホワイト、サーモンピンク、ライトグリーン、バイオレット、ベージュ、ライトブルー、オレンジベージュ)の強化プラスチック製カラーマスクが貼られており、レインボーカラーと称される。
先頭部には8色(ブルーグリーン、アイボリーホワイト、サーモンピンク、ライトグリーン、バイオレット、ベージュ、ライトブルー、オレンジベージュ)の強化プラスチック製カラーマスクが貼られており、レインボーカラーと称される。

2012年11月18日 高井戸駅 写真:こぱふぅ

2006年5月28日 吉祥寺駅
井の頭線は、このカラフルさのおかげで、ステンレス車の導入時期が東急に次いで早かった(1962年)にもかかわらず、貧乏くさい「ステンレス電車」というイメージが定着しなかったあたりがお洒落である。

2006年5月28日 吉祥寺駅
路線カラーが無いという意味でもユニークである。

列車種別は各駅停車と急行の2種類。京王電鉄で唯一の1,067mmの狭軌。これは、開業時は小田急電鉄の元となった帝都電鉄の路線だったため。
列車種別は各駅停車と急行の2種類。京王電鉄で唯一の1,067mmの狭軌。これは、開業時は小田急電鉄の元となった帝都電鉄の路線だったため。

2006年5月28日 吉祥寺駅
京王線・井の頭線の車内には、小さい子どもが扉へ引き込まれるのを防止するためにハローキティのステッカーが貼られている。
2008年(平成20年)に導入された5次車両から先頭部分が丸みを帯び、3000系に近いイメージとなった。前面行先表示器はフルカラーLED化を果たしている。
また、車内設備では、各乗降扉の上部にJR東日本の車両のような液晶ディスプレイ方式の案内表示装置が設置されている。
また、車内設備では、各乗降扉の上部にJR東日本の車両のような液晶ディスプレイ方式の案内表示装置が設置されている。

2011年6月19日 明大前駅近く 写真:こぱふぅ
新色のオレンジベージュ車両は、第6次車両として2009年(平成21年)6月に導入された。
井の頭線とアジサイ
浜田山駅から西永福町駅までと、新代田駅から下北沢駅までの区間では、梅雨のシーズンになると色とりどりのアジサイが楽しめる。

丘を切り開いたり人工的に盛り土するなどして作った法面は、土砂崩れに弱い。そこで、植物を植えることで法面を強化するとともに、景観の向上を図っている。
アジサイが植えられるようになったのは1991年(平成3年)以降のこと。
除草剤を使わない京王沿線の緑化の取組みは、2001年(平成13年)の杉並「まち」デザイン賞を受賞している。
丘を切り開いたり人工的に盛り土するなどして作った法面は、土砂崩れに弱い。そこで、植物を植えることで法面を強化するとともに、景観の向上を図っている。
アジサイが植えられるようになったのは1991年(平成3年)以降のこと。
除草剤を使わない京王沿線の緑化の取組みは、2001年(平成13年)の杉並「まち」デザイン賞を受賞している。
参考書籍

|
井の頭線沿線の1世紀 | ||
| 著者 | 生活情報センター/鎌田達也 | ||
| 出版社 | 生活情報センター | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2006年04月 | ||
| 価格 | 4,180円(税込) | ||
| ISBN | 9784861262555 | ||
| 沿線の失われた風景が甦る。写真総数600点で振り返る井の頭線の歴史と沿線の生活史。 | |||
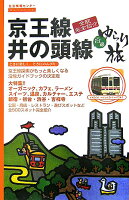
|
京王線・井の頭線 沿線ゆらり旅 | ||
| 著者 | |||
| 出版社 | 生活情報センター | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2006年08月 | ||
| 価格 | 1,430円(税込) | ||
| ISBN | 9784861262692 | ||

|
京王電鉄ものがたり | ||
| 著者 | 松本典久 | ||
| 出版社 | ネット武蔵野 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2003年04月 | ||
| 価格 | 1,361円(税込) | ||
| ISBN | 9784944237104 | ||
(この項おわり)
 大きな写真
大きな写真









吉祥寺~渋谷間を結ぶ井の頭線は、ぱふぅ家の足のひとつだ。