発言者
| 萩野正昭 |
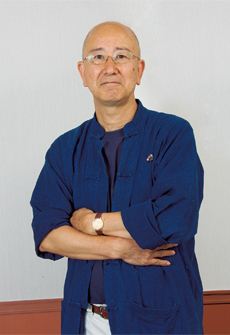
|
|
| ボイジャー社長 | ||
| 2010年10月16日 |
場面
本は誰でも読めるものでないといけません。規格、端末、ビューアなどで読める本の制限がある今の状況はおかしいですよね。すぐに規格の話が語られることはなくなって世界で統一されるでしょう。私たちの作ったドットブックや「T-Time」もなくなるかもしれません。「特集・電子書籍入門」(週刊ダイヤモンド 2010年10月16日号)
コメント
電子書籍元年といっても、電子書籍のデータとアプリは一体化している。もしOSのアップグレードなどでアプリが使えなくなれば、せっかく入手した電子書籍は単なるビットデータと化してしまう
それでなくても、電子書籍を読むためにはPCやタブレット、スマートフォンといったデジタル・デバイスが必要だ。それを動かす電気も必要だ。
アマゾンの奥地に住んでいる原住民や、荒川の河川敷に住んでいるホームレスの方が簡単に読めるというものでは無いだろう(いまのホームレス生活は充実しているから、もしかしたら‥‥)。

紙でできた本はなくならないと思う。だが出版コストを考えると、聖書や食品成分表のような大ベストセラーしか残らないかもしれない。
それでなくても、電子書籍を読むためにはPCやタブレット、スマートフォンといったデジタル・デバイスが必要だ。それを動かす電気も必要だ。
アマゾンの奥地に住んでいる原住民や、荒川の河川敷に住んでいるホームレスの方が簡単に読めるというものでは無いだろう(いまのホームレス生活は充実しているから、もしかしたら‥‥)。
紙でできた本はなくならないと思う。だが出版コストを考えると、聖書や食品成分表のような大ベストセラーしか残らないかもしれない。
(この項おわり)

