染井よしの桜の里公園

その説によると、ソメイヨシノは1730年(享保15年)ごろにオオシマザクラとエドヒガンを人工交配してつくられたという。染井村の名前と、桜の名所として名高い奈良の吉野山の名前を合わせて「ソメイヨシノ」とした。
染井稲荷

西福寺(真言宗豊山派)と隣り合うようにして染井稲荷(東京都豊島区駒込6-11-5)がある。

現存する最古のソメイヨシノは青森県の弘前公園にある、1882年(明治15年)に植えられたものだ。
ソメイヨシノが学術的に同定されたのは1890年(明治23年)のことだが、その頃は東京でも様々な種類の桜が楽しめた。品種によって開花時期が異なるので、1ヶ月は花見ができたという。
現存する最古のソメイヨシノは青森県の弘前公園にある、1882年(明治15年)に植えられたものだ。
ソメイヨシノが学術的に同定されたのは1890年(明治23年)のことだが、その頃は東京でも様々な種類の桜が楽しめた。品種によって開花時期が異なるので、1ヶ月は花見ができたという。
戦後、焼け跡の東京に次々と桜の木が植えられた。これがソメイヨシノだった。ソメイヨシノの祖先は同じ1本の桜の木なので、完全なクローンである。花の色形が同じなら、咲く時期も一緒である。

ソメイヨシノは東京だけでなく全国に“拡散”した。
そして、1973年(昭和48年)に豊島区の皮切りに、1984年(昭和59年)には東京の花に指定された。
そして、1973年(昭和48年)に豊島区の皮切りに、1984年(昭和59年)には東京の花に指定された。
毎年桜の季節になると、染井よしの町会(駒込四丁目、五丁目、六丁目)によって催し物がある。
霜降銀座商店街

旧古河庭園

【写真:ままぱふぅ】
参考書籍
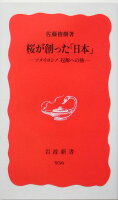
|
桜が創った「日本」 | ||
| 著者 | 佐藤 俊樹 | ||
| 出版社 | 岩波書店 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2005年02月18日頃 | ||
| 価格 | 946円(税込) | ||
| ISBN | 9784004309369 | ||
| まえがき 1 ソメイヨシノ革命 1 「桜の春」今昔 桜、桜、……/昔の桜景色/江戸の桜/ソメイヨシノはすべてクローン/花見の時空/多品種型と単品種型/吉田兼好の花見/ソメイヨシノ革命 2 想像の桜/現実のサクラ 花と名/「桜」とよばれた理由/ヨシノの由来/「名」の力/想像の美・現実の美/「吉野の桜」はなかった/言葉と想像力/絵に画いたような……/説話の宇宙/理念の重力/起源と反起源の遠近法 2 起源への旅 1 九段と染井 明治三年のソメイヨシノ/三つの年代/創建当時の境内/ソメイヨシノ説の典拠/染井と九段と上野/土地愛の多重性/「四季の遊び場」 2 ソメイヨシノの森へ 吉野桜の出現/「日本」と桜/新しさの魅力/公園と公共/戦争と事業/普及のメカニズム 3 桜の帝国 起源への視線/ナショナリズムの科学/伊藤銀月と井上哲次郎/桜らしい桜/大正期の飯田/日本らしさと桜らしさ/「桜の国土」の生成/「桜の国土」の拡張/風土と民族 4 逆転する時間 始源の桜の誕生/書き換えられる歴史/「山桜」の同心円/日本らしさの超自然学/旧い桜・新しい桜/逆転する時間/見出された起源 3 創られる桜・創られる「日本」 1 拡散する記号 花の時間と人の時間/拡散する物語/桜語りの戦後/想像される「歴史」/「みんな」のモノローグ/空転する言葉/不死のゼロ記号 2 自然と人工の環 桜のエコノミー/嫌われる理由/「日本の自然」は一つでない/自然・人工の反転/美しさの根底/「桜」とは何か/「桜」の自己創出/ありえた「桜」とありえた歴史/「日本」の自己創出/ソメイヨシノの明日 あとがき 桜のがいどぶっく・がいど ソメイヨシノの起源をめぐる新たな展開ーー本書五刷に際して(二〇〇九年一二月) | |||
染井稲荷へのアクセス

近隣の情報
- ソメイヨシノの故郷は東京の「染井村」:ぱふぅ家のホームページ
- 上中里駅は京浜東北線の駅:ぱふぅ家のホームページ
- 路面電車の日で車庫内を見学:ぱふぅ家のホームページ
- しだれ桜が見頃、ライトアップも(2019年3月25日)
- 光の池に浮かぶ紅葉、幻想的に(2017年11月30日)
- 東京・旧古河庭園で紅葉が見頃(2017年11月27日)
- 闇に照らされ、しだれ桜見頃 東0.6義園(2017年4月9日)
- 旧古河庭園でバラを楽しむ(2016年10月5日)
- 暗闇に浮かぶしだれ桜(2016年3月30日)
参考サイト
- 豊島区で生まれたソメイヨシノ:豊島区
(この項おわり)
 大きな写真
大きな写真



写真の「染井よしの桜の里公園」(東京都豊島区駒込6-3-1)は、2009年(平成21年)3月に完成したばかりの新しい公園だ。
東京都豊島区駒込四丁目から六丁目の界隈は、江戸時代には染井村と呼ばれ、多くの植木屋が軒を連ねていた。江戸後期から明治半ばごろまで、キクやツツジなど四季折々の花々を楽しめる名所だった。