

太平洋戦争中も操業を続けたが、空襲の被害を受けなかったこと、操業停止後も片倉工業が保存に尽力したことから、創業当時の建物が良好な状態で残った。
2005年(平成17年)に敷地全体が国の史跡に、2006年(平成18年)には主要建造物が重要文化財の指定を受けた。2014年(平成26年)6月、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産として、世界遺産に登録された。

建物内には、写真の世界遺産認定証のレプリカが展示されている。
2005年(平成17年)に敷地全体が国の史跡に、2006年(平成18年)には主要建造物が重要文化財の指定を受けた。2014年(平成26年)6月、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産として、世界遺産に登録された。
建物内には、写真の世界遺産認定証のレプリカが展示されている。

入口を入ると、木造の軸組に煉瓦を積んだ、2階建ての東置繭所が目に入る。桁行は104メートルもあり、繭を乾燥・貯蔵する施設である。乾燥するために数多くの鉄製ガラス窓を備えている。

この日は、東置繭所の2階が特別公開されていた。100メートル走ができそうな広さである。

こちらは西置繭所。東置繭所と並んでおり、建物の作りや大きさは同じ。

写真のフランス式繰糸機を使い、繰糸器に据え付けられた釜で繭を煮て、工女が糸を引き出していった。製糸場には、この繰糸器が300台設置され、大量の水が使われていた。繭を煮る湯を蒸気で加熱していたほか、動力源としても利用された。

戦後は、全自動の繰糸機が開発された。
写真の「日産HR型自動繰糸機」は1964年(昭和39年)に開発され、富岡製糸場には1966年(昭和41年)頃から導入された。操業停止まで活躍した。
写真の「日産HR型自動繰糸機」は1964年(昭和39年)に開発され、富岡製糸場には1966年(昭和41年)頃から導入された。操業停止まで活躍した。
自動繰糸機は、人が行ってきた繰糸作業の10倍の生産力を誇り、生産される生糸の品質も著しく向上した。


首長館の南西には、工女が寝泊まりする寄宿舎がある。写真は、1940年(昭和15年)に片倉製糸紡績会社が建てた妙義寮である。
部屋の広さは15畳で、1棟は16部屋の2階建て。各棟2階東端に娯楽室が設けられている。
部屋の広さは15畳で、1棟は16部屋の2階建て。各棟2階東端に娯楽室が設けられている。

製糸工場というと『あゝ野麦峠』の女工哀史を連想するが、あちらは昭和初期の信州の話。富岡製糸場は現代を先取りしたかのような経営・労働環境であった。
だが、ポール・ブリュナの給与が高額すぎることもあり、創業3年目に解雇。それからは日本人だけで工場運営をしていくのだが、工女の中途退職も多く、思うように生産量が伸びず、赤字経営が続く。

1893年(明治26年)に三井に払い下げられるが、労働条件の悪化を理由に、1898年(明治31年)、工女がストライキを起こす。だが、労働環境は女工哀史に述べられているほど劣悪だったわけではなく、三井時代の経営は概ね順調だった。
だが、製糸業に見切りを付けた三井は、1902年(明治35年)、富岡製糸工場を含む4工場全てを、原富太郎の原合名会社に売却する。1902年(明治35年)10月、原富岡製糸所と改名した。原時代、第一次世界大戦や世界恐慌に見舞われるが、繰糸機を更新するなどして生産性は向上した。
ところが、主要輸出国であるアメリカでナイロンが台頭し、経営の先行きに不安があったことから、原合名会社は製糸事業を縮小。1938年(昭和13年)、原富岡製糸所は株式会社富岡製糸所として独立し、翌1939年(昭和14年)、日本最大級の繊維企業であった片倉製糸紡績会社に合併。片倉富岡製糸所と改名する。

太平洋戦争中も製糸工場として操業を続けたが、統制経済に組み込まれたが、戦後、再び片倉の手に戻り、片倉工業株式会社富岡工場となった。
1952年(昭和27年)、自動繰糸器を段階的に導入し、電化を進めるために所内に変電所を設置した。1974年(昭和49年)には生産量37万3401kgと、富岡製糸場史上最高の生産高をあげた。
しかし、和服を着る機会が減少し、1972年(昭和47年)の日中国交正常化により中国さんの廉価な生糸が輸入されるようになり、その後は生産量は減少を続けた。そして1987年(昭和62年)2月、ついに操業を停止した。

片倉工業は閉場後も一般公開はせず、「貸さない、売らない、壊さない」の方針を堅持し、工場の保存に専念した。
だが、ポール・ブリュナの給与が高額すぎることもあり、創業3年目に解雇。それからは日本人だけで工場運営をしていくのだが、工女の中途退職も多く、思うように生産量が伸びず、赤字経営が続く。
1893年(明治26年)に三井に払い下げられるが、労働条件の悪化を理由に、1898年(明治31年)、工女がストライキを起こす。だが、労働環境は女工哀史に述べられているほど劣悪だったわけではなく、三井時代の経営は概ね順調だった。
だが、製糸業に見切りを付けた三井は、1902年(明治35年)、富岡製糸工場を含む4工場全てを、原富太郎の原合名会社に売却する。1902年(明治35年)10月、原富岡製糸所と改名した。原時代、第一次世界大戦や世界恐慌に見舞われるが、繰糸機を更新するなどして生産性は向上した。
ところが、主要輸出国であるアメリカでナイロンが台頭し、経営の先行きに不安があったことから、原合名会社は製糸事業を縮小。1938年(昭和13年)、原富岡製糸所は株式会社富岡製糸所として独立し、翌1939年(昭和14年)、日本最大級の繊維企業であった片倉製糸紡績会社に合併。片倉富岡製糸所と改名する。
太平洋戦争中も製糸工場として操業を続けたが、統制経済に組み込まれたが、戦後、再び片倉の手に戻り、片倉工業株式会社富岡工場となった。
1952年(昭和27年)、自動繰糸器を段階的に導入し、電化を進めるために所内に変電所を設置した。1974年(昭和49年)には生産量37万3401kgと、富岡製糸場史上最高の生産高をあげた。
しかし、和服を着る機会が減少し、1972年(昭和47年)の日中国交正常化により中国さんの廉価な生糸が輸入されるようになり、その後は生産量は減少を続けた。そして1987年(昭和62年)2月、ついに操業を停止した。
片倉工業は閉場後も一般公開はせず、「貸さない、売らない、壊さない」の方針を堅持し、工場の保存に専念した。
交通アクセス
【鉄道】

- 上信電鉄「上州富岡駅」から徒歩約15分
- 上信越自動車道「富岡IC」から約10分

参考書籍
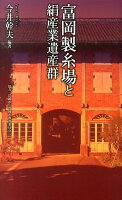
|
富岡製糸場と絹産業遺産群 | ||
| 著者 | 今井幹夫(郷土史) | ||
| 出版社 | ベストセラーズ | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2014年03月 | ||
| 価格 | 1,026円(税込) | ||
| ISBN | 9784584124369 | ||
| 日本の近代化を牽引、世界の絹産業を支えた伝説の模範工場が、いま、世界遺産へ!写真や絵画、数々の史料で甦る、日本近代化150年の真実!奇跡の産業遺産がここにある。 | |||

|
世界文化遺産富岡製糸場と明治のニッポン | ||
| 著者 | 熊谷充晃 | ||
| 出版社 | WAVE出版 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2014年06月18日頃 | ||
| 価格 | 1,320円(税込) | ||
| ISBN | 9784872906943 | ||
| 日本のグローバリゼーションの先駆、富岡製糸場の全貌とは?教科書にも掲載され、日本人なら誰もが一度は聞き覚えのある「富岡製糸場」。極東の島国の、ローカルエリアにあるこの工場がなぜ、「世界文化遺産」に選ばれたのか?世界中が驚嘆した、高品質な「ジャパニーズ・シルク」を生み出した日本の養蚕・製糸技術。それを引っさげ、「小さくても強い、技術大国ニッポン」を作り上げた明治の人々の素顔に迫る一冊! | |||

|
尾高惇忠―富岡製糸場の初代場長 | ||
| 著者 | 荻野勝正 | ||
| 出版社 | さきたま出版会 | ||
| サイズ | 全集・双書 | ||
| 発売日 | 2015年06月 | ||
| 価格 | 1,320円(税込) | ||
| ISBN | 9784878914515 | ||
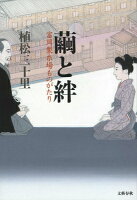
|
繭と絆 富岡製糸場ものがたり | ||
| 著者 | 植松 三十里 | ||
| 出版社 | 文藝春秋 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2015年08月26日頃 | ||
| 価格 | 1,760円(税込) | ||
| ISBN | 9784163902845 | ||
| 世界遺産・富岡製糸場の成立秘話が満載 富岡製糸場の初代工場長・尾高惇忠の娘・勇は、婚約を棚上げして女工になる。明治の日本を支えた製糸業を隆盛に導いた父娘のドラマ。 | |||
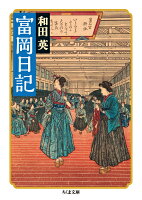
|
富岡日記 | ||
| 著者 | 和田英 | ||
| 出版社 | 筑摩書房 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 2014年06月10日頃 | ||
| 価格 | 748円(税込) | ||
| ISBN | 9784480431844 | ||
| 富岡製糸場は日本初の器械化された官営製糸場で、規模は当時世界一。本書は、そこで伝習工女となり、その後長野で日本初の民営器械化製糸場(六工社)の指導員となった女性が書いた日記。明治初頭、周囲の期待を背にプライドをもって仕事に臨んだこの記録は、近代殖産興業、女性の社会参加の貴重なドキュメント。日本の近代製糸業がわかる文化遺産と施設の案内付き。 | |||
参考サイト
- 富岡製糸場
- 富岡製糸場と絹産業遺産群:群馬県立世界遺産センター
- 世界遺産 富岡製糸場:おりふしの記
- 富岡製糸場に行ってみた:ブログのはしくれ
- 旧富岡製糸場 診療所・病室:レトロな建物を訪ねて
- 富岡製糸場見学3:ひさちゃんのブログ
近隣の情報
- 富岡製糸場は超ホワイト職場としてスタート:ぱふぅ家のホームページ
- 安中精錬所の夜景:ぱふぅ家のホームページ
- 安中榛名駅は新幹線の秘境駅:ぱふぅ家のホームページ
- 群馬・富岡の「黄金」の繭、出荷(2024年10月17日)
- 富岡製糸場の敷地内にキッチンカー検討(2024年7月24日)
- 開運願い、だるまを買い求める(2024年1月5日)
- 「現代の名工」青木さん門下生の作品展(2023年9月20日)
- コロナ禍、沈んだ心を照らした七色の光(2023年5月27日)
- 高崎の街並みを華やかに彩る幻想的なイルミネーション(2023年1月23日)
- 天平文化を伝える宮廷衣装の行列(2022年10月29日)
- 源氏物語の世界、装いから(2022年10月1日)
- 高崎の丘でキバナコスモスが見ごろ(2022年9月12日)
- 古墳時代の鈴が響く鏡や馬具、埴輪(2022年2月16日)
- 「音楽のある街」のシンボル施設、60周年(2021年10月19日)
- 雨ニモマケズ手帳、県内初展示(2021年8月16日)
- 富岡製糸場の西置繭所が照明デザイン賞の優秀賞に(2021年5月31日)
- 街の片隅彩る草花知って(2021年5月15日)
- 名勝の宮崎公園でツツジ満開(2021年4月30日)
- 地元産の大豆から大ヒット(2020年12月13日)
- SLぐんまの客車改装、公開(2020年3月21日)
- 「ごんぎつね」に会いに高崎で企画展(2019年9月2日)
- 村のでっかい「恐竜王国」(2019年5月15日)
- 「鶴舞う形」の群馬皿、飲食店の盛り上げに一役(2018年10月18日)
- 豪商の夢の跡掘り進めると…(2018年9月30日)
- 金足農・吉田にブルゾンちえみ(2018年9月7日)
(この項おわり)
 大きな写真
大きな写真


1893年(明治26年)に三井に払い下げられ、1939年(昭和14年)には片倉製糸紡績会社(現・片倉工業)に経営が移ったが、1987年(昭和62年)に操業停止するまで一貫して製糸工場として稼働を続けた。