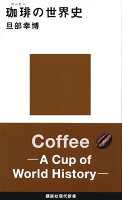
|
珈琲の世界史 | ||
| 著者 | 旦部 幸博 | ||
| 出版社 | 講談社 | ||
| サイズ | 新書 |

|
|
| 発売日 | 2017年10月18日頃 | ||
| 価格 | 1,056円(税込) | ||
| ISBN | 9784062884457 | ||
コーヒーに熱い思いを抱く人がいる限り、きっと何十年、何百年後も、地球のどこかで誰かが、その歴史に思いを馳せながら、1杯のコーヒーを飲んでいるに違いありません。(249ページ)
概要

戦後、コーヒー豆やインスタントコーヒーの輸入自由化された頃、私が産まれた。学生時代、個人経営の喫茶店に入り浸っていたが、これが第一次ブームの頃だ。これらの個人店は、バブル経済の加熱とともに閉店し寂しい思いをしたものだが、バブル崩壊後、スターバックスが上陸後し、再び喫茶店に足を運べるようになる。そして、現在のお気に入りはコンビニのレギュラーコーヒーだ。はるか昔、イエメンに現れたコーヒーの先祖に思いを馳せながら、今日もその香りと味を楽しむことにしよう。
レビュー

コーヒー豆がなるコーヒーノキの化石は、まだ発見されていない。ただ、近縁のアカネ科植物の花粉の化石から、約1440万年前の中央アフリカのカメルーン付近で誕生し、アフリカ大陸一帯の熱帯林に広がったと推測されている。
人類がいつコーヒーを見つけたかも明らかになっていないが、コーヒーという言葉はアラビア語の「カフワ qahwah」に由来するという。これがトルコ語の「カフヴェ kahve」になり、ヨーロッパに伝わった。日本にはオランダ人が最初に持ち込んだため、オランダ語のkoffieから、「コーヒー」という呼称が生まれた。「珈琲」という漢字は、中国語表記の「咖啡」から独自に考案したものと考えられている。
人類がいつコーヒーを見つけたかも明らかになっていないが、コーヒーという言葉はアラビア語の「カフワ qahwah」に由来するという。これがトルコ語の「カフヴェ kahve」になり、ヨーロッパに伝わった。日本にはオランダ人が最初に持ち込んだため、オランダ語のkoffieから、「コーヒー」という呼称が生まれた。「珈琲」という漢字は、中国語表記の「咖啡」から独自に考案したものと考えられている。

634~644年頃、イスラム教徒の一派が商売のためにエチオピアに渡った。このとき、コーヒーがイスラム圏内にもたらされたと考えられている。10~11世紀に書かれたアル=ラーズィーの「ブン」とイブン・スィーナーの「ブンクム」は、初めてコーヒーについて紹介している。その後、コーヒーは一時姿を消し、15世紀のイエメンで「カフワ」という飲み物として現れる。カフワは、15世紀初め、モカからイエメン各地のスーフィー教徒の間に広まる。
また、イエメンを支配したオスマン帝国は、外貨獲得に役立つコーヒーノキの栽培を奨励し、コーヒーが普及する。
また、イエメンを支配したオスマン帝国は、外貨獲得に役立つコーヒーノキの栽培を奨励し、コーヒーが普及する。

イスラム圏に広まったコーヒは、17世紀に入り、4つのルートを通ってヨーロッパに上陸する。1573年、レヴァントを旅行したドイツの医師で植物学者のレオンハルト・ラウヴォルフは、人々が「チャウベ」という飲み物を飲んでいるのを目撃し、『東方旅行の実録』(1582年)で紹介した。これがヨーロッパ人初のコーヒー目撃情報だ。

1630年代、イギリスにコーヒーが伝わり、コーヒー1杯2ペニーという安さのコーヒーハウスでは、カフェインの薬理作用で頭をはっきりさせ人々が政治談義に花を咲かせたようである。

パリのコーヒー店はフランス革命にも影響を与えた。バスティーユ襲撃の日、ジャコバン党に出入りしていたジャーナリストが、パレ・ロワイヤルの回廊にあるカフェ・ド・フォワのテラスから演説を行った。
ドイツでは、バッハの「コーヒー・カンタータ」が流行し、国の資金が海外に流出することを恐れたプロイセン王フリードリヒ2世は、1777年にコーヒー禁止令を布告したほどだった。
17世紀半ばにはアメリカに伝わり、ボストン茶会事件の前後でコーヒーの消費量は7倍に跳ね上がった。コーヒー豆不足になったアメリカでは、紅茶の代わりに薄いコーヒーが普及し、これがアメリカン・コーヒーの初まりである。
ドイツでは、バッハの「コーヒー・カンタータ」が流行し、国の資金が海外に流出することを恐れたプロイセン王フリードリヒ2世は、1777年にコーヒー禁止令を布告したほどだった。
17世紀半ばにはアメリカに伝わり、ボストン茶会事件の前後でコーヒーの消費量は7倍に跳ね上がった。コーヒー豆不足になったアメリカでは、紅茶の代わりに薄いコーヒーが普及し、これがアメリカン・コーヒーの初まりである。

ヨーロッパ列強で、最初にコーヒー栽培に手を出したのはオランダだったオランダ東インド会社は1619年にインドネシア・ジャワ島のバタヴィア(現在のジャカルタ)を占拠し、17世紀半ばに中継交易に翳りが見えはじめたため、植民地の住民に、指定した作物を栽培させ、安く買い上げて利益を得る方針に切り替えた。
コーヒーの覚醒作用の本体がカフェインで、そもそもヨーロッパの植物には存在しない、代用不能な成分だと判明したのはナポレオン戦争の終結後だった。1819年にフリードリープ・ルンゲが、文豪ゲーテにもらったモカの豆からカフェインを発見。
コーヒーの覚醒作用の本体がカフェインで、そもそもヨーロッパの植物には存在しない、代用不能な成分だと判明したのはナポレオン戦争の終結後だった。1819年にフリードリープ・ルンゲが、文豪ゲーテにもらったモカの豆からカフェインを発見。

ナポレオンもコーヒーの愛飲者で、流刑中のセントヘレナでは毎食後に欠かさずコーヒーを飲んでおり、亡くなる数日前にもコーヒーが欲しいと訴えたという。
ナポレオンが失脚し大陸封鎖が解かれ、ヨーロッパ全土でそれまでの不足を取り返すかのような消費拡大がおきた。
ナポレオンが失脚し大陸封鎖が解かれ、ヨーロッパ全土でそれまでの不足を取り返すかのような消費拡大がおきた。

ブームの中心になったのは中産階級の市民や知識人たちだった。アメリカで焙煎機の改良が相次ぎ、大量焙煎が可能になった。また、鉄道網の発達により、輸送や流通も改善された。
19世紀前半にはイエメンのコーヒーは、モカ以外の港から輸出されるようになった。ただし、どの港から出荷されても、取引時には「モカ」として高値が付き、ブランド化された。
19世紀前半にはイエメンのコーヒーは、モカ以外の港から輸出されるようになった。ただし、どの港から出荷されても、取引時には「モカ」として高値が付き、ブランド化された。
コーヒーは、政治体制にも影響を与えてきた。
1791年、コーヒー農園で働かされていたハイチの黒人奴隷が自由を求めて革命を起こし、奴隷制復活を目指して派兵されたナポレオンの遠征軍にも勝利して、1804年に世界初の黒人奴隷の革命政権として独立を果たした。
大陸封鎖令に従わなかったポルトガルは、1808年、ナポレオンの侵攻を受け、王族は植民地ブラジルのリオ・デ・ジャネイロに亡命し、ここを暫定首都とした。リオの産業やインフラは発展し、少し離れたヴァソーラスを中心にコーヒー栽培が盛んになった。
1898年、ベルギーでロブスタ種が発見され、コーヒーさび病に耐性があることが分かった。
1791年、コーヒー農園で働かされていたハイチの黒人奴隷が自由を求めて革命を起こし、奴隷制復活を目指して派兵されたナポレオンの遠征軍にも勝利して、1804年に世界初の黒人奴隷の革命政権として独立を果たした。
大陸封鎖令に従わなかったポルトガルは、1808年、ナポレオンの侵攻を受け、王族は植民地ブラジルのリオ・デ・ジャネイロに亡命し、ここを暫定首都とした。リオの産業やインフラは発展し、少し離れたヴァソーラスを中心にコーヒー栽培が盛んになった。
1898年、ベルギーでロブスタ種が発見され、コーヒーさび病に耐性があることが分かった。

第一次世界大戦に入ると、アメリカでインスタントコーヒーが普及した。戦時中はどの国でもコーヒーは軍に徴用されて、前線の兵士に支給された。カフェインが兵士の眠気防止や疲労感を軽減し、ストレスの軽減にもつながったからだ。


日本は、戦後から1980年代頃までの間に、焙煎や抽出の技術を国内で研鑽していった結果、まるでガラパゴス島のように独特の進化をとげたコーヒー文化を持つ国に成長した。
初めて文献に珈琲が登場するのは、江戸時代の1804年のことだ。明治に入り、1888年、上野黒門町で「可否茶館」という喫茶店が誕生する。ブラジル移民の父と呼ばれた水野龍が銀座に1911年2月に開業したのが「カフェー・パウリスタ」は、ブラジルから無償のコーヒー豆を提供され、低価格のコーヒーを出した。現在の日東珈琲だ。
初めて文献に珈琲が登場するのは、江戸時代の1804年のことだ。明治に入り、1888年、上野黒門町で「可否茶館」という喫茶店が誕生する。ブラジル移民の父と呼ばれた水野龍が銀座に1911年2月に開業したのが「カフェー・パウリスタ」は、ブラジルから無償のコーヒー豆を提供され、低価格のコーヒーを出した。現在の日東珈琲だ。

喫茶店では女給が働いており、これが、風俗店のようなカフェーに発展するが、戦後、GHQによって取り締まりの対象となる。
1960年には生豆輸入が自由化、1961年にはインスタントコーヒーが完全自由化された。1970年代から喫茶店は増加していき、1981年には5万件を超えて黄金期を迎える。だが、バブルで地価が急上昇。客単価が低い喫茶店は撤退を余儀なくされた。
1960年には生豆輸入が自由化、1961年にはインスタントコーヒーが完全自由化された。1970年代から喫茶店は増加していき、1981年には5万件を超えて黄金期を迎える。だが、バブルで地価が急上昇。客単価が低い喫茶店は撤退を余儀なくされた。

一方、アメリカでは、品質低下していく一方だったコーヒーに我慢できず、アルフレッド・ピートやエルナ・クヌッセンがスペシャルティコーヒーを提案した。そして1986年、シュルツがスターバックスのスタイルを確立した。
スペシャルティコーヒーは、画一化されて品質低下していくコモディティコーヒーに対する一つのアンチテーゼであり、フェアトレードの動きも広がった。1990年代に入ると、国際コーヒー協定が突然破綻し、コーヒー価格が大暴落を起こす。
この危機に際し、スターバックスは世界進出の足掛かりとして日本に上陸した。2000年代に入ると、スターバックスに対するアンチテーゼとして、コーヒーのサードウェーブが訪れる。
スペシャルティコーヒーは、画一化されて品質低下していくコモディティコーヒーに対する一つのアンチテーゼであり、フェアトレードの動きも広がった。1990年代に入ると、国際コーヒー協定が突然破綻し、コーヒー価格が大暴落を起こす。
この危機に際し、スターバックスは世界進出の足掛かりとして日本に上陸した。2000年代に入ると、スターバックスに対するアンチテーゼとして、コーヒーのサードウェーブが訪れる。

旦部さんは最後に、「コーヒーに熱い思いを抱く人がいる限り、きっと何十年、何百年後も、地球のどこかで誰かが、その歴史に思いを馳せながら、1杯のコーヒーを飲んでいるに違いありません。――そう、今のあなたや私と同じように。」(249ページ)と締めくくる。
(2019年9月1日 読了)
参考サイト
- 珈琲の世界史:講談社
- 『コーヒーの科学』:ぱふぅ家のホームページ
- @y_tambe(Y Tambe):Twitter
- 百珈苑
- カフェ・バッハ
- 10月1日はコーヒーの日:Twitterモーメント
- カフェー・パウリスタ
(この項おわり)

