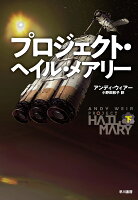概要

アンディ・ウィアー
著者は、2014年に『火星の人』でデビューしたアンディ・ウィアー。父親は素粒子物理学者、母親は電気技術者で、コンピュータ技術者として働いていた。『火星の人』はWeb小説として書き始められ、2011年にKindleの最低価格99セントで出版したところ、発売3ヶ月で3万5000ダウンロードを記録し、SF部門の売上げトップ5に。2015年には『オデッセイ』として映画化される。
上巻のあらすじ
人間は脳味噌をまるごと視覚に捧げていて、それ専用のキャッシュメモリまで持っている。(262ページ)

ぼくは目を覚ました。いったいどれだけ長いこと寝ていたのだろうか。酸素マスクを付けられている。体中に電極と管が取り付けられている。コンピュータが耳障りな音声で質問してくる。だが、ろれつが回らない。自分の名前も思い出せない。ここはどこだろう。
ようやく腕が動かせるようになった。体がやけに重たい。メールを読んだ。太陽から金星に向けて25.984ミクロンの赤外線を放射する星雲「ペトロヴァ・ライン」が見つかったという内容だ。
ぼくは歩けるようになった。同じ部屋にミイラ化した遺体が2つ。ぼくは、記憶を取り戻した。この場所がどこなのか、そして、ぼくがやるべき仕事を思い出した――。
ぼくは歩けるようになった。同じ部屋にミイラ化した遺体が2つ。ぼくは、記憶を取り戻した。この場所がどこなのか、そして、ぼくがやるべき仕事を思い出した――。
下巻のあらすじ
〈ヘイル・メアリー〉はいつ見てもハインラインの小説から抜け出してきたような姿をしている。銀色に輝くなめらかな船体、先が尖った船首。大気とかかわる必要のない宇宙船が、なぜそんな格好をしているのか?(171ページ)

タウ・ケチ星系のイメージ
ぼくは、寒冷化する地球を救うために、片道切符のヘイル・メアリー号に乗り込み11.9光年離れたタウ・セチにやって来た分子生物学者だ。タウ・セチで偶然出会ったロッキーの奇妙な共同研究が始まる――。
ぼくの科学知識とロッキーの技術力を合わせれば、かならず危機を救えると信じ、試行錯誤を繰り返し、けっして諦めず、ときには生命の危機に晒されることもあった。

ついにプロジェクト・ヘイル・メアリーは完了し、2人のその後がどうなったかというと‥‥。
ぼくの科学知識とロッキーの技術力を合わせれば、かならず危機を救えると信じ、試行錯誤を繰り返し、けっして諦めず、ときには生命の危機に晒されることもあった。
ついにプロジェクト・ヘイル・メアリーは完了し、2人のその後がどうなったかというと‥‥。
レビュー

突然、見知らぬ部屋に放り込まれたら、以前の記憶を失っていたら、あなたはそこが〈異世界〉だと考えるだろうか――主人公が研究対象にしていた地球外生命体はメタルスライムのようなものだが、大きさは10ミクロンしかない極小スライムだ。一人ぼっちの主人公は、神の力を頼るでもなく、チート魔法力を与えられたわけでもなく、地道に物理学の基礎実験を通じて自分の位置を確認する――20世紀末、ファンタジー小説にお株を奪われたオタク世界がSFに戻ってきた。

E.E.スミス『レンズマン』

本作では、いわゆる「悪人」が登場しない。登場人物の一人一人が、自らの職務を全うするために奔走する。冷酷無情なペトロヴァ対策委員会のエヴァ・ストラットも、最後にその思いを語る。人類存亡の危機に遭って、誰一人諦めない、くじけない、科学に全幅の信頼を寄せている。
ヘイル・メアリー・プロジェクトは完了し、主人公は、本来やりたかった仕事に戻ることができた――ただ、地球を出発する前とは少し違った形で――プロジェクトを通じて、人と出会い、想いを交わし、そして自分を変化させていく。
本作品は、良い意味で、スペースオペラのワクワク感と科学に対する信頼感を再認識させるSFである。
本作品は、良い意味で、スペースオペラのワクワク感と科学に対する信頼感を再認識させるSFである。
(2023年4月21日 読了)
参考サイト
- プロジェクト・ヘイル・メアリー 上巻:早川書房
- プロジェクト・ヘイル・メアリー 下巻:早川書房
- 『物理学者、SF映画にハマる』――科学に対する情熱:ぱふぅ家のホームページ
- 『SF挿絵画家の時代』――趣味を広げてくれた絵師さんに感謝:ぱふぅ家のホームページ
- 『輪廻の蛇』――そして、円環の理へ:ぱふぅ家のホームページ
- 『日本SF精神史』――楽しい文学史・近代史:ぱふぅ家のホームページ
(この項おわり)