
クイズラリー

館内は5つの展示室(宇宙の科学、生命の科学、生活の科学、地域の科学、地球の科学)に分かれているが、それぞれの内容に即したクイズを出題する端末が設置されている。このクイズに参加するには、自分の名前と写真が入るクイズラリー・カードを作る必要がある。

ミュージアムショップで白カードを100円で買って、クイズラリー発行機で写真を撮影して名前とともに印字する。
クイズのコースは、「幼児・低学年コース」か「上級コース」を選べる。カードは1年間使用でき、回答ポイントをためると景品と交換できる形になっている。
クイズのコースは、「幼児・低学年コース」か「上級コース」を選べる。カードは1年間使用でき、回答ポイントをためると景品と交換できる形になっている。

宇宙の科学

パパぱふぅは「宇宙の科学」コーナーがお勧めである。

スーパーカミオカンデで実際に使われている光電子倍増管である。直径50センチ――大きい。
2001年(平成13年)に、11,200本ある光電子倍増感の7割を破損するという大事故が起きたが、現場は大惨事になっていたことだろう。2006年(平成18年)4月に再建が完了し、現在、「SuperKamiokande-III」として調整が進められているところだ。
スーパーカミオカンデで実際に使われている光電子倍増管である。直径50センチ――大きい。
2001年(平成13年)に、11,200本ある光電子倍増感の7割を破損するという大事故が起きたが、現場は大惨事になっていたことだろう。2006年(平成18年)4月に再建が完了し、現在、「SuperKamiokande-III」として調整が進められているところだ。

光電子倍増管の近くには、小柴昌俊・東京大学特別栄誉教授のサイン色紙が展示されている。
小柴教授は、1987年(昭和62年)2月23日に大マゼラン雲で発生した超新星から飛来した大量のニュートリノを、1983年(昭和58年)に稼働開始したカミオカンデで検出したことでニュートリノ天文学という新天地を開拓し、2002年(平成14年)にノーベル物理学賞を受賞した。現場一筋の研究者として、たいへんな幸運に恵まれた天文学者である。
小柴教授は、1987年(昭和62年)2月23日に大マゼラン雲で発生した超新星から飛来した大量のニュートリノを、1983年(昭和58年)に稼働開始したカミオカンデで検出したことでニュートリノ天文学という新天地を開拓し、2002年(平成14年)にノーベル物理学賞を受賞した。現場一筋の研究者として、たいへんな幸運に恵まれた天文学者である。
小柴教授は、1926年(大正15年)愛知県生まれ。現在は杉並区に住んでいる。散歩が好きな好々爺として有名。杉並区は名誉区民の称号を贈るとともに、井荻川遊歩道を整備して「小柴ロード」と命名した
そういった税金のかけ方は本人の希望にそぐわないような気もするのだが、とくに意見を述べることもなく、飄々と全国の講演会に出かけているようである。いいお爺さんである。
そういった税金のかけ方は本人の希望にそぐわないような気もするのだが、とくに意見を述べることもなく、飄々と全国の講演会に出かけているようである。いいお爺さんである。

スペースシャトルの模型の近くには向井千秋・宇宙飛行士のサイン色紙があった。
向井飛行士はスペースシャトルに搭乗し、1994年(平成6年)7月と1998年(平成10年)10月に二度にわたって宇宙での様々な実験を行った女医さんである。一時期、フランス国際宇宙大学の客員教授として赴任していたが、2007年(平成19年)10月に宇宙航空研究開発機構(JAXA)筑波宇宙センターに戻り、宇宙医学生物学研究室の室長として活躍している。
向井飛行士はスペースシャトルに搭乗し、1994年(平成6年)7月と1998年(平成10年)10月に二度にわたって宇宙での様々な実験を行った女医さんである。一時期、フランス国際宇宙大学の客員教授として赴任していたが、2007年(平成19年)10月に宇宙航空研究開発機構(JAXA)筑波宇宙センターに戻り、宇宙医学生物学研究室の室長として活躍している。
特別展示「たまろく鉄道展出発進行!!」

今日の目当ては特別展示「たまろく鉄道展出発進行!!」だ。

交通アクセス
最寄り駅は西武新宿線花小金井駅だが、歩いて20分近くかかる。バスは、花小金井駅のほか、田無駅や吉祥寺駅からも出ている。

2007年(平成19年)10月19日、多摩六都科学館の構造設計に携わった設計事務所が、横浜市内の建築物について構造計算書を偽装していたことが分かった。そのため、急遽、15時に閉館し、安全が確保されるまでの間、休館することになった。
その後、偽装の事実はなく安全性が確認されたため、11月23日(金)より営業を再開した。
2007年(平成19年)10月19日、多摩六都科学館の構造設計に携わった設計事務所が、横浜市内の建築物について構造計算書を偽装していたことが分かった。そのため、急遽、15時に閉館し、安全が確保されるまでの間、休館することになった。
その後、偽装の事実はなく安全性が確認されたため、11月23日(金)より営業を再開した。

参考書籍
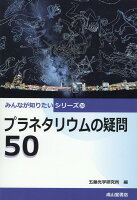
|
プラネタリウムの疑問50 | ||
| 著者 | 五藤光学研究所 | ||
| 出版社 | 成山堂書店 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2023年07月 | ||
| 価格 | 1,980円(税込) | ||
| ISBN | 9784425984312 | ||
| 100年の歴史を有するプラネタリウムについて、その誕生から現在までの移り変わり、しくみや楽しみ方、魅力などを、プラネタリウムの製造を行うメーカーの社員や、プラネタリウム施設の運営や投映(解説)を行う解説員が、わかりやすく紹介しています。この本を通じて、より多くの方々にプラネタリウムに興味を持っていただき、実際に訪れていただければ幸いです。 | |||
近隣の情報
- 多摩六都科学館でプラネタリウムを見る:ぱふぅ家のホームページ
- 辰年にちなんで田無神社に初詣:ぱふぅ家のホームページ
- 江戸東京たてもの園には「千と千尋の神隠し」のモデルとなった子宝湯がある:ぱふぅ家のホームページ
- 多摩湖自転車道を走る:ぱふぅ家のホームページ
- 多摩湖自転車道を走って狭山公園へ:ぱふぅ家のホームページ
- 江戸東京たてもの園で「東京大茶会」(2023年8月28日)
- 喫茶「くすの樹」跡にスターバックス、樹齢300年のクスノキを継承(2021年1月9日)
- 小金井の双ギャラリーで伊藤誠さん展示「知らない場所II」(2019年9月11日)
- レッドロブスター武蔵野関前店で50周年企画(2018年2月17日)
- ダイヤモンド富士25日まで見ごろ 東京に観測ポイント(2016年12月19日)
- 「千と千尋の神隠し」この街から? ライトアップ始まる(2016年11月27日)
- 中等科時代に思いはせ 両陛下が小金井公園訪問(2016年6月2日)
- 江戸東京たてもの園、夜間特別開園(2015年11月16日)
(この項おわり)
 大きな写真
大きな写真





多摩六都科学館は1994年(平成6年)6月にオープンした。小平市、東村山市、田無市、保谷市、清瀬市、東久留米市の6市が共同で開設したので「六都」の名が冠せられているが、のちに田無市と保谷市は合併して西東京市となっている。
サイエンスエッグは直径27.5メートルのドームで、プラネタリウムのほか、全天周映画などを上映している。開館当時は東洋一のプラネタリウムであった。2011年(平成23年)10月現在は世界第4位、東日本では最大。