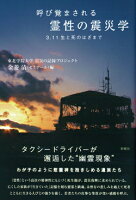
|
呼び覚まされる霊性の震災学 | ||
| 著者 | 東北学院大学/金菱清 | ||
| 出版社 | 新曜社 | ||
| サイズ | 単行本 |

|
|
| 発売日 | 2016年01月 | ||
| 価格 | 2,420円(税込) | ||
| ISBN | 9784788514577 | ||
タクシードライバーたちが体験した幽霊現象は、事実上、無賃乗車という扱いになっている。(10ページ)
概要
レビュー
最初に、石巻や気仙沼の多くのタクシードライバーが体験した幽霊現象を取材する。
タクシードライバーのひとりは、「最初はただただ怖く、しばらくその場から動けなかった」(5ページ)というが、いまでは「また同じように季節外れの冬服を着た人がタクシーを待っていることがあっても乗せるし、普通のお客さんと同じ扱いをするよ」と語る。このドライバーは、震災で娘さんを亡くしているという。
論者は、この現象について、絶望から畏敬が生まれたと結論づけている。

津波を受けて骨組みだけの無残な姿になった南三陸町防災対策庁舎を取り上げ、震災遺構を残すかどうか、遺族の心の移り変わりを取材する。論者は「負の遺産のシンボルである原爆ドームの永久保存にも20年という歳月が必要であった(65ページ)として、「時間は人びとの認識と心情の面で変化を与える。外部のさまざまな人びととの交流や環境の変化、供養という節目などがご遺族に変化をもたらしている」という。

津波で墓地が流されてしまった中浜の人びとは、「(新しく造成された)お墓と(流された墓地の後に建てられた)慰霊碑という異なる場でご先祖様に対して祈っている」(81ページ)。「遺骨が見つかっていないために、まだ元のお墓のあった場所にご先祖様の存在を感じる人もいる」というのだ。
「震災後、避難所や仮設住宅、お年寄りや子どもに復興のスポットライトが強烈にあたるなか、夫も子どももいて、家も流されなかった「普通のおばさん」は蚊帳の外におかれ、焦燥感と虚無感に苛まれ」(97ページ)、うつ状態になった母親がいる。
たった9人で、672人のご遺体を土葬し、再び掘り起こして荼毘に付す作業に従事した民間葬儀会社がある。「掘り起こしの現場で一番大事にしたのは、厳粛なイメージから懸け離れた“笑い”であった」(113ページ)という。
「東日本大震災での消防団の犠牲者数は、岩手県で119人、宮城県で107人、福鳥県で27人、計253人となった。同3県の消防本部の職員の犠牲者は27人だった」(128ページ)という。論者は、「消防団には明確な『目的』と『価値』がある」(145ページ)としたうえで、「この恨底が崩れない限り、彼らは再び現場へと向かうだろう」と結論づけた。

本書を執筆した学生は、高校3年の春に震災を体験したという。
当事者が書いた文章は主観的になりやすいという原則は当てはまらない。むしろ、客観的であるはずのマスメディアの方が偏っているのではないかと感じさせるほど、本書の調査は客観的で、微に入り細を穿っている。
本書を執筆した学生の皆さんは、このフィールドワークを忘れることなく、社会に貢献できる仕事に就かれんことを祈っている。また、今後遭遇するであろう艱難辛苦にあっては、ご遺体を掘り起こしていた葬儀会社を思い出し、笑顔で前へ進んでいってほしい。
そして、震災に見舞われた全ての皆さん、私たちは常にあなた方の側にいます。どうか、あきらめないでください。
タクシードライバーのひとりは、「最初はただただ怖く、しばらくその場から動けなかった」(5ページ)というが、いまでは「また同じように季節外れの冬服を着た人がタクシーを待っていることがあっても乗せるし、普通のお客さんと同じ扱いをするよ」と語る。このドライバーは、震災で娘さんを亡くしているという。
論者は、この現象について、絶望から畏敬が生まれたと結論づけている。
津波を受けて骨組みだけの無残な姿になった南三陸町防災対策庁舎を取り上げ、震災遺構を残すかどうか、遺族の心の移り変わりを取材する。論者は「負の遺産のシンボルである原爆ドームの永久保存にも20年という歳月が必要であった(65ページ)として、「時間は人びとの認識と心情の面で変化を与える。外部のさまざまな人びととの交流や環境の変化、供養という節目などがご遺族に変化をもたらしている」という。
津波で墓地が流されてしまった中浜の人びとは、「(新しく造成された)お墓と(流された墓地の後に建てられた)慰霊碑という異なる場でご先祖様に対して祈っている」(81ページ)。「遺骨が見つかっていないために、まだ元のお墓のあった場所にご先祖様の存在を感じる人もいる」というのだ。
「震災後、避難所や仮設住宅、お年寄りや子どもに復興のスポットライトが強烈にあたるなか、夫も子どももいて、家も流されなかった「普通のおばさん」は蚊帳の外におかれ、焦燥感と虚無感に苛まれ」(97ページ)、うつ状態になった母親がいる。
たった9人で、672人のご遺体を土葬し、再び掘り起こして荼毘に付す作業に従事した民間葬儀会社がある。「掘り起こしの現場で一番大事にしたのは、厳粛なイメージから懸け離れた“笑い”であった」(113ページ)という。
「東日本大震災での消防団の犠牲者数は、岩手県で119人、宮城県で107人、福鳥県で27人、計253人となった。同3県の消防本部の職員の犠牲者は27人だった」(128ページ)という。論者は、「消防団には明確な『目的』と『価値』がある」(145ページ)としたうえで、「この恨底が崩れない限り、彼らは再び現場へと向かうだろう」と結論づけた。
本書を執筆した学生は、高校3年の春に震災を体験したという。
当事者が書いた文章は主観的になりやすいという原則は当てはまらない。むしろ、客観的であるはずのマスメディアの方が偏っているのではないかと感じさせるほど、本書の調査は客観的で、微に入り細を穿っている。
本書を執筆した学生の皆さんは、このフィールドワークを忘れることなく、社会に貢献できる仕事に就かれんことを祈っている。また、今後遭遇するであろう艱難辛苦にあっては、ご遺体を掘り起こしていた葬儀会社を思い出し、笑顔で前へ進んでいってほしい。
そして、震災に見舞われた全ての皆さん、私たちは常にあなた方の側にいます。どうか、あきらめないでください。
(2016年3月5日 読了)
参考サイト
- 金菱清研究室:東北学院大学
- 奇跡の一本松と道の駅「高田松原」:ぱふぅ家のホームページ
- 常磐線不通区間の富岡駅から浪江駅へ:ぱふぅ家のホームページ
- 盛駅と三陸鉄道とBRT:ぱふぅ家のホームページ
- 九段会館は二・二六事件の時に戒厳司令部が置かれた:ぱふぅ家のホームページ
(この項おわり)

