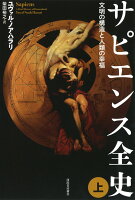
|
サピエンス全史(上) | ||
| 著者 | ユヴァル・ノア・ハラリ/柴田 裕之 | ||
| 出版社 | 河出書房新社 | ||
| サイズ | 単行本 |

|
|
| 発売日 | 2016年09月09日頃 | ||
| 価格 | 2,090円(税込) | ||
| ISBN | 9784309226712 | ||
不幸なことに、複雑な人間社会には想像上のヒエラルキーと不正な差別が必要なようだ。(174ページ)
サピエンス全史
| 時代 | イベント | アウトプット |
|---|---|---|
| 約7万年前 | 認知革命 | 抽象概念 アニミズム 集団による協調行動 |
| 約1万2千年前 | 農業革命 | 人口爆発 定住 労働時間増加 感染症リスク |
| 約5千年前 | 貨幣や文字の登場 | 交易の拡大 脳の容量を超えた記憶 神話・多神教 帝国の出現 |
| 約2千年前 | 一神教 | 秩序 グローバル社会 |
| 約500年前 | 科学革命 | 無知の革命 近代帝国主義 軍事力の増強 |
| 約300年前 | 産業革命 | エネルギー変換革命 資本主義 信用取引 個人主義 |
概要
著者は、イスラエル人歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリさん。本書は、世界で800万部を超えるベストセラーとなったそうだ。
上巻は、人類の発生から中世までを扱う歴史書ではあるが、年代や事件を解説しているわけではない。ホモ・サピエンスの本質を、認知革命、農業革命、神話といったキーワードを軸に掘り下げてゆく。貨幣や帝国が果たしてきた役割とは何か。そこから人権や差別、多様性といった現代の社会問題を考える。
世界史について、ある程度の知識があると、本書の視点が新鮮に感じられるであろう。だが、鵜呑みにする事なかれ。持っている知識を動員して本書の内容を考察することこそ、著者が求めていることだと感じた。
上巻は、人類の発生から中世までを扱う歴史書ではあるが、年代や事件を解説しているわけではない。ホモ・サピエンスの本質を、認知革命、農業革命、神話といったキーワードを軸に掘り下げてゆく。貨幣や帝国が果たしてきた役割とは何か。そこから人権や差別、多様性といった現代の社会問題を考える。
世界史について、ある程度の知識があると、本書の視点が新鮮に感じられるであろう。だが、鵜呑みにする事なかれ。持っている知識を動員して本書の内容を考察することこそ、著者が求めていることだと感じた。
レビュー
いまから7万年前、アフリカ大陸を再出発したホモ・サピエンスは、ホモ・エレクトスやネアンデルタール人にない高い認知的能力を備えた「認知革命」を達成し、唯一の人類になったと考えられている。抽象概念を扱えるようになったホモ・サピエンスは、チンパンジーなどの「群れ」とは比較にならない大規模な組織を統率できるようになった。
この仮説は、先日読んだ後藤明さんの『世界神話学入門』とも通じる。つまり、他の人類の宗教はゴンドワナ型神話をベースにしているが、再出発したサピエンスのそれはローラシア型神話なのである。
ハラリさんは、法人格や法律も、神話・宗教と同列としている。交易もサピエンスしか行っていないことをあげ、「認知革命は歴史が生物学から独立を宣言した時点だ」(55ページ)と説く

1万2千年前の農業革命が始まるまで、サピエンスは狩猟採集の生活にあった。この時代は、健康に良い多様な食材を手に入れ、労働時間が短く、感染症も少ない「原初の豊かな社会」であった。サピエンスは集団生活を営んでおり、一夫一婦制ではなかった。ハラリさんは、現代の不倫は狩猟採集時代の記憶の名残ではないかと指摘する。
また、この時代のサピエンスはアニミズムを信仰していたといるが、アニミズムは体系化されているものではなく、当時の生活は依然として謎に包まれていると書いている。
感染症が少ないのは、集団同士の物理的距離があったことと、集団が違うと生活も違ったことが要因と考えられているが、多様性を考えるうえで、振り返っておきたい。

サピエンスが南太平洋を航行した証拠は発見されていないものの、いまから4万5千年前にオーストラリア大陸へ渡った。そこで、独自に進化した動物の多くを絶滅させた。一方、脂肪に富むマンモスなどを追った集団は、陸伝いにシベリアからアラスカへ移動し、1万年前には南アメリカの南端へ到達した。ここでも、多くの動物を絶滅させてきた。ハラリさんは、サピエンスを「史上最も危険な種」と書いている。

ハラリさんは、1万2千年前から始まった農業革命を「史上最大の詐欺」という。なぜなら、狩猟採集の時代より労働時間が増え、得られる食料が減ったからだ。だが、単位面積あたりの収穫量が増えたことにより、人口は爆発的に増えることになる。酪農も同様。増えた人口を養うために、サピエンスの農作業は次第に過酷なものとなっていった。
サピエンスと小麦のDNAが、個体の生存環境ではなく、自己複製を優先させた結果かもしれない。もちろんDNAに意志があるわけではない。だが、我々が「意志」と信じているものの正体は何だろう――そして、我々が便利になると考えて受けいれてきた文明の利器は、本当に生活を豊かにしただろうか。

ハラリさんは、ハンムラビ法典は神話と同質と説く。たしかに、その前文にはバビロニアの神々の名前が列挙され、そうした神々の名の下に法典が作られたと記されている。
さらにハラリさんは、アメリカ独立宣言もハンムラビ法典と同質だと言う(ハンムラビ法典が紀元前1776年、独立宣言を西暦1776年として対比するという皮肉)。歴史の授業では、王権神授説を脱却した人類の叡智とされる独立宣言であるが、冷静に考えてみれば、人権には実体がなく、その解釈をめぐって21世紀の今日でも百家争鳴なのである。ハラリさんの言葉を借りれば、これらは「サピエンスの社会秩序は想像上のもの」(155ページ)なのである。

農業革命を経て、数千~数万人の住民を養う穀物を生産できるようになったものの、そうした記録はサピエンスの脳の記憶に収まりきらない。そこで「書記」が登場する。最初のシュメール文字は、散文を書くためのものではなく、こうした定量記録を残すためのものだった。その子孫がインカのキープ文字である。散文が書けなくても、インカ人は不便を感じなかったのであろう。
9世紀に入ってヨーロッパに輸入されたゼロを含むアラビア数字は、記録文字としては全世界で通用するものになった。アラビア数字は数学という抽象的な学問を扱うことができるから、「想像上の産物」を扱うのに都合がいいツールとなった。

法律、体制や数字といったサピエンスの「神話=想像上の産物」の副産物として、ヒエラルキーが発生する。社会的地位は、べつに生物学的な根拠があるわけではない。ハラリさんは、「これらのヒエラルキーはすべて人類の想像力の産物」(173ページ)という。
また、「不幸なことに、複雑な人間社会には想像上のヒエラルキーと不正な差別が必要」(174ページ)と指摘する一方で、「ヒエラルキーのおかげで、見ず知らずの人どうしが、個人的に知り合うために必要とされる時間とエネルギーを浪費しなくても、お互いをどう扱うべきなのか知ることができる」とも書いている。
そして歴史を俯瞰すると、サピエンスの社会は統合する方へと進んでいるという。グローバリゼーションだ。
この仮説は、先日読んだ後藤明さんの『世界神話学入門』とも通じる。つまり、他の人類の宗教はゴンドワナ型神話をベースにしているが、再出発したサピエンスのそれはローラシア型神話なのである。
ハラリさんは、法人格や法律も、神話・宗教と同列としている。交易もサピエンスしか行っていないことをあげ、「認知革命は歴史が生物学から独立を宣言した時点だ」(55ページ)と説く
1万2千年前の農業革命が始まるまで、サピエンスは狩猟採集の生活にあった。この時代は、健康に良い多様な食材を手に入れ、労働時間が短く、感染症も少ない「原初の豊かな社会」であった。サピエンスは集団生活を営んでおり、一夫一婦制ではなかった。ハラリさんは、現代の不倫は狩猟採集時代の記憶の名残ではないかと指摘する。
また、この時代のサピエンスはアニミズムを信仰していたといるが、アニミズムは体系化されているものではなく、当時の生活は依然として謎に包まれていると書いている。
感染症が少ないのは、集団同士の物理的距離があったことと、集団が違うと生活も違ったことが要因と考えられているが、多様性を考えるうえで、振り返っておきたい。
サピエンスが南太平洋を航行した証拠は発見されていないものの、いまから4万5千年前にオーストラリア大陸へ渡った。そこで、独自に進化した動物の多くを絶滅させた。一方、脂肪に富むマンモスなどを追った集団は、陸伝いにシベリアからアラスカへ移動し、1万年前には南アメリカの南端へ到達した。ここでも、多くの動物を絶滅させてきた。ハラリさんは、サピエンスを「史上最も危険な種」と書いている。
ハラリさんは、1万2千年前から始まった農業革命を「史上最大の詐欺」という。なぜなら、狩猟採集の時代より労働時間が増え、得られる食料が減ったからだ。だが、単位面積あたりの収穫量が増えたことにより、人口は爆発的に増えることになる。酪農も同様。増えた人口を養うために、サピエンスの農作業は次第に過酷なものとなっていった。
サピエンスと小麦のDNAが、個体の生存環境ではなく、自己複製を優先させた結果かもしれない。もちろんDNAに意志があるわけではない。だが、我々が「意志」と信じているものの正体は何だろう――そして、我々が便利になると考えて受けいれてきた文明の利器は、本当に生活を豊かにしただろうか。
ハラリさんは、ハンムラビ法典は神話と同質と説く。たしかに、その前文にはバビロニアの神々の名前が列挙され、そうした神々の名の下に法典が作られたと記されている。
さらにハラリさんは、アメリカ独立宣言もハンムラビ法典と同質だと言う(ハンムラビ法典が紀元前1776年、独立宣言を西暦1776年として対比するという皮肉)。歴史の授業では、王権神授説を脱却した人類の叡智とされる独立宣言であるが、冷静に考えてみれば、人権には実体がなく、その解釈をめぐって21世紀の今日でも百家争鳴なのである。ハラリさんの言葉を借りれば、これらは「サピエンスの社会秩序は想像上のもの」(155ページ)なのである。
農業革命を経て、数千~数万人の住民を養う穀物を生産できるようになったものの、そうした記録はサピエンスの脳の記憶に収まりきらない。そこで「書記」が登場する。最初のシュメール文字は、散文を書くためのものではなく、こうした定量記録を残すためのものだった。その子孫がインカのキープ文字である。散文が書けなくても、インカ人は不便を感じなかったのであろう。
9世紀に入ってヨーロッパに輸入されたゼロを含むアラビア数字は、記録文字としては全世界で通用するものになった。アラビア数字は数学という抽象的な学問を扱うことができるから、「想像上の産物」を扱うのに都合がいいツールとなった。
法律、体制や数字といったサピエンスの「神話=想像上の産物」の副産物として、ヒエラルキーが発生する。社会的地位は、べつに生物学的な根拠があるわけではない。ハラリさんは、「これらのヒエラルキーはすべて人類の想像力の産物」(173ページ)という。
また、「不幸なことに、複雑な人間社会には想像上のヒエラルキーと不正な差別が必要」(174ページ)と指摘する一方で、「ヒエラルキーのおかげで、見ず知らずの人どうしが、個人的に知り合うために必要とされる時間とエネルギーを浪費しなくても、お互いをどう扱うべきなのか知ることができる」とも書いている。
そして歴史を俯瞰すると、サピエンスの社会は統合する方へと進んでいるという。グローバリゼーションだ。
(2018年12月15日 読了)
科学は自らの優先順位を設定できない。また、自らが発見した物事をどうするかも決められない。(88ページ)
概要
イスラエル人歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリさんが著した『サピエンス全史』の下巻は、中世から科学革命を経て、現代までの人類史を俯瞰する。上巻同様、年代や事件を解説してするわけではなく、宗教、イデオロギー、科学革命、資本主義、産業革命といったキーワードを軸に掘り下げる。
いままでの歴史書とは視点が全く異なる本書だが、「科学革命は無知の革命」「産業革命はエネルギー変換における革命」というハラリさんの主張が、果たして本当にそうなのか、自分自身の頭で考察することが大切だし、ハラリさんもそれを読者に求めているような気がした。

終盤で、幸福とは何か、ホモ・サピエンスがまったく違うものに変容するのではないかという未来予測を述べる。人類が進化したらどうなるかという話は、アーサー・C・クラーク『幼年期の終わり』をはじめとして、SFでよく取り上げられるテーマだ。子どもや孫の世代では、そう劇的な変化は現れないかもしれない。
超ホモ・サピエンスの話はやや消化不良の感じがするが、次回作『ホモ・デウス』で明らかにされることを期待しつつ、「私たちは何になりたいのか」という問題意識を常に持ち続けるようにしよう。
いままでの歴史書とは視点が全く異なる本書だが、「科学革命は無知の革命」「産業革命はエネルギー変換における革命」というハラリさんの主張が、果たして本当にそうなのか、自分自身の頭で考察することが大切だし、ハラリさんもそれを読者に求めているような気がした。
終盤で、幸福とは何か、ホモ・サピエンスがまったく違うものに変容するのではないかという未来予測を述べる。人類が進化したらどうなるかという話は、アーサー・C・クラーク『幼年期の終わり』をはじめとして、SFでよく取り上げられるテーマだ。子どもや孫の世代では、そう劇的な変化は現れないかもしれない。
超ホモ・サピエンスの話はやや消化不良の感じがするが、次回作『ホモ・デウス』で明らかにされることを期待しつつ、「私たちは何になりたいのか」という問題意識を常に持ち続けるようにしよう。
レビュー
下巻ではまず、キリスト教やイスラム教といった一神教を取り上げる。
ハラリさんは、宗教は差別の根源ではなく、「貨幣や帝国と並んで、宗教もこれまでずっと、人類を統一する3つの要素の1つだった」(10ページ)と指摘する。人間の気まぐれではなく、「絶対的な至上の権威が定めた」ルールによって社会の秩序がもたらされたからだ。
さらにハラリさんは、イデオロギーも宗教と同等だと語る。なぜなら、宗教に神が必須だとするなら、一貫性を保つためには「仏教や道教、ストア主義のいくつかの宗派を宗教ではなくイデオロギーに分類せざるをえなくなる」(33ページ)からだ。
共和政体では政教分離が前提とされるが、これは人間が勝手にそう思っているだけで、米国大統領の就任式で聖書に手を置いて宣誓をする映像を見るにつけ、キリスト教徒は意識しないのかもしれないが、私たち日本人から見れば、両者は確かに不可分の関係にあることが自明に映る。逆に、キリスト教徒から日本の政治やイデオロギーを見たときにも、同様な感想を持たれるだろう。

ハラリさんは、「歴史は正確な予想をするための手段ではない」と前置きした上で、歴史研究の目的は、「未来を知るためではなく、視野を拡げ、現在の私たちの状況は自然なものでも必然的なものでもなく、したがって私たちの前には、想像しているよりもずっと多くの可能性があることを理解するため」(48ページ)と語る。そして、「歴史が決定論的ではないことを認めれば、今日ほとんどの人が国民主義や資本主義、人権を信奉するのはただの偶然だと認めることになる」(46ページ)と指摘する。

近代に入って科学革命が起きる。ハラリさんは、宗教は「この世界について知るのが重要である事柄はすでに全部知られていると主張」したが、科学は「人類は自らにとって最も重要な疑問の数々の答えを知らない」(59ページ)という無知の革命だったと指摘する。
そして、「科学は自らの優先順位を設定できない。また、自らが発見した物事をどうするかも決められない」(88ページ)ため、産業や軍事と結びついた。
ハリラさんは、天文学者をタヒチへ運んだイギリスのクック船長を例に、科学が軍事と結びついて、ヨーロッパ帝国主義が太平洋を収奪したことを紹介する。

価額と貨幣の発達は、資本主義革命をもたらした。ハラリさんは、資本主義革命の本質は、信用取引にあると説く。
中世の宗教観では、富の総量限られており、信用を与えてもそれが回収できると考えられなかった。だからイエス・キリストは信用取引を戒めた。また、本書では触れられていないが、イスラム銀行が金利を設定しないのも、同じ理由からではないだろうか。つまり、中世はゼロサムゲームだった。
科学は、サピエンス社会に止まることのない成長をもたらした。信用を与え、それが回収できる可能性が高まったのだ。
だが、自由市場資本主義には欠点もある。1719年のミシシッピ・バブルを紹介し、「利益が公正な方法で得られることも、公正な方法で分配されることも保証できない」(159ページ)と指摘する。ハラリさんは、国家による市場介入は避けられないと主張する。

科学と資本主義は産業革命をもたらした。ハラリさんは、「産業革命は、エネルギー変換における革命」(169ページ)と説く。蒸気機関は、熱エネルギーを運動エネルギーに変換した。そして、「私たちは数十年ごとに新しいエネルギー源を発見するので、私たちが使えるエネルギーの総量は増える一方」(169ページ)という。
国家や市場は、家族やコミュニティの絆を弱めた。「個人になるのだ」と提唱したのだ。

終盤で、ハラリさんは、「私たちは以前より幸せになっただろうか?」(214ページ)と問いかける。この問いかけこそ、本書が他の歴史書と一線を画すものである。
「2000年には、戦争で31万人が亡くなり、暴力犯罪によって52万人が命を落とした」(200ページ)ことを挙げ、「人々が戦争を想像することすらできないほどに平和が広まった例は、これまでに一度もなかった」(209ページ)と指摘する。
マスコミは地域紛争を取り上げ、1人でも命を落とせば、人の命は地球よりも重たいとロマンチックに喧伝する。しかし、現実問題として、「戦争は採算が合わなくなる一方で、平和からはこれまでにないほどの利益が挙がるようになった」(211ページ)。
ハラリさんは、幸福を感じるのは、生物学的現象としては、セロトニンやドーパミンといった化学物質によってニューロンやシナプスが刺激を受けることだとしたうえで、「脳の化学的特性の理解と適切な治療の開発に投じれば、革命などいっさい起こさずに、人々をこれまでより格段に幸せにすることができる」(231ページ)と主張する。

最終章では、上巻冒頭で触れた認知革命が、脳の生理機能にとくに目立った変化を必要としなかったことから、「再びわずかな変化がありさえすれば―(中略)―ホモ・サピエンスを何かまったく違うものに変容させることになるかもしれない」(249ページ)という。
ただ、幸福と超ホモ・サピエンスをめぐる話は、少々、消化不良の感じがする。次の作品『ホモ・デウス』で明らかにされることを期待しよう。
ハラリさんは最後に、「私たちは、最後にもう一つだけ疑問に答えるために時間を割くべきだろう。その疑問とは、私たちは何になりたいのか、だ」(262ページ)と述べる。同感である。
ハラリさんは、宗教は差別の根源ではなく、「貨幣や帝国と並んで、宗教もこれまでずっと、人類を統一する3つの要素の1つだった」(10ページ)と指摘する。人間の気まぐれではなく、「絶対的な至上の権威が定めた」ルールによって社会の秩序がもたらされたからだ。
さらにハラリさんは、イデオロギーも宗教と同等だと語る。なぜなら、宗教に神が必須だとするなら、一貫性を保つためには「仏教や道教、ストア主義のいくつかの宗派を宗教ではなくイデオロギーに分類せざるをえなくなる」(33ページ)からだ。
共和政体では政教分離が前提とされるが、これは人間が勝手にそう思っているだけで、米国大統領の就任式で聖書に手を置いて宣誓をする映像を見るにつけ、キリスト教徒は意識しないのかもしれないが、私たち日本人から見れば、両者は確かに不可分の関係にあることが自明に映る。逆に、キリスト教徒から日本の政治やイデオロギーを見たときにも、同様な感想を持たれるだろう。
ハラリさんは、「歴史は正確な予想をするための手段ではない」と前置きした上で、歴史研究の目的は、「未来を知るためではなく、視野を拡げ、現在の私たちの状況は自然なものでも必然的なものでもなく、したがって私たちの前には、想像しているよりもずっと多くの可能性があることを理解するため」(48ページ)と語る。そして、「歴史が決定論的ではないことを認めれば、今日ほとんどの人が国民主義や資本主義、人権を信奉するのはただの偶然だと認めることになる」(46ページ)と指摘する。
近代に入って科学革命が起きる。ハラリさんは、宗教は「この世界について知るのが重要である事柄はすでに全部知られていると主張」したが、科学は「人類は自らにとって最も重要な疑問の数々の答えを知らない」(59ページ)という無知の革命だったと指摘する。
そして、「科学は自らの優先順位を設定できない。また、自らが発見した物事をどうするかも決められない」(88ページ)ため、産業や軍事と結びついた。
ハリラさんは、天文学者をタヒチへ運んだイギリスのクック船長を例に、科学が軍事と結びついて、ヨーロッパ帝国主義が太平洋を収奪したことを紹介する。
価額と貨幣の発達は、資本主義革命をもたらした。ハラリさんは、資本主義革命の本質は、信用取引にあると説く。
中世の宗教観では、富の総量限られており、信用を与えてもそれが回収できると考えられなかった。だからイエス・キリストは信用取引を戒めた。また、本書では触れられていないが、イスラム銀行が金利を設定しないのも、同じ理由からではないだろうか。つまり、中世はゼロサムゲームだった。
科学は、サピエンス社会に止まることのない成長をもたらした。信用を与え、それが回収できる可能性が高まったのだ。
だが、自由市場資本主義には欠点もある。1719年のミシシッピ・バブルを紹介し、「利益が公正な方法で得られることも、公正な方法で分配されることも保証できない」(159ページ)と指摘する。ハラリさんは、国家による市場介入は避けられないと主張する。
科学と資本主義は産業革命をもたらした。ハラリさんは、「産業革命は、エネルギー変換における革命」(169ページ)と説く。蒸気機関は、熱エネルギーを運動エネルギーに変換した。そして、「私たちは数十年ごとに新しいエネルギー源を発見するので、私たちが使えるエネルギーの総量は増える一方」(169ページ)という。
国家や市場は、家族やコミュニティの絆を弱めた。「個人になるのだ」と提唱したのだ。
終盤で、ハラリさんは、「私たちは以前より幸せになっただろうか?」(214ページ)と問いかける。この問いかけこそ、本書が他の歴史書と一線を画すものである。
「2000年には、戦争で31万人が亡くなり、暴力犯罪によって52万人が命を落とした」(200ページ)ことを挙げ、「人々が戦争を想像することすらできないほどに平和が広まった例は、これまでに一度もなかった」(209ページ)と指摘する。
マスコミは地域紛争を取り上げ、1人でも命を落とせば、人の命は地球よりも重たいとロマンチックに喧伝する。しかし、現実問題として、「戦争は採算が合わなくなる一方で、平和からはこれまでにないほどの利益が挙がるようになった」(211ページ)。
ハラリさんは、幸福を感じるのは、生物学的現象としては、セロトニンやドーパミンといった化学物質によってニューロンやシナプスが刺激を受けることだとしたうえで、「脳の化学的特性の理解と適切な治療の開発に投じれば、革命などいっさい起こさずに、人々をこれまでより格段に幸せにすることができる」(231ページ)と主張する。
最終章では、上巻冒頭で触れた認知革命が、脳の生理機能にとくに目立った変化を必要としなかったことから、「再びわずかな変化がありさえすれば―(中略)―ホモ・サピエンスを何かまったく違うものに変容させることになるかもしれない」(249ページ)という。
ただ、幸福と超ホモ・サピエンスをめぐる話は、少々、消化不良の感じがする。次の作品『ホモ・デウス』で明らかにされることを期待しよう。
ハラリさんは最後に、「私たちは、最後にもう一つだけ疑問に答えるために時間を割くべきだろう。その疑問とは、私たちは何になりたいのか、だ」(262ページ)と述べる。同感である。
(2018年12月20日 読了)
(この項おわり)


