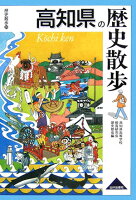足摺岬灯台

2022年5月27日 撮影
足摺岬灯台は、足摺宇和海国立公園にそびえ立つ高さ18メートルの白亜の灯台である。1914年(大正3年)に点灯し、1960年(昭和35年)に現在の形に改築された。46万カンデラの明かりは、約38キロ先まで届く。
 大きな写真
大きな写真
 大きな写真
大きな写真
(2560×1707 ピクセル, 1945 Kbyte)

2022年5月27日 撮影

2007年7月30日 撮影
展望台からの視界は270度におよぶ。灯火の標高は60.6メートル。

2007年7月30日 撮影
1914年(大正3年)4月の初点灯当時は八角形のコンクリート造りで、第4等フレネル式レンズを使用していた。

1960年(昭和35年)7月、現在のロケット型に改築された。
光度46万カンデラ、光達距離38kmは、わが国で最大級の灯台のひとつである。
1960年(昭和35年)7月、現在のロケット型に改築された。
光度46万カンデラ、光達距離38kmは、わが国で最大級の灯台のひとつである。

2022年5月27日 撮影

2022年5月27日 撮影
南国を感じさせる。
中村駅からは足摺岬行きの路線バスが、特急の到着時刻に合わせて出ている。このバスに乗って終点の足摺岬まで1時間45分(約50キロ)――かなり無茶な移動である。

2007年7月30日 撮影
乗っているうちに、バスの運賃表(電光掲示板)が一杯になってしまった。
基本的に国道沿いに走っているのだが、路線バスなので、ジョン万次郎の故郷である中浜や、足摺の集落にも立ち寄る。海岸線ギリギリを走る細い路地で、バスが通れること自体信じられない。
基本的に国道沿いに走っているのだが、路線バスなので、ジョン万次郎の故郷である中浜や、足摺の集落にも立ち寄る。海岸線ギリギリを走る細い路地で、バスが通れること自体信じられない。
さらに県道27号線に入って足摺岬へ向かうのだが、路線バスの乗客はぱふぅ家だけ。対向車とすれ違うことが出来ないほど狭く曲がりくねった道路だ。所々に待避スペースがあり、高知ナンバーの対向車と阿吽の呼吸ですり抜けていく。県外の乗用車など1台も見かけない。自動車で訪れるのは避けた方がいいだろう。
金剛福寺

2007年7月30日 撮影

2022年5月27日 撮影

2022年5月27日 撮影

2007年7月30日 撮影
仁王門(山門)をくぐる。

2022年5月27日 撮影
境内には亜熱帯植物が生い茂り、左側には池が広がり、多くの奇岩が配置されている――京都・奈良の古刹とは違い、荒々しさを感じる。

2022年5月27日 撮影
本堂と大師堂の間にある行者堂のあたりは、岩の間を縫うようにして進む。

2022年5月27日 撮影
弘法大師空海が沖の岩で修行するために亀を呼んで渡ったというエピソードを体現できるようになっている。
また、歴代天皇の祈願所とされたほか、源氏の信仰が篤く、源満仲は多宝塔を寄進した。
また、歴代天皇の祈願所とされたほか、源氏の信仰が篤く、源満仲は多宝塔を寄進した。

2022年5月27日 撮影
百八仏と献燈十二句碑――五智如来・十三仏・千手観音の鋳造仏が108体、配置されている。
足摺岬

2007年7月30日 撮影

2022年5月27日 撮影
足摺半島南東端に位置、黒潮の打ち寄せる断崖は約80メートルの高さ――高いところが苦手な人は要注意。

2022年5月27日 撮影

2022年5月27日 撮影
1976年(昭和51年)7月に、皇太子殿下(現・太上天皇陛下)が足摺岬に立ち寄られ、その様子を翌1977年(昭和52年)の歌会始の時に読まれた歌を記念として歌碑として建立した。

2022年5月27日 撮影
ジョン万次郎(中浜万次郎;1827~1898年)の銅像が、足摺岬観光案内所前にある。
漁師の次男として生まれた万次郎は、幼い頃に父を亡くし、1841年(天保11年)、14歳のとき、仲間とともに漁に出ていて遭難。アメリカの捕鯨船に救助され、そのまま渡米。英語・数学・測量・航海術・造船技術などを学び、1851年(嘉永4年)に帰国。
万次郎はアメリカでの生活や学問を著し、坂本龍馬や多くの幕末志士たちの目に触れたと考えられている。さらに、後藤象二郎や岩崎弥太郎は直接指導を受けた。ペリー来航で外国の情報を必要としていた幕府に重用され、咸臨丸にも乗り込んだ。
漁師の次男として生まれた万次郎は、幼い頃に父を亡くし、1841年(天保11年)、14歳のとき、仲間とともに漁に出ていて遭難。アメリカの捕鯨船に救助され、そのまま渡米。英語・数学・測量・航海術・造船技術などを学び、1851年(嘉永4年)に帰国。
万次郎はアメリカでの生活や学問を著し、坂本龍馬や多くの幕末志士たちの目に触れたと考えられている。さらに、後藤象二郎や岩崎弥太郎は直接指導を受けた。ペリー来航で外国の情報を必要としていた幕府に重用され、咸臨丸にも乗り込んだ。

2007年7月30日 撮影
足摺宇和海国立公園には、足摺七不思議といわれている伝説があり、けっこう楽しめる。時間があれば、全部回ってみたかった。

2022年5月27日 撮影
採訪したので、足摺七不思議をめぐってみた。
地獄の穴は、今は埋まっているが、この穴に銭を落とすと、チリンチリンと音がして落ちて行き、その穴は金剛福寺付近まで通じるといわれている。
地獄の穴は、今は埋まっているが、この穴に銭を落とすと、チリンチリンと音がして落ちて行き、その穴は金剛福寺付近まで通じるといわれている。

2022年5月27日 撮影
亀呼場は、弘法大師空海が、ここから亀を呼び、亀の背中に乗って前の不動岩に渡り、祈祷をしたといわれている。

2022年5月27日 撮影
ゆるぎ石は、弘法大空海が金剛福寺を建立した時発見した石で、乗り揺るがすと、その動揺の程度によって孝心をためすといわれている。

2007年7月30日 撮影
参考書籍
近隣の情報
- 足摺岬と弘法大師:ぱふぅ家のホームページ
- 四万十川のウナギはワイルドだが脂っこくない:ぱふぅ家のホームページ
- 高校生が開発したお菓子をみずから販売(2025年1月31日)
- 四万十川の大空にこいのぼり500匹(2022年4月12日)
- 秋風にゆらゆら、スルメイカ天日干し(2021年11月7日)
- 四国最南端の足摺海洋館、入館者20万人を突破(2021年6月4日)
- ギンナンを割る音響く夜の街(2019年11月25日)
- 餅つきで帰省客もてなし土佐くろしお鉄道(2019年1月7日)
- 土佐くろしお鉄道にXマス列車高校生が飾り付け(2018年11月21日)
- 世界で唯一土佐清水にすむサンショウウオ特別展示(2018年9月18日)
- 土佐くろしお中村線開業30周年記念マーク掲出(2018年6月11日)
- 一條公、玉姫 中村ぶらり(2017年10月29日)
- 高知県黒潮町の道の駅でタコクラゲの瓶詰め人気 癒やされる(2016年9月8日)
参考サイト
- 足摺岬灯台:土佐清水市
- 足摺岬・足摺岬灯台:土佐清水観光協会
- 蹉跎山 補陀洛院 金剛福寺:四国八十八ヶ所霊場會
- 第38番札所 金剛福寺:土佐清水市
- 高野山 奥之院:ぱふぅ家のホームページ
- 金剛峯寺は高野山真言宗の総本山:ぱふぅ家のホームページ
- 『高野山』――敵も味方も高野山に眠る:ぱふぅ家のホームページ
- 足摺宇和海国立公園:環境省
(この項おわり)