
赤坂見附から虎ノ門に至る長さ1.4km、幅45m~190mといった大きさで、不忍池より大きい。かなり細長い溜池で、ひょうたん池とも呼ばれていた。
もともと江戸は飲料水に乏しく、和歌山藩の浅野幸長が1606年(慶長11年)に造った人造湖である。
溜池は水質もよく、風景も美しく、浮世絵などによく描かれた。琵琶湖や淀川からわざわざコイやフナを取り寄せて放したと伝わっており、ハスを植えてその花を鑑賞し蓮根を採取したという。
宝永4年(1707年)と享保年間(1716~1736年)の間にその一部が埋立てられたが、1875年(明治8年)から本格的に埋立てが始まり、1888年(明治21年)に溜池町が成立した。
もともと江戸は飲料水に乏しく、和歌山藩の浅野幸長が1606年(慶長11年)に造った人造湖である。
溜池は水質もよく、風景も美しく、浮世絵などによく描かれた。琵琶湖や淀川からわざわざコイやフナを取り寄せて放したと伝わっており、ハスを植えてその花を鑑賞し蓮根を採取したという。
宝永4年(1707年)と享保年間(1716~1736年)の間にその一部が埋立てられたが、1875年(明治8年)から本格的に埋立てが始まり、1888年(明治21年)に溜池町が成立した。
しかし、なにしろ窪地であるため、最近も大雨で何度か冠水している。仕事で来る機会が多いものだから、地下鉄の駅にいるときは恐怖である。

ちなみに、ここから六本木通りを北東に向かうと皇居である。六本木通りは皇室専用車が時々通るが、その際には沿道に警察官が隈無く配置され、信号機のタイミングを調整して、専用車が止まらないようにされている。さすが、である。
ちなみに、ここから六本木通りを北東に向かうと皇居である。六本木通りは皇室専用車が時々通るが、その際には沿道に警察官が隈無く配置され、信号機のタイミングを調整して、専用車が止まらないようにされている。さすが、である。
1858年の溜池交差点付近

近隣の情報
- 溜池交差点は外堀兼用の上水源だった:ぱふぅ家のホームページ
- 日枝神社には狛犬でなく神猿がいる:ぱふぅ家のホームページ
- 国会議事堂と首相官邸:ぱふぅ家のホームページ
- みなと科学館は塾/仕事帰りに気軽に立ち寄れる:ぱふぅ家のホームページ
- 愛宕神社の出世の階段:ぱふぅ家のホームページ
- NHK放送博物館はラジオ放送誕生の地に:ぱふぅ家のホームページ
(この項おわり)
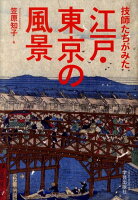



溜池山王駅(東京都千代田区永田町2-11-1)には東京メトロ銀座線と南北線が入っている。開業は1997年(平成9年)9月30日。
銀座線の上を走る外堀通りは、名前の通り、かつては外堀兼用の上水源だった。