目次
- 自殺防止42団体が全国ネット設立
- 健診とは別にストレス検査、企業に義務付け
- 自殺とうつの損失2.7兆円
- 自殺・うつ病対策の5本柱まとまる
- うつ病チェック、企業健診で義務化へ
- うつ病患者が急増
- 参考書籍
- 参考サイト
自殺防止42団体が全国ネット設立

自殺対策に取り組む全国42の民間団体は、世界自殺予防デーとなる9月10日、情報共有や各自治体の取り組みの底上げなどを目指して「自殺対策全国民間ネットワーク」を設立した。

自殺者は1998年(平成10年)以降、12年連続で3万人を超えている。自殺対策基本法が施行されて、まもなく4年。国による100億円の基金が設けられるなど自殺対策は進みつつある。しかし、各地域に根ざして活動している民間団体には、国の基金の活用方法などの情報が十分に行き届いていないケースもある。こうした情報格差をなくすのがネットワーク設立の狙いだ。
自殺者は1998年(平成10年)以降、12年連続で3万人を超えている。自殺対策基本法が施行されて、まもなく4年。国による100億円の基金が設けられるなど自殺対策は進みつつある。しかし、各地域に根ざして活動している民間団体には、国の基金の活用方法などの情報が十分に行き届いていないケースもある。こうした情報格差をなくすのがネットワーク設立の狙いだ。
朝日新聞,2010年9月10日より
健診とは別にストレス検査、企業に義務付け
職場での精神疾患を把握する方法について検討していた厚生労働省の「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」は9月7日、健康診断とは別に、うつなどの兆候がないかなどをチェックするストレス検査の義務付けを提言する報告書を公表した。→「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ

報告書は以下の4つのポイントからなる。
報告書は以下の4つのポイントからなる。
- 一般定期健康診断に併せ、ストレスに関連する労働者の症状・不調を医師が確認する。
- 面接が必要とされた労働者は産業医等と面接を行う。その際は、上記ストレスに関連する症状や不調の状況、面接が必要かについて事業者に知らせない。
- 産業医等は労働者との面接の結果、必要と判断した場合は労働者の同意を得て、事業者に時間外労働の制限や作業の転換などについて意見を述べる。
- 事業者は、労働時間の短縮等を行う場合には、産業医等の意見を労働者に明示し、了解を得るための話合いを行う。
朝日新聞,2010年9月7日より
自殺とうつの損失2.7兆円
長妻昭厚生労働大臣は、2009年(平成21年)の1年間に自殺者が出たことで失われた所得や、うつ病をきっかけとした休業や失業で労災補償や生活保護の給付の必要が生じたことによる国の負担増を合わせた経済的損失が計約2.7兆円に上るとする推計を発表した。→自殺・うつ対策の経済的便益(自殺やうつによる社会的損失)
共同通信,2010年9月7日より
自殺・うつ病対策の5本柱まとまる
厚生労働省に設けられた「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」が5月28日、これまでの4回にわたる会合で検討してきた内容をまとめた(自殺・うつ病等対策プロジェクトチームとりまとめについて)。今後の厚生労働省の対策として以下の5本柱を掲げており、同省では職場のメンタルヘルスや地域の精神保健医療の整備などに注力していく方針だ。
- 普及啓発の重点的実施
- ゲートキーパー機能の充実と地域連携体制の構築
- 職場におけるメンタルヘルス対策・職場復帰支援の充実
- アウトリーチ(訪問支援)の充実
- 精神保健医療改革の推進
キャリアブレイン,2010年5月28日より
うつ病チェック、企業健診で義務化へ

長妻昭厚生労働相は4月19日、企業が行う健康診断で、精神疾患に関する検査を義務づける方針を示した。労働安全衛生法の改正も検討する。増え続けるうつ病や自殺を防ぐ狙いだ。
労働安全衛生法は、原則として1年に最低1回、従業員の定期健康診断を行うことを事業主に義務づけている。違反すれば50万円以下の罰金となる。労働者にも受診義務があるが、罰則はない。

厚労省によると、2008年度のうつ病を含む精神障害などの労災請求件数は927件で、認定件数は269件。2000年(平成12年)と比べると、請求件数は4倍以上、認定件数は7倍以上に増えている。
厚労省によると、2008年度のうつ病を含む精神障害などの労災請求件数は927件で、認定件数は269件。2000年(平成12年)と比べると、請求件数は4倍以上、認定件数は7倍以上に増えている。
朝日新聞,2010年4月20日より
うつ病患者が急増
うつ病患者は最近10年間で2.4倍に急増し、100万人を超えた。不況などの影響はもちろんだが、新規抗うつ薬の登場との関係を指摘する声も強いという。
読売新聞,2010年1月6日より
参考書籍

|
雅子さまと「新型うつ」 | ||
| 著者 | 香山リカ | ||
| 出版社 | 朝日新聞出版 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2009年03月 | ||
| 価格 | 770円(税込) | ||
| ISBN | 9784022732668 | ||
| 仕事中はうつ、私生活では活動的ー。働き盛りの男女に増えている「新型うつ」。従来型うつの常識が通用しない新たな国民病に、医師も患者も周囲もとまどっている。「皇室」という日本社会の映し鏡を通して、気鋭の精神科医が現代人の「心」の病の深層に迫る。 | |||

|
なぜうつ病の人が増えたのか | ||
| 著者 | 冨高辰一郎 | ||
| 出版社 | 幻冬舎ルネッサンス | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2009年07月 | ||
| 価格 | 1,650円(税込) | ||
| ISBN | 9784779004537 | ||
| うつ病になるのはあなたのせいではない。これはつくられた「病い」だったー。薬と休養を勧めるだけのうつ病対策では不十分。現役精神科医が、うつ病診療の問題点と解決策を書き尽くす。 | |||

|
誇大自己症候群 | ||
| 著者 | 岡田尊司 | ||
| 出版社 | 筑摩書房 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2005年09月 | ||
| 価格 | 814円(税込) | ||
| ISBN | 9784480062635 | ||
| 「普通の子」が、些細なことから突発的に凶悪な事件を起こす。彼らはなぜ、世間を震撼させる犯罪者になったのか?従来の精神医学ではとらえきれない病理を、「誇大自己症候群」という切り口から探る。そこに共通するのは、幼児的な万能感やヒーロー願望、現実感に乏しいファンタジー傾向、他者への共感性の欠如や自己正当化などである。そしてそれらは、とりもなおさず、現代の大人たち、ひいては社会全体に見られる心的傾向なのだ。本書では、この病理を徹底分析、自己の呪縛が肥大化した現代を検証しつつ、その超克を見据えた画期的論考。 | |||

|
セロトニン欠乏脳 | ||
| 著者 | 有田秀穂 | ||
| 出版社 | 日本放送出版協会 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2003年12月 | ||
| 価格 | 748円(税込) | ||
| ISBN | 9784140880937 | ||
| キレる子どもや鬱の大人の脳では、セロトニン神経が衰弱し、脳内物質が欠乏している。不安や恐怖、興奮を適度に抑え、覚醒時のクールな意識(とらわれない心)を演出するセロトニン神経の不思議な働きを明らかにする。リズム運動できたえ、昼夜逆転した生活習慣を見直すことなどで、弱った脳と心に静かなパワーをとり戻す方法を、脳科学研究の最前線から提案する。 | |||

|
病み情報社会 | ||
| 著者 | 金子義保 | ||
| 出版社 | 新書館 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2007年12月 | ||
| 価格 | 4,180円(税込) | ||
| ISBN | 9784403120206 | ||
| 厚生労働省、製薬会社、大学医学部、病院、マスコミのネットワークが病気を蔓延させている-だけではない、現代社会の仕組みそのものが病気をつくっているのだ。淡々と並べられてゆく事実が浮き彫りにする現代医療の恐るべき実態。 | |||
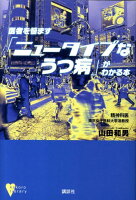
|
医者を悩ます「ニュータイプなうつ病」がわかる本 | ||
| 著者 | 山田和男 | ||
| 出版社 | 講談社 | ||
| サイズ | 全集・双書 | ||
| 発売日 | 2009年09月 | ||
| 価格 | 1,430円(税込) | ||
| ISBN | 9784062594981 | ||
| 「ニュータイプなうつ病」は誰でもなるかもしれない“ココロの花粉症”。原因、症状から治療法まで、近年急増しているうつ病の新分野を気鋭の精神科医が徹底解析。 | |||
参考サイト
- みんなのメンタルヘルス総合サイト:厚生労働省
- 自殺対策:厚生労働省
- 自殺対策支援センター ライフリンク
- 自殺・うつ対策の経済的便益(自殺やうつによる社会的損失):厚生労働省,2010年9月7日
- 「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ:厚生労働省,2010年9月7日
- 自殺・うつ病等対策プロジェクトチームとりまとめについて:厚生労働省,2010年5月28日
- 第6回 自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム 資料:厚生労働省,2010年7月27日
- 第7回 自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム 資料:厚生労働省,2010年9月9日
- メンタルヘルス・自殺対策:ぱふぅ家のホームページ
- メンタルヘルス 2010年版:ぱふぅ家のホームページ
- メンタルヘルス 2012年版:ぱふぅ家のホームページ
(この項おわり)



