エイリアン展

日本科学未来館(東京都江東区青海2-3-6)で開催している「エイリアン展」(2008年3月20日~6月16日)を見に行った。(展示物は撮影禁止)
 大きな写真
大きな写真
 大きな写真
大きな写真
(1920×1418 ピクセル, 920 Kbyte)


エスカレーターは7階まで吹き抜けになっており、葉っぱのようなオブジェ(?)が天井からぶら下がっている。
途中に喫茶コーナーがあり、そこで昼食を食べた。
途中に喫茶コーナーがあり、そこで昼食を食べた。


こちらは、数学者、秋山仁先生のサイン――哲学的な言葉である。
プラネタリウム「メガスター」


外から見ると、ドームシアターガイアは外に出っ張っている。

開発の経緯は「プラネタリウムを作りました。」(大平貴之/エクスナレッジ/2003年6月)に詳しいが、ともかく、一人ですべて作ってしまうということに驚かされる。化学薬品の扱いから、光学系、電装系、制御系、コンピュータ系、そして英語のスピーチまで、いろいろな専門家に教わった技術、ノウハウをすべて自分のモノにしていく過程が本書から読み取れる。それも「趣味」としてやっているのだから、恐れ入る。
開発の経緯は「プラネタリウムを作りました。」(大平貴之/エクスナレッジ/2003年6月)に詳しいが、ともかく、一人ですべて作ってしまうということに驚かされる。化学薬品の扱いから、光学系、電装系、制御系、コンピュータ系、そして英語のスピーチまで、いろいろな専門家に教わった技術、ノウハウをすべて自分のモノにしていく過程が本書から読み取れる。それも「趣味」としてやっているのだから、恐れ入る。
ジオ・コスモス

名物「Geo-Cosmos」は、200万分の1スケール(直径6.5メートル)の“映像地球儀”だ。約90万個のLEDによって、地球の様子だけでなく、他の惑星の様子も映し出せるように進化していた。



みらいCANマグレブ


みらいCANマグレブのからくりは写真の通り。

軌道の中に線路があり、模型を移動させるための台車がこの線路に沿って走っているのである。
超伝導バルク体と永久磁石のマイスナー効果により、模型は浮上し、全長30mの軌道の上を安定して走行することができる。
超伝導バルク体と永久磁石のマイスナー効果により、模型は浮上し、全長30mの軌道の上を安定して走行することができる。

マイスナー効果とは何か――デモンストレーションで見ることができた。

液体窒素(−196 ℃)で超伝導体(黒い円盤)を冷やすと、何もしていないのに、その上で磁石(緑色)がクルクル回転する。これがマイスナー効果だ。
しばらくすると超伝導体の温度が上がり、磁石は着地してしまう。
液体窒素(−196 ℃)で超伝導体(黒い円盤)を冷やすと、何もしていないのに、その上で磁石(緑色)がクルクル回転する。これがマイスナー効果だ。
しばらくすると超伝導体の温度が上がり、磁石は着地してしまう。

今度は、磁石でできた軌道の上に、液体窒素で冷却された超伝導体(白色)が浮上している。
超伝導体内ではボース凝縮が起きており、ここへ入った光子はボーズ粒子を取り込んで質量を得てしまい、光速で進むことができなくなる。結果として、光子が媒介する電磁波の到達距離が極端に短くなり、超伝導体内部に磁場が届かなくなり、磁石の上に浮かぶことになる。
超伝導体内ではボース凝縮が起きており、ここへ入った光子はボーズ粒子を取り込んで質量を得てしまい、光速で進むことができなくなる。結果として、光子が媒介する電磁波の到達距離が極端に短くなり、超伝導体内部に磁場が届かなくなり、磁石の上に浮かぶことになる。

この超伝導体には適度な不純物が混ざっており、軌道を倒しても超伝導体は落下することがない。
これをピン止め効果と呼ぶ。超伝導の重要な性質のひとつだ。
これをピン止め効果と呼ぶ。超伝導の重要な性質のひとつだ。
ロボット


Halluc IIは、「ロボット技術によって、さまざまな状況に柔軟に適応し、環境と共存して自由自在にどこにでも行ける、人の役に立つ機械をつくりたい」という研究者の夢に基づくコンセプトモデルで、後方にある卵形のコックピットで遠隔操作する。
インターネットのしくみ


まず、メッセージ・テーブルを見ながら、手作業で白と黒のボールを並べていく。

相手先を指定し、ボールを発射する。

ボールの伝送速度より人の歩くスピードの方が速い。そこで、到着地に先回りしてみる。

パケットが到着すると、自動的にデコードされ、電光掲示板にメッセージが表示される。
パケットが到着すると、自動的にデコードされ、電光掲示板にメッセージが表示される。
リニューアル
開館以来初めてという常設展の大幅リニューアルを行い、2016年(平成28年)4月20日に公開した。
今回、展示コンセプトを見直し、情報展示や体験型が主流だったものを、経験・思考型の展示に切り替えたという。

館長を務める宇宙飛行士の毛利衛さんは、「新しくなった日本科学未来館が、科学技術外交の場・科学コミュニケーションの場になればいい」と語った。
今回、展示コンセプトを見直し、情報展示や体験型が主流だったものを、経験・思考型の展示に切り替えたという。
館長を務める宇宙飛行士の毛利衛さんは、「新しくなった日本科学未来館が、科学技術外交の場・科学コミュニケーションの場になればいい」と語った。
新館長
2021年(令和3年)4月1日、IBMのIBMフェロー、浅川智恵子さんが新しい館長に就任する。
参考書籍
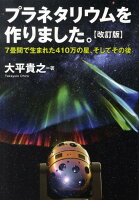
|
プラネタリウムを作りました。 | ||
| 著者 | 大平貴之 | ||
| 出版社 | エクスナレッジ | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2010年07月 | ||
| 価格 | 1,760円(税込) | ||
| ISBN | 9784767810157 | ||
| 世界一の個人開発プラネタリウム『メガスター』の原点とその後を語る改訂版。2003年以降、著者大平氏の7年にわたる活躍を追記。 | |||

|
真空のからくり | ||
| 著者 | 山田 克哉 | ||
| 出版社 | 講談社 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2013年10月18日頃 | ||
| 価格 | 1,210円(税込) | ||
| ISBN | 9784062578363 | ||
| ヒッグス粒子誕生の秘密が一から理解できる本。何もないはずの空間がざわめき、「無限のエネルギー」を生み出す──。光さえ存在しない真っ暗闇の「無の世界」で、無数の粒子たちが生成・消滅を繰り返していた! 「質量の起源」と「宇宙の進化」に不可欠な「真空のエネルギー」とは何か? ヒッグス粒子誕生の秘密からカシミール効果まで、謎に満ちた空間のふしぎを、わかりやすく解き明かす。 すべては真空から始まった! ピーター・ヒッグスと南部陽一郎が挑んだ「奇妙な空間」の正体とは? 何もないはずの空間がざわめき、「無限のエネルギー」を生み出すーー。 光さえ存在しない真っ暗闇の「無の世界」で、 無数の粒子たちが生成・消滅を繰り返していた! 「質量の起源」と「宇宙の進化」に不可欠な「真空のエネルギー」とは何か? ヒッグス粒子誕生の秘密からカシミール効果まで、 謎に満ちた空間のふしぎを、わかりやすく解き明かす。 【著者プロフィール】 山田克哉(やまだ・かつや) 一九四〇年生まれ。東京電機大学工学部電子工学科卒業。米国テネシー大学工学部原子力工学科大学院修士課程(原子炉理論)、同大学理学部物理学科大学院博士課程(理論物理学)修了。Ph.D.。セントラル・アーカンソー大学物理学科助教授、カリフォルニア州立大学ドミンゲツヒル校物理学科助教授を経て、ロサンゼルス・ピアース大学物理学科教授に就任。二〇一三年六月に退官。アメリカ物理学会会員。主な著書に『原子爆弾』『光と電気のからくり』『量子力学のからくり』(いずれもブルーバックス)などがある。一九九九年には、講談社科学出版賞を受賞した。 第1章 真空には「構造」がある 第2章 真空から粒子を叩き出せ 第3章 真空が生み出す奇妙な現象 第4章 「力が真空を伝わる」とはどういうことかーー仮想粒子の役割 第5章 「弱い力」と質量の起源をめぐる謎 第6章 真空はなぜ「ヒッグス粒子」を生み出したのか | |||
参考サイト
近隣の情報
- 日本科学未来館とエイリアン展:ぱふぅ家のホームページ
- 日本科学未来館でASIMOに会う:ぱふぅ家のホームページ
- 日本科学未来館:特別展「チ。 ―地球の運動について― 地球が動く」:ぱふぅ家のホームページ
- 日本科学未来館とサッカーをするAIBO:ぱふぅ家のホームページ
- 東京税関本関と東京港視察船「東京みなと丸」:ぱふぅ家のホームページ
- ユニコーンの日 in お台場:ぱふぅ家のホームページ
- お台場でバーベキュー:ぱふぅ家のホームページ
- ガンダム、お台場に立つ:ぱふぅ家のホームページ
- 東京ジョイポリスはセガのアミューズメント・パーク:ぱふぅ家のホームページ
- 帰ってきたゴーイングメリー号:ぱふぅ家のホームページ
- リスーピア RiSuPia は体感型ミュージアム:ぱふぅ家のホームページ
- レインボーブリッジは東京のシンボル:ぱふぅ家のホームページ
- 「中秋の名月」観覧車のゴンドラ照らして(2018年9月25日)
- CGアート、不思議な空間(2018年8月9日)
- サンタとトナカイ、お台場のビルで窓ふき(2017年12月24日)
- 日本科学未来館、科学捜査が体験できる企画展 「名探偵コナン」とコラボ(2017年12月10日)
- お台場がクリスマス仕様に衣替え(2017年11月14日)
- 「実物大ユニコーンガンダム」9月24日展示開始(2017年8月24日)
- ガンプラ公式店お台場に初出店 世界最大、国内1号(2017年8月23日)
- コンピューターゲームの魅力に迫る企画展(2015年9月17日)
- 22万個の光、お台場の夜を包む 13日から点灯(2014年11月12日)
- ひと足お先にお月見 「かぐや」の映像、大型球体に映す(2014年9月8日)
(この項おわり)



