
白河法皇
第72代・白河天皇は、1087年1月5日(応徳3年11月26日)、8歳の第二皇子・善仁親王に譲位し(第73代・堀河天皇)、自らは上皇となり院政をはじめる。以後、第74代・鳥羽天皇、第75代・崇徳天皇の時代まで43年にわたり「治天の君」として院政を行った。

後冷泉天皇~後白河天皇
当時の政治の要は天皇の人事にあった。つまり、次の天皇を誰にするかという問題である。藤原氏による摂関時代は、人事権は摂関家に握られていた
それが、宇多天皇から数えて170年ぶりに摂関家と繋がりのない第71代・後三条天皇が1068年(治暦4年)に即位すると、風向きが変わってきた。後三条天皇は皇子の白河天皇に譲位すると、その兄弟である実仁親王や輔仁親王へ皇位を譲るような人事を行った。
後三条上皇が崩御すると、白河天皇は兄弟ではなく皇子である堀河天皇へ位を譲ることを強行し、自らも上皇になる。

院の人事権掌握は、非公式におこなわれる。「佳人折紙」という非公式のメモを通じて、人事を動かすのである。
ここでは、人事権という「国家大事」を担うのはあくまでも天皇であり、その代行者の摂政なのであって、院はそれを裏から動かすというわけである。

白河上皇は仏教の熱心な信者で、1096年(嘉保2年)、出家し法皇となった。
それが、宇多天皇から数えて170年ぶりに摂関家と繋がりのない第71代・後三条天皇が1068年(治暦4年)に即位すると、風向きが変わってきた。後三条天皇は皇子の白河天皇に譲位すると、その兄弟である実仁親王や輔仁親王へ皇位を譲るような人事を行った。
後三条上皇が崩御すると、白河天皇は兄弟ではなく皇子である堀河天皇へ位を譲ることを強行し、自らも上皇になる。
院の人事権掌握は、非公式におこなわれる。「佳人折紙」という非公式のメモを通じて、人事を動かすのである。
ここでは、人事権という「国家大事」を担うのはあくまでも天皇であり、その代行者の摂政なのであって、院はそれを裏から動かすというわけである。
白河上皇は仏教の熱心な信者で、1096年(嘉保2年)、出家し法皇となった。
白河法皇は、賀茂川の水、双六の賽の目、山法師――この3つ以外、自らの意のままにならないものはないと豪語した。
この時代、賀茂川の氾濫が多く、双六が流行っていたことが分かっている。また、山法師というのは、力を付けてきた僧兵たちのことである。
この時代、賀茂川の氾濫が多く、双六が流行っていたことが分かっている。また、山法師というのは、力を付けてきた僧兵たちのことである。
この時代の世界
参考書籍
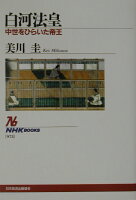
|
白河法皇 中世をひらいた帝王 | ||
| 著者 | 美川圭 | ||
| 出版社 | 日本放送出版協会 | ||
| サイズ | 全集・双書 | ||
| 発売日 | 2003年06月 | ||
| 価格 | 1,122円(税込) | ||
| ISBN | 9784140019733 | ||
| 賀茂川の水、双六の賽の目、山法師。この三つ以外、自らの意のままにならないものはないと豪語した、白河法皇。彼は、古代から中世へと転換を遂げようとする時代の流れに逆行した、恣意的な専制君主だったのか。さまざまな政治勢力が激しく競合する中世社会にあって、天皇の権威を守り、天皇制を持続させるため、白河は院政とよばれる新しい形態の政治システムを生み出した。希代の専制君主を生んだ時代の転換点を活写し、白河法皇の知られざる実像に迫る、初の本格的評伝。 | |||

|
院政 もうひとつの天皇制 | ||
| 著者 | 美川圭 | ||
| 出版社 | 中央公論新社 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2006年10月 | ||
| 価格 | 902円(税込) | ||
| ISBN | 9784121018670 | ||
| 院政とはすでに譲位した上皇(院)による執政をいう。平安後期には白河・鳥羽・後白河の三上皇が百年余りにわたって専権を振るい、鎌倉初期には後鳥羽上皇が幕府と対峙した。承久の乱の敗北後、朝廷の地位は低下したが、院政自体は、変質しながらも江戸末期まで存続する。退位した天皇が権力を握れたのはなぜか。その権力構造はどのようなものであったか。律令制成立期から南北朝期まで、壮大なスケールで日本政治史を活写する。 | |||
(この項おわり)


