

滑稽本は会話文を主体とした平易な文章で、単純な言葉の引っかけや常識から逸脱した言動、下ネタなどで大衆的な読者の笑いを誘う。当時の落語と影響を与え合っている。
廉価な作品が多く、人々の識字率が高まってきた文化・文政期において、数多く出版されるようになった。

「東海道中膝栗毛」は大ベストセラーとなり、続編の「続膝栗毛」が文化7年(1810年)から文政5年(1822年)にかけて刊行され、一九は原稿料だけで生計を支えたといわれている。
廉価な作品が多く、人々の識字率が高まってきた文化・文政期において、数多く出版されるようになった。
「東海道中膝栗毛」は大ベストセラーとなり、続編の「続膝栗毛」が文化7年(1810年)から文政5年(1822年)にかけて刊行され、一九は原稿料だけで生計を支えたといわれている。
十返舎一九は、かなり破天荒な性格であったらしい。
武士の子として駿府(現在の静岡市)に生まれ、江戸に出て武家奉公をした。19歳で大阪へ移るが、間もなく浪人の身となり、義太夫語りに頼って浄瑠璃作者となった。
その後独学で、黄表紙のほか、洒落本、人情本、読本、合巻、狂歌集など、さらには教科書的な文例集まで書いた。筆耕・版下書き・挿絵描きなど、自作以外の出版の手伝いもしており、版元にとっては便利な人物であった。
ただ、もらった原稿料ですぐ酒を買い、翌日には無一文になるという放蕩ぶりが災いして、私生活はけっして豊かではなかった。二度の離婚を経験している。
武士の子として駿府(現在の静岡市)に生まれ、江戸に出て武家奉公をした。19歳で大阪へ移るが、間もなく浪人の身となり、義太夫語りに頼って浄瑠璃作者となった。
その後独学で、黄表紙のほか、洒落本、人情本、読本、合巻、狂歌集など、さらには教科書的な文例集まで書いた。筆耕・版下書き・挿絵描きなど、自作以外の出版の手伝いもしており、版元にとっては便利な人物であった。
ただ、もらった原稿料ですぐ酒を買い、翌日には無一文になるという放蕩ぶりが災いして、私生活はけっして豊かではなかった。二度の離婚を経験している。
当時、江戸では町人を中心とした化政文化が花開いた。ちょうどその時に出版された「東海道中膝栗毛」は大ベストセラーとなった。

天保2年(1831年)8月7日、67歳で没した。
最期を看取った弟子には、着物を変えずに火葬にしてほしいと遺言した。そこで荼毘に付すと、一九があらかじめ体に仕込んでおいた花火に点火し、それが上がったという逸話が残っている。
辞世の句は
天保2年(1831年)8月7日、67歳で没した。
最期を看取った弟子には、着物を変えずに火葬にしてほしいと遺言した。そこで荼毘に付すと、一九があらかじめ体に仕込んでおいた花火に点火し、それが上がったという逸話が残っている。
辞世の句は
此世をば どりやおいとまに せん香と ともにつひには 灰左様なら最期まで人を楽しませることを忘れなかった人である。
この時代の世界
参考書籍
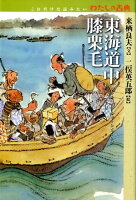
|
東海道中膝栗毛 | ||
| 著者 | 来栖良夫/二俣英五郎 | ||
| 出版社 | 童心社 | ||
| サイズ | 全集・双書 | ||
| 発売日 | 2009年02月 | ||
| 価格 | 2,200円(税込) | ||
| ISBN | 9784494019847 | ||

|
江戸っ子はなぜ宵越しの銭を持たないのか | ||
| 著者 | 田中優子 | ||
| 出版社 | 小学館 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2010年06月 | ||
| 価格 | 792円(税込) | ||
| ISBN | 9784098250844 | ||
| 金離れがよく、物事に執着しない「江戸っ子」の美学は、どのように育まれたのか?落語に息づく人々の暮らしをひもとけば、現代人が忘れてしまった、まっとうな「しあわせ」が見えてくる。江戸の社会・文化を渉猟し、現代への明敏な批判としてよみがえらせてきた気鋭の江戸学者が世に問う、初めての本格的「落語論」。 | |||
(この項おわり)



江戸神田八丁堀の住人、栃面屋弥次郎兵衛と、居候の喜多八が、東海道を江戸から伊勢神宮へお伊勢参りに出掛け、さらに京都、大坂へとめぐる物語。道中の2人は、狂歌・洒落・冗談をかわし合い、行く先々で騒ぎを起こすというストーリー。登場人物の弥次さん、喜多さんは、現代でも親しまれている。