
銅と亜鉛を用いたボルタ電池の仕組み

アレッサンドロ・ボルタ
ボルタは最も電気を発生する金属片の組み合わせと溶液を求めて実験を繰り返し、ついに1800年、銅と亜鉛の金属板を希硫酸につけるという「ボルタ電池」を発明する。
電圧の単位として使われている「ボルト」は彼の名にちなんで命名された。

ボルタの電池は放電が進むとプラス極の表面に水素ガスが発生し、1時間ほどで電気が流れなくなるという欠点があった。また、危険な硫酸を使っていることも問題であった。
電圧の単位として使われている「ボルト」は彼の名にちなんで命名された。
ボルタの電池は放電が進むとプラス極の表面に水素ガスが発生し、1時間ほどで電気が流れなくなるという欠点があった。また、危険な硫酸を使っていることも問題であった。
1868年、フランスの科学者ジョルジュ・ルクランシェは、プラス極に二酸化マンガンを加えることで水素ガスを吸着させ、発電量を一定にすることに成功した。これが今日でも使われている「マンガン乾電池」である。

一方、ボルタの電池を使って電気分解を行ったイギリスのデービー卿(ファラデーの師匠)は、1801年、その逆反応として燃料電池を実現できることを発見した。

1801年、パリに招かれたボルタは、第一統領となっていたナポレオン・ボナパルトの前で電池を用いた実験を行った。ナポレオンは、ボルタに勲章と伯爵の爵位を贈った。
1814年、イギリスの化学者ハンフリー・デービーは、助手のマイケル・ファラデーとともにボルタを訪れる。伯爵の礼装で迎えたボルタを、後に電磁誘導を発見する若きファラデーは、「年配ながらかくしゃくとしており、気さくに話をする人」と日記に記している。
一方、ボルタの電池を使って電気分解を行ったイギリスのデービー卿(ファラデーの師匠)は、1801年、その逆反応として燃料電池を実現できることを発見した。
1801年、パリに招かれたボルタは、第一統領となっていたナポレオン・ボナパルトの前で電池を用いた実験を行った。ナポレオンは、ボルタに勲章と伯爵の爵位を贈った。
1814年、イギリスの化学者ハンフリー・デービーは、助手のマイケル・ファラデーとともにボルタを訪れる。伯爵の礼装で迎えたボルタを、後に電磁誘導を発見する若きファラデーは、「年配ながらかくしゃくとしており、気さくに話をする人」と日記に記している。
バグダッドで、紀元前250年頃に製造されたとされる土器の壺が発見された。壺の中には銅製の筒と鉄の棒がはめ込まれていたことから、電池として使われていたのではないかと考えられている(バグダッド電池)。
この時代の世界
参考書籍
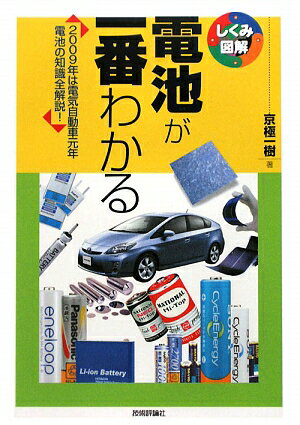
電池が一番わかる
(京極一樹/技術評論社/2010年1月)
電池の歴史から乾電池や充電池のしくみや特性の説明に加え、燃料電池、太陽電池などの開発状況を解説している。また、電気自動車のしくみも紹介している。
(この項おわり)


一方、フランスの科学者ボルタも同様の実験を行い、動物電気を否定。二種類の金属板の間に電気が発生することを突き止めた。