
田沼意次
足軽の息子として江戸で生まれた田沼意次は、第8代将軍・徳川吉宗の長男・徳川家重の小姓となり出世。第10代将軍・徳川家治の信任も厚く、1767年(明和4年)に側用人に抜擢される。これより、意次が失脚する1786年(天明6年)までを田沼時代と呼ぶ。
1745年(延享2年)、将軍徳川吉宗が引退し、享保の改革は頓挫した。第9代将軍となった徳川家重は、お気に入りの小姓だった田沼意次を側用人に取り立てる。
意次は、幕府の財政を改善するために重商主義政策をとった。株仲間の結成、銅座などの専売制の実施、鉱山の開発、蝦夷地の開発計画などである。また、平賀源内との親交を通じて蘭学を保護した。

意次は、武士は質素倹約を旨として米だけを収入源とする常識を打ち破った。商人の儲けが大きくなればなるほど、幕府に入る税金も大きくなるという仕組みになっていた。

1761年(宝暦11年)、家重が死去し、10代将軍の座についた息子の徳川家治も父の遺言に従って意次を重用した。
意次は、海産物を長崎に集め中国の商人に売るなどして、輸入中心だった消極的な貿易を輸出主導に切り換えた。
1772年(明和9年)意次は老中に任命された。足軽の身分出身が老中にまで上り詰めたのは、江戸幕府はじまって以来のことだった。

しかし、徳川家との繋がりで既得権益を守ってきた譜代や親藩は、商業中心の財政改革に不快感をあらわにした。なかでも急先鋒だったのが、徳川吉宗の孫で白河藩主の松平定信である。
意次は、幕府の財政を改善するために重商主義政策をとった。株仲間の結成、銅座などの専売制の実施、鉱山の開発、蝦夷地の開発計画などである。また、平賀源内との親交を通じて蘭学を保護した。
意次は、武士は質素倹約を旨として米だけを収入源とする常識を打ち破った。商人の儲けが大きくなればなるほど、幕府に入る税金も大きくなるという仕組みになっていた。
1761年(宝暦11年)、家重が死去し、10代将軍の座についた息子の徳川家治も父の遺言に従って意次を重用した。
意次は、海産物を長崎に集め中国の商人に売るなどして、輸入中心だった消極的な貿易を輸出主導に切り換えた。
1772年(明和9年)意次は老中に任命された。足軽の身分出身が老中にまで上り詰めたのは、江戸幕府はじまって以来のことだった。
しかし、徳川家との繋がりで既得権益を守ってきた譜代や親藩は、商業中心の財政改革に不快感をあらわにした。なかでも急先鋒だったのが、徳川吉宗の孫で白河藩主の松平定信である。
自然災害が続いたことも災いした。
1770年(明和7年)は干魃、1772年(明和9年)は江戸で明和の大火が起き、そして1773年(安永2年)には江戸だけで19万人が犠牲になった疫病が発生した。
さらに1783年(天明3年)4月、浅間山が突如大噴火を起こし、2万人以上の犠牲者が出る大惨事になった。噴煙が東日本一帯を覆い、農作物は壊滅的な打撃を受け、深刻な飢饉が広がった。天明の大飢饉である。
田沼意次は米の買い占めや売り惜しみを禁止する法令を出し、米の販売を自由化した。ところがこの政策が裏目に出て、無数の商人が米の売買に参入し、米不足が加速してしまった。
民衆は各地で一揆や打ち壊しを起こし、田沼意次を恨んだ。

一方、松平定信の白河藩では、他の地域から米を買い付け、藩内に供給した。飢饉に苦しむ東日本にあって、白河藩からは一人の餓死者も出さなかったという。

1786年(天明6年)、意次を重用していた将軍・徳川家治が病に倒れた。定信ら反対派は、意次が家治に見舞いに行くことを阻止した。
8月27日、ついに意次は老中を解任され、減封を受けて財産も没収されてしまった。その2年後、意次は失意のうちに70歳で死去する。

1787年(天明7年)、意次と入れ替わるように定信が老中に就任し、意次の改革を白紙に戻したうえで、重農主義の寛政の改革に着手する。
1770年(明和7年)は干魃、1772年(明和9年)は江戸で明和の大火が起き、そして1773年(安永2年)には江戸だけで19万人が犠牲になった疫病が発生した。
さらに1783年(天明3年)4月、浅間山が突如大噴火を起こし、2万人以上の犠牲者が出る大惨事になった。噴煙が東日本一帯を覆い、農作物は壊滅的な打撃を受け、深刻な飢饉が広がった。天明の大飢饉である。
田沼意次は米の買い占めや売り惜しみを禁止する法令を出し、米の販売を自由化した。ところがこの政策が裏目に出て、無数の商人が米の売買に参入し、米不足が加速してしまった。
民衆は各地で一揆や打ち壊しを起こし、田沼意次を恨んだ。
一方、松平定信の白河藩では、他の地域から米を買い付け、藩内に供給した。飢饉に苦しむ東日本にあって、白河藩からは一人の餓死者も出さなかったという。
1786年(天明6年)、意次を重用していた将軍・徳川家治が病に倒れた。定信ら反対派は、意次が家治に見舞いに行くことを阻止した。
8月27日、ついに意次は老中を解任され、減封を受けて財産も没収されてしまった。その2年後、意次は失意のうちに70歳で死去する。
1787年(天明7年)、意次と入れ替わるように定信が老中に就任し、意次の改革を白紙に戻したうえで、重農主義の寛政の改革に着手する。
蔦屋重三郎の足跡

蔦屋重三郎
NHK大河ドラマ第64作『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(2025年1月5日放映開始)は、江戸時代中期に版元として、日本のメディア産業を築いた蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯を描く。

新吉原 大門付近
蔦屋重三郎は、1750年(寛延3年)に吉原遊廓で産まれた。幼名を珂理という。7歳の時、両親が離婚し、吉原に置いてけぼりにされた珂理は、遊客を遊女屋へ案内する引手茶屋「蔦屋」を営んでいた喜多川家の養子となる。その後、蔦屋を継ぎ、蔦屋重三郎、蔦重と呼ばれるようになる。

明和の大火
1772年(明和9年)4月、目黒の大円寺から出火した炎は南西からの風にあおられ、麻布、京橋、日本橋を襲い、江戸城下の武家屋敷を焼き尽くし、神田、千住方面まで燃え広がった。吉原も巻き込まれた。江戸三大大火のひとつ、明和の大火である。

『吉原細見』
1773年(安永2年)、蔦重は、大門のある五十間道にあった義兄・蔦屋次郎兵衛が経営する茶屋の軒先を借り、耕書堂という書店兼貸本屋をオープンする。
当時、鱗形屋孫兵衛が経営する鶴鱗堂という版元が、『吉原細見』というガイドブックを年2回刊行していた。鱗形屋は1660年(万治3年)頃に大伝馬町に店を構えた老舗で、絵本や浄瑠璃本などを刊行していたが、享保の改革の煽りで大名や商人の勢いが落ち、吉原では、各地にできた岡場所(私娼街)に客を取られて潰れる見世(妓楼)が出ており、遊女の数も3分の2まで激減するという厳しい状況にあった。遊女の出入りも激しく、年2回の出版では情報が陳腐化しており、目当ての遊女を求めて初めて吉原を訪れても、すでに遊女はいなくなっているという有様だった。
当時、鱗形屋孫兵衛が経営する鶴鱗堂という版元が、『吉原細見』というガイドブックを年2回刊行していた。鱗形屋は1660年(万治3年)頃に大伝馬町に店を構えた老舗で、絵本や浄瑠璃本などを刊行していたが、享保の改革の煽りで大名や商人の勢いが落ち、吉原では、各地にできた岡場所(私娼街)に客を取られて潰れる見世(妓楼)が出ており、遊女の数も3分の2まで激減するという厳しい状況にあった。遊女の出入りも激しく、年2回の出版では情報が陳腐化しており、目当ての遊女を求めて初めて吉原を訪れても、すでに遊女はいなくなっているという有様だった。

『細見嗚呼御江戸』
鱗形屋は、情報を最新にするため、吉原の情報通として蔦重に白羽の矢が立った。編集長を任された蔦重は、1774年(安永3年)に『細見嗚呼御江戸』を刊行。遊女や見世の情報を最新のものにしたのはもちろんのこと、序文を福内鬼外(平賀源内のペンネーム)が書いたことで話題になった。

『雛形若菜の初模様』

『明月余情』
1777年(安永6年)、蔦屋重三郎は吉原の祭り俄の模様を伝える『明月余情』という3編の絵本を出した。久保田藩藩士で戯作者の朋誠堂喜三二が、洒落た語り口で「この盛大な行事が吉原の繁栄につながる」と序文を飾り、数々の挿絵が祭りの盛り上がりを伝えた。

『利得算法記』
蔦屋重三郎は、この頃から戯作本を、1780年(安永9年)からは、知的でナンセンスな笑いと現実世界を踏まえた青本の刊行をはじめた。時間がたつと表紙が黄色くなることから、黄表紙とも呼ばれる。さらに、拡大する寺子屋で使われる教科書としての往来本を手掛け、『吉原細見』とともに耕書堂の売上を支えた。1781年(安永10年)に女子用の『女今川艶紅梅』を、1788年(天明8年)には和算を学べる『利得算法記』を出版した。

『身貌大通神畧縁記』

富士山形に蔦の葉
吉原において版元としての地盤を確固たるものとした重三郎は、1783年(天明3年)に丸屋小兵衛の店を買い上げ、ついに日本橋通油町に進出するとともに、地本問屋の株を手に入れた。重三郎は、耕書堂が版元になった作品に「富士山形に蔦の葉」のマークを表示した。
この年、重三郎は大田南畝の知己を得て、蔦唐丸と号して狂歌師としての活動を開始し、吉原連に所属。著名な狂歌師たちとの繋がりを持つようになり、狂歌ブームが巻き起こる。
この年、重三郎は大田南畝の知己を得て、蔦唐丸と号して狂歌師としての活動を開始し、吉原連に所属。著名な狂歌師たちとの繋がりを持つようになり、狂歌ブームが巻き起こる。
参考書籍

|
田沼意次と松平定信 | ||
| 著者 | 童門冬二 | ||
| 出版社 | 時事通信社 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2000年06月 | ||
| 価格 | 1,760円(税込) | ||
| ISBN | 9784788700598 | ||
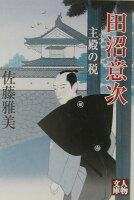
|
田沼意次 主殿の税 | ||
| 著者 | 佐藤雅美 | ||
| 出版社 | 学陽書房 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 2003年05月 | ||
| 価格 | 836円(税込) | ||
| ISBN | 9784313751651 | ||
| 「賄賂の卸問屋」か?「経済改革者」か?田沼意次は老中として財政再建に取り組むうちに、幕府の租税制度が持っている根本的矛盾に気がついた。しかし改革に乗り出した彼の前に守旧派の厚い壁が…。緻密な考証で悪徳政治家とされた田沼の実績を見直し、その波瀾の生涯を描き出す迫真の歴史経済小説。 | |||

|
学習まんが 世界の伝記NEXT 蔦屋重三郎 | ||
| 著者 | おおつき べるの/はの まきみ/日野原 健司 (太田記念美術館) | ||
| 出版社 | 集英社 | ||
| サイズ | 全集・双書 | ||
| 発売日 | 2024年11月26日頃 | ||
| 価格 | 1,210円(税込) | ||
| ISBN | 9784082400897 | ||
| 歌麿、写楽、北斎を仕掛けた江戸のカリスマ出版人ーー 2025年大河ドラマの主人公・蔦屋重三郎の生涯を 美しい絵、引きこまれるストーリーで、分かりやすくえがいた学習まんが! 260年間も平和な治世が続いた江戸時代。 それは庶民の文化が花開いた時代でもありました。 そんな江戸時代の中ごろに生まれた蔦重こと蔦屋重三郎は、 時代を読む確かな目と 熱意と誠実さとでつちかった人脈をいかし、 軒先を間借りして始めた貸本屋をたった10年で江戸を代表する本屋、版元に成長させます。 その後も幕府の出版統制にあらがいながら、 江戸っ子たちが楽しめる本や浮世絵を世に送り出しつづけました。 江戸の町民文化の最先端を走りつづけた本屋、蔦重が見いだした作家たちの作品は、時代や国をこえ、 多くの人びとを楽しませることになるのです。 【本書の特長】 ●まんがだから読みやすく、わかりやすい! ●すべてふりがな付きなので、小学校低学年から楽しく読める! ●Q&Aや年表など、よりくわしく知ることができる記事ページも充実! 【もくじより】 みんなをよろこばせたい! ひとりで本はつくれない まじめなる口上 だれも見たことがない絵 もっとみんなに「楽しい!」を 9つの質問でわかる! 蔦重が江戸のカリスマ出版人になったわけ 年表 | |||

|
蔦屋重三郎 | ||
| 著者 | 鈴木 俊幸 | ||
| 出版社 | 平凡社 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2024年10月21日頃 | ||
| 価格 | 1,100円(税込) | ||
| ISBN | 9784582860672 | ||
| 18世紀後半の江戸には、喜多川歌麿、東洲斎写楽、山東京伝。大田南畝といった江戸文化を彩る花形スターが登場し、一大旋風を巻き起こした。これらのスターたちの作品を巧みに売り出し、江戸文化の最先端を演出・創造したのが、版元の「蔦重」こと蔦屋重三郎(1750?1797)だ。 蔦屋重三郎は、その類まれなる嗅覚とセンスを忌憚なく発揮し、江戸吉原の人気ガイドブック『吉原細見』の独占出版から狂歌と浮世絵を合体させた豪華な狂歌絵本の刊行、当時の情勢を風刺した山東京伝らによる戯作を出版し、時の人となる。重三郎の凄みはそれだけではない。才能を秘めた人を見出し、世に送り出すという現代でいえば、“名プロデューサー”的な役割も果たし、歌麿や写楽などを見出した。 本書は江戸時代を代表する稀代の名プロデューサー(仕掛け人)、蔦屋重三郎という人物にフォーカスするとともに、吉原の町の本屋だった彼がなぜ大成功をおさめたのか、そして蔦重がもたらした文化的な影響を軸として「蔦重」をわかりやすく解説する1冊。 【目次】 第一章 吉原と蔦重 吉原の本屋重三郎/鱗形屋版吉原細見に蔦重の名/『一目千本』と『急戯花の名寄』 吉原細見『籬乃花』を出版/生い立ち/『青楼美人合姿鏡』と「雛形若菜初模様」/江戸時代中期の江戸/通という美意識と吉原/吉原発の当世本/戯作と通/朋誠堂喜三二/富本浄瑠璃/『碁太平記白石噺』/黄表紙の出版/広告の発想/足場固め 第二章 天明狂歌・戯作と蔦重 安永から天明へ/大田南畝との出会い/江戸狂歌の流行/狂歌師蔦唐丸誕生/地本問屋蔦屋重三郎/日本橋通油町/北尾政演と喜多川歌麿/戯作・狂歌の勢い/季節の終わり/狂歌絵本/田沼意次の失脚と松平定信の登場/武家社会の空気/南畝の退陣と狂歌熱のゆくえ/喜三二と春町の黄表紙 第三章 新たな時代の到来 寛政という時代/倹約・不景気/山東京伝人気/地本問屋仲間と板木屋仲間/京伝作洒落本一件/浮世絵の出版/書籍市場の変化/蔦重の書物問屋加入と京伝黄表紙/民間知の底上げ/平仮名の経書/全国展開/永楽屋東四郎/和学書/一九と馬琴/蔦重の死 第一章 吉原と蔦重 吉原の本屋重三郎/鱗形屋版吉原細見に蔦重の名/『一目千本』と『急戯花の名寄』 吉原細見『籬乃花』を出版/生い立ち/『青楼美人合姿鏡』と「雛形若菜初模様」/江戸時代中期の江戸/通という美意識と吉原/吉原発の当世本/戯作と通/朋誠堂喜三二/富本浄瑠璃/『碁太平記白石噺』/黄表紙の出版/広告の発想/足場固め 第二章 天明狂歌・戯作と蔦重 安永から天明へ/大田南畝との出会い/江戸狂歌の流行/狂歌師蔦唐丸誕生/地本問屋蔦屋重三郎/日本橋通油町/北尾政演と喜多川歌麿/戯作・狂歌の勢い/季節の終わり/狂歌絵本/田沼意次の失脚と松平定信の登場/武家社会の空気/南畝の退陣と狂歌熱のゆくえ/喜三二と春町の黄表紙 第三章 新たな時代の到来 寛政という時代/倹約・不景気/山東京伝人気/地本問屋仲間と板木屋仲間/京伝作洒落本一件/浮世絵の出版/書籍市場の変化/蔦重の書物問屋加入と京伝黄表紙/民間知の底上げ/平仮名の経書/全国展開/永楽屋東四郎/和学書/一九と馬琴/蔦重の死 | |||
この時代の世界
(この項おわり)


