
藤原道長

朱雀天皇~後朱雀天皇 系図
旧暦16日は十六夜だ。天文学的に見たら月はわずかに欠けていたはずなのだが、それにかけた歌なのであろう。

道長は御堂関白と呼ばれることもあるが、自らは関白の地位に就いたことがない。これは、自身の孫が天皇に即位して外祖父となるまでは摂政・関白には就かず、太政官の事実上の首席である左大臣として公事の執行にあたると同時に、関白に近い権限を持つ内覧を兼任することによって最高権力を行使しようとしていたと考えられている。

外孫である後一条天皇に娘・威子を嫁がせて間もなく、1019年(寛仁3年)、道長の長男・藤原頼通が関白に就任する。これにより、道長は実質的に天皇や公家より上の立場に君臨することになる。
道長は御堂関白と呼ばれることもあるが、自らは関白の地位に就いたことがない。これは、自身の孫が天皇に即位して外祖父となるまでは摂政・関白には就かず、太政官の事実上の首席である左大臣として公事の執行にあたると同時に、関白に近い権限を持つ内覧を兼任することによって最高権力を行使しようとしていたと考えられている。
外孫である後一条天皇に娘・威子を嫁がせて間もなく、1019年(寛仁3年)、道長の長男・藤原頼通が関白に就任する。これにより、道長は実質的に天皇や公家より上の立場に君臨することになる。
その後、道長は法成寺の建立に精力を傾けた。地方の受領は、天皇家の仕事よりも優先して法成寺建立に奉仕したという。「栄花物語」が、その壮麗さを伝えている。

道長は多くの子どもたちに先立たれており、心安らかな晩年ではなかっただろう。1027年(万寿4年)に病没。享年62。

道長は藤原北家の全盛期を築き、摂関政治の崩壊後も彼の子孫のみが摂関職を代々世襲し、本流から五摂家と九清華のうち三家(花山院・大炊御門・醍醐)を輩出した。

ちなみに、669年10月16日(旧暦)には、藤原氏の始祖・藤原鎌足(中臣鎌足)が死没している。
道長は多くの子どもたちに先立たれており、心安らかな晩年ではなかっただろう。1027年(万寿4年)に病没。享年62。
道長は藤原北家の全盛期を築き、摂関政治の崩壊後も彼の子孫のみが摂関職を代々世襲し、本流から五摂家と九清華のうち三家(花山院・大炊御門・醍醐)を輩出した。
ちなみに、669年10月16日(旧暦)には、藤原氏の始祖・藤原鎌足(中臣鎌足)が死没している。
参考書籍
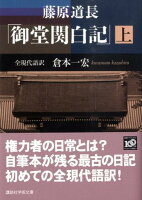
|
藤原道長「御堂関白記」 上 全現代語訳 | ||
| 著者 | 倉本 一宏 | ||
| 出版社 | 講談社 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 2009年05月11日頃 | ||
| 価格 | 1,584円(税込) | ||
| ISBN | 9784062919470 | ||
| 平安時代最大の権力者・藤原道長が、絶頂期に記した日記を読む! 『御堂関白記』は、平安時代中期いわゆる摂関政治の最盛期を築いた藤原道長の日記である。 長徳元(995)年、30歳で関白に准じる職・内覧に任じられたときから始まり、豪放磊落な筆致と独自の文体で描かれる宮廷政治と日常生活の様子が記されている。 平安貴族が活動した世界とはどのようなものだったのか。 自筆本・古写本・新写本などからの初めての現代語訳。 | |||
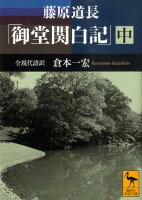
|
藤原道長「御堂関白記」 中 全現代語訳 | ||
| 著者 | 倉本 一宏 | ||
| 出版社 | 講談社 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 2009年06月10日頃 | ||
| 価格 | 1,694円(税込) | ||
| ISBN | 9784062919487 | ||
| 平安時代最大の権力者・藤原道長が、絶頂期に記した日記を読む! 『御堂関白記』は、平安時代中期いわゆる摂関政治の最盛期を築いた藤原道長の日記である。 一条朝から三条朝へと移る中、娘彰子に続いて妍子も中宮となり、道長の宮廷での権勢はさらに増大する。 本巻では、寛弘6(1009)年以降、彰子の親王出産、天皇崩御などの出来事から、 長和2(1013)年までのさまざまな朝議・公事、神事・仏事や饗宴の様子が詳細に綴られる。 宮廷政治の世界を、平易な現代語訳で読む! 寛弘6年(1009) 寛弘7年(1010) 寛弘8年(1011) 長和元年(1012) 長和2年(1013) | |||

|
藤原道長「御堂関白記」 下 全現代語訳 | ||
| 著者 | 倉本 一宏 | ||
| 出版社 | 講談社 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 2009年07月13日頃 | ||
| 価格 | 1,980円(税込) | ||
| ISBN | 9784062919494 | ||
| この世をばわが世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えばー 三女威子を後一条天皇の中宮に立て、ついに「一家三后」を実現した道長。 宮廷での栄華が極まる一方で、その明るさに胸病、眼病が暗い影を落としはじめる。 政治から身を引き、極楽往生を願う晩年の日々。 いまに残る日記の最終条は念仏「十七万遍」であった。 平安時代最強の政治権力者の日記、ここに完結! 長和4年(1015) 長和5年(1016) 寛仁元年(1017) 寛仁2年(1018) 寛仁3年(1019) 寛仁4年(1020) 治安元年(1021) | |||
この時代の世界
(この項おわり)



威子の立后の日(旧暦10月16日)、道長は即興の歌「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」を詠んだ。この世は自分のためにあるものだから満月が欠けることもない、と解釈されている。まさに道長の絶頂期である。