
マキャベリ家は、フィレンツェ共和国の要職を何人か輩出している名家である。
マキャベリ自身も、1498年、ピエロ・ソデリーニ政権下の第2書記局長に選出される。内政・軍政を所管している部署であったことから、ピサ領有の重要性を説き、1500年にはフィレンツェ軍顧問の副官としてピサ攻略に赴いた。しかし、フランス王が協約を違え、ピサ領有に失敗する。
この苦い経験から、マキャベリは、国の根源は傭兵に拠らない軍事力にあると確信し、国民軍の創設を計画した。そして、権謀術数に長けた教皇軍総司令官チェーザレ・ボルジアに理想の君主像を見出すようになった。

だが、メディチ家のフィレンツェ復権を後押しするハプスブルク家スペインの前に、1512年、マキャヴェッリは失脚し、隠遁生活に入る。
『君主論』が1513年から1514年にかけて執筆されたと考えられており、マキャベリは1516年にフィレンツェ僭主となったロレンツォ・ディ・ピエロ・デ・メディチ(ロレンツォ2世)に献上した。

その後、メディチ家政権下で顧問的に用いられるようになったマキャヴェッリであるが、1527年に発生したローマ略奪でメディチ家がフィレンツェから追放されると、失意のうちに病死する。
『君主論』は写本として読まれてきたが、出版されたのは、マキャベリの死後となる1532年のことである。
マキャベリ自身も、1498年、ピエロ・ソデリーニ政権下の第2書記局長に選出される。内政・軍政を所管している部署であったことから、ピサ領有の重要性を説き、1500年にはフィレンツェ軍顧問の副官としてピサ攻略に赴いた。しかし、フランス王が協約を違え、ピサ領有に失敗する。
この苦い経験から、マキャベリは、国の根源は傭兵に拠らない軍事力にあると確信し、国民軍の創設を計画した。そして、権謀術数に長けた教皇軍総司令官チェーザレ・ボルジアに理想の君主像を見出すようになった。
だが、メディチ家のフィレンツェ復権を後押しするハプスブルク家スペインの前に、1512年、マキャヴェッリは失脚し、隠遁生活に入る。
『君主論』が1513年から1514年にかけて執筆されたと考えられており、マキャベリは1516年にフィレンツェ僭主となったロレンツォ・ディ・ピエロ・デ・メディチ(ロレンツォ2世)に献上した。
その後、メディチ家政権下で顧問的に用いられるようになったマキャヴェッリであるが、1527年に発生したローマ略奪でメディチ家がフィレンツェから追放されると、失意のうちに病死する。
『君主論』は写本として読まれてきたが、出版されたのは、マキャベリの死後となる1532年のことである。
参考書籍
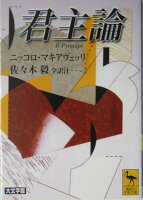
|
君主論 | ||
| 著者 | ニッコロ・マキアヴェッリ/佐々木 毅 | ||
| 出版社 | 講談社 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 2004年12月 | ||
| 価格 | 880円(税込) | ||
| ISBN | 9784061596894 | ||
| 近代政治学の古典として名高い『君主論』。その著者マキアヴェッリは、都市国家が並び立つルネサンスのイタリアにあって、共和政のフィレンツェ市書記官として活躍。国際政治の荒波のなか、軍事、外交にわたり東奔西走の日々を送った。その豊かな体験を生かして権力の生態を踏まえた統治術として執筆した名著を、政治学の第一人者が全訳し解説する。 | |||

|
NHK「100分de名著」ブックス マキャベリ 君主論 | ||
| 著者 | 武田好 | ||
| 出版社 | NHK出版 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2012年08月 | ||
| 価格 | 1,100円(税込) | ||
| ISBN | 9784140815274 | ||
| 政治的リアリティでもって、キリスト教的倫理観を排し、「権謀術数の書」として物議を醸した『君主論』。現代では帝王学のマニュアルとして切り貼りされがちだ。しかし、それが政庁への再雇用を求めたマキャベリが自分のために、自分の経験をもとに記した「政治実践の書」であったことはあまり知られていない。ルネサンス期のフィレンツェで辣腕をふるった書記官による、乱世を生き抜くための政治哲学を紹介する。東郷和彦氏との対談/読書案内/年譜を新たに収載。 | |||
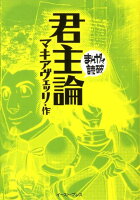
|
君主論 (まんがで読破) | ||
| 著者 | マキアヴェッリ | ||
| 出版社 | イースト・プレス | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 2008年09月30日頃 | ||
| 価格 | 607円(税込) | ||
| ISBN | 9784781600048 | ||
この時代の世界
(この項おわり)



歴史上の様々な君主および君主国を分析し、君主とはどうあるものか、君主として権力を獲得し、また保持し続けるにはどのような力量(徳、ヴィルトゥ)が必要かなどを論じている。
君主に権謀術数を教えた(マキャベリズム)とされることが多いが、現実主義の古典であり、後代のルソーなどから評価されている。