
明石市立天文科学館 2023年8月26日撮影
明石市立天文科学館(兵庫県明石市人丸町2-6)は、日本標準時子午線(東経135度)の真上に建つ天文科学館である。
 大きな写真
大きな写真
 大きな写真
大きな写真
(2560×1707 ピクセル, 1687 Kbyte)

明石市立天文科学館 2014年8月15日撮影
1960年(昭和35年)6月10日に開館し、現存する天文科学館の中では最も古い。塔時計の上部にある巨大な時計盤は、正確な日本標準時を刻んでいる。

明石市立天文科学館 2014年8月15日撮影

明石市立天文科学館 2014年8月15日撮影
4階の展示室「時のギャラリー」には、塔時計を制御している親時計がある。
親時計は、独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)のテレホンJJYから電話回線で時刻情報を受信し、自動的に補正している。精度は±1/100秒以下という。

塔時計と親時計はセイコーが寄贈したものだ。
親時計は、独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)のテレホンJJYから電話回線で時刻情報を受信し、自動的に補正している。精度は±1/100秒以下という。
塔時計と親時計はセイコーが寄贈したものだ。

宇宙メダカ 2014年8月15日撮影

天文ギャラリー 2014年8月15日撮影

天文ギャラリー 2014年8月15日撮影

赤道環型日時計 2014年8月15日撮影
4階はテラスになっていて、さまざまな形の日時計が設置されている。

写真は赤道環型日時計。目盛りが等間隔なので設計は易しいが、曲がった面を正しい形に仕上げるのは難しい。
写真は赤道環型日時計。目盛りが等間隔なので設計は易しいが、曲がった面を正しい形に仕上げるのは難しい。

多面体日時計 2014年8月15日撮影
こちらは多面体日時計。水平型、垂直型、赤道環型、極型、正午計が合わさった日時計である。
正午計の目盛りの形は、太陽高度の季節変化と均時差に対応してアナレンマという8の字形になっている。
正午計の目盛りの形は、太陽高度の季節変化と均時差に対応してアナレンマという8の字形になっている。

日時計広場 2014年8月15日撮影
こぱふぅも日時計になる!

漫画家の松本零士さんは、父親の仕事の都合で4歳から6歳まで明石公園の近くで暮らしており、天文科学館の北側にある高さ7メートルの子午線標識「トンボの標識」を見たことが、宇宙に関心を持つきっかけだったと語っている。代表作『銀河鉄道999』に描かれる星空は、明石にいた頃に見た星空をイメージしているという。(故松本零士さん、宇宙への興味は明石が「始発駅」,神戸新聞 2023年2月26日)
漫画家の松本零士さんは、父親の仕事の都合で4歳から6歳まで明石公園の近くで暮らしており、天文科学館の北側にある高さ7メートルの子午線標識「トンボの標識」を見たことが、宇宙に関心を持つきっかけだったと語っている。代表作『銀河鉄道999』に描かれる星空は、明石にいた頃に見た星空をイメージしているという。(故松本零士さん、宇宙への興味は明石が「始発駅」,神戸新聞 2023年2月26日)

惑星の大きさ比べ 2014年8月15日撮影
地球を直径65cm(2000万分の1)の球にした時の、太陽他惑星の大きさが比べられる模型がある。木星、土星、太陽は大きすぎるので、床に描かれている。

明石市立天文科学館 2014年8月15日撮影
塔時計の13階・14階は展望室になっており、エレベーターが1つと螺旋階段が2つある。螺旋階段の内部には全天星座が描かれている。

明石市立天文科学館 2014年8月15日撮影
展望室に床には東経135度の日本標準時子午線が引かれている。

明石海峡大橋 2014年8月15日撮影

明石海峡大橋 2014年8月15日撮影
こちらは、4階の日時計広場から見た明石海峡大橋。
手前に、JR山陽本線と山陽電鉄本線が走っている。
手前に、JR山陽本線と山陽電鉄本線が走っている。

明石海峡大橋 2023年8月26日撮影
日時計広場の左側に見えるドームはプラネタリウムである。

プラネタリウム 2023年8月26日撮影

プラネタリウム 2023年8月26日撮影
1960年(昭和35年)6月10日に稼動を開始した、現在国内最古のプロネタリウムである。ドームは直径20メートル、300席。
2017年(平成29年)に、コニカミノルタプラネタリウムのデジタル投影機「SUPER MEDIAGLOBE II」を導入し、映像表現を強化した。
2017年(平成29年)に、コニカミノルタプラネタリウムのデジタル投影機「SUPER MEDIAGLOBE II」を導入し、映像表現を強化した。
2024年(令和6年)2月には、アストロアーツ製のデジタルプラネタリウムソフトウェア「ステラドームプロ」が新たに導入され、カールツァイス・イエナ製プラネタリウムと組み合わせて、天体の動きや宇宙の広がりなどをより視覚的に学ぶことができるようになった。

漏刻 2014年8月15日撮影

日本標準時子午線 2014年8月15日撮影
漏刻から南へ日本標準時子午線が延びている。

ちなみに、日本標準時(JST)は、東京都小金井市にある情報通信機構(NICT)本部のセシウム原子時計18台と水素メーザー原子時計3台を使って決められている。時刻サーバへのアクセスは、1日約億回、アナログ電話回線でも1ヶ月に約14万回の利用がある。
2011年(平成23年)3月の東日本大震災の際、原発事故に伴う避難指示で、JSTは福島県にあるおおたかどや山標準電波送信所を停止せざるを得なかった。
ちなみに、日本標準時(JST)は、東京都小金井市にある情報通信機構(NICT)本部のセシウム原子時計18台と水素メーザー原子時計3台を使って決められている。時刻サーバへのアクセスは、1日約億回、アナログ電話回線でも1ヶ月に約14万回の利用がある。
2011年(平成23年)3月の東日本大震災の際、原発事故に伴う避難指示で、JSTは福島県にあるおおたかどや山標準電波送信所を停止せざるを得なかった。
電波時計は、この施設と、はがね山標準電波送信所(佐賀県)の2カ所が発信する電波を使って時刻を微修正するが、停止の影響で一部の電波時計が正確な時を刻めなくなり、利用者から500件以上の苦情があった。
こうした事態を防ぐため、標準時子午線(東経135度)から4キロ西にあるNICT未来ICT研究所に副局を設置することになり、2018年(平成30年)6月10日(時の記念日)に運用開始した。5台のセシウム原子時計と2台の水素メーザー原子時計で運用し、通常は現地と東京からの遠隔で監視し、大地震などで本部から送信できなくなった際は、7台の時計を駆使して標準時を作成、提供することになっているb。
こうした事態を防ぐため、標準時子午線(東経135度)から4キロ西にあるNICT未来ICT研究所に副局を設置することになり、2018年(平成30年)6月10日(時の記念日)に運用開始した。5台のセシウム原子時計と2台の水素メーザー原子時計で運用し、通常は現地と東京からの遠隔で監視し、大地震などで本部から送信できなくなった際は、7台の時計を駆使して標準時を作成、提供することになっているb。

トケイソウ 2014年8月15日撮影

毎年、3月1日と、10月12日の年2回、約1.4キロ西にある電波塔の奥に沈む夕日がパンダのように見える「夕焼けパンダ」が観測できる。長尾高明館長(60)が2013年(平成25年)10月、夕日を撮影中に偶然発見した。

人丸前駅 2014年8月15日撮影
ホームはひとつだけで、西寄りの部分を日本標準時子午線が貫いている。

人丸前駅 2014年8月15日撮影

人丸前駅 2014年8月15日撮影
山陽電気鉄道本線のすぐ北側にはJR山陽本線が走っている。
交通アクセス
【鉄道】

- 山陽電鉄「人丸前駅」から徒歩約3分
- JR明石駅から徒歩約15分
- 第二神明道路「大蔵谷I.C.」から南西へ約3Km

リツイート
ここに泊まったらぜひ目の前にある肉屋で飯を食べていただきたい、まじで美味しい https://t.co/iLEQt47G4W
— 古河彪 (@another_holy) 2018年7月5日
近隣の情報
- 明石市立天文科学館と人丸前駅は日本標準時子午線の上に建つ:ぱふぅ家のホームページ
- 明石焼を10個食べたらお腹いっぱい:ぱふぅ家のホームページ
- 明石海峡大橋は世界最長の吊橋:ぱふぅ家のホームページ
- 五色塚古墳は兵庫県内最大の前方後円墳:ぱふぅ家のホームページ
- 東垂水駅は兵庫県最南端の駅:ぱふぅ家のホームページ
- 須磨浦山上遊園は昭和レトロな公園:ぱふぅ家のホームページ
- ウェスティンホテル淡路は淡路夢舞台に建つ高級ホテル:ぱふぅ家のホームページ
- 北淡震災記念公園は野島断層を保存:ぱふぅ家のホームページ
- 世界平和大観音像は巨大廃墟:ぱふぅ家のホームページ
- 10万本の赤いサルビアと青い海が競演(2024年9月21日)
- 新生「神戸須磨シーワールド」…シャチが大ジャンプ、初回のショーには立ち見客も(2024年6月3日)
- 水族館で合格祈願、生き物たちが受験生応援(2023年2月25日)
- 夜の森歩き「鬼滅の刃」の世界へ、音や光で鬼との戦いを再現(2022年4月14日)
- 淡路島ソフトつくる牛型ロボ(2021年9月19日)
- 深まる赤い色、淡路島でサルビア見頃(2021年9月9日)
- 淡路島の新アトラクション「ドラゴンクエストアイランド」が4月29日にオープン(2021年4月6日)
- 大宇宙へ誘い100回目。明石・天文科学館の「こども教室」12日に節目(2020年12月5日)
- 色とりどりの「うそ」が招く幸運、木彫りのお守り人気(2020年11月30日)
- 淡路島に実物大ゴジラ:新アトラクション10日オープン(2020年10月12日)
- ドローンで見る日本の絶景、青々とした海にそびえたつ明石海峡大橋(2019年12月1日)
- 「ピングーと違うぞ」 AIペンギン…「学習」して返答(2019年5月28日)
- ペンギン足形集めて 3水族館でスタンプラリー(2019年5月5日)
- 須磨離宮公園の梅が咲き始め、家族連れら楽しむ(2019年2月8日)
- スプートニクに似た洗濯機 「昭和」のデザイン、挑戦的(2019年1月29日)
- 明石海峡大橋、開通から20年(2018年4月8日)
参考サイト
- 明石市立天文科学館
- 明石市立天文科学館@jstm135e:Twitter
- 人丸前駅:山陽電車
- NICTを「ニクト」って読んじゃダメなの? 直接聞いた 意外な事実判明:ITmedia NEWS,2023年09月05日
- 西暦1923年(大正12年) - ミュンヘン一揆/光学式プラネタリウムの発明:ぱふぅ家のホームページ
参考書籍
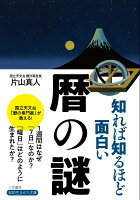
|
知れば知るほど面白い暦の謎 | ||
| 著者 | 片山 真人 | ||
| 出版社 | 三笠書房 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 2022年02月17日頃 | ||
| 価格 | 858円(税込) | ||
| ISBN | 9784837987635 | ||
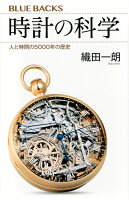
|
知時計の科学 人と時間の5000年の歴史 | ||
| 著者 | 織田 一朗 | ||
| 出版社 | 講談社 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2017年12月14日頃 | ||
| 価格 | 1,078円(税込) | ||
| ISBN | 9784065020418 | ||
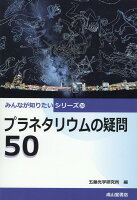
|
プラネタリウムの疑問50 | ||
| 著者 | 五藤光学研究所 | ||
| 出版社 | 成山堂書店 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2023年07月 | ||
| 価格 | 1,980円(税込) | ||
| ISBN | 9784425984312 | ||
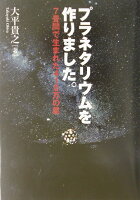
|
プラネタリウムを作りました。 | ||
| 著者 | 大平貴之 | ||
| 出版社 | エクスナレッジ | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2003年06月 | ||
| 価格 | 1,980円(税込) | ||
| ISBN | 9784767802510 | ||
(この項おわり)





