
源実朝

隠れ銀杏 - 鶴岡八幡宮
頼家が将軍職に就くのとほぼ同時期、13人の有力者による合議制がはじまる。
1199年(建久10年)、13人の一人、頼家の側近である梶原景時が失脚。さらに、1203年(建仁3年)、頼家に北条時政追討を進言した比企能員が滅ぼされる。
1199年(建久10年)、13人の一人、頼家の側近である梶原景時が失脚。さらに、1203年(建仁3年)、頼家に北条時政追討を進言した比企能員が滅ぼされる。
こうして北条時政は鎌倉武士の声に押される形で、1203年(建仁3年)9月、クーデターを指導。頼家は将軍職を剥奪され、伊豆に追放された。

頼家に代わって3代将軍の座についたのは、わずか12歳の弟の実朝だった。実朝を補佐する執権に時政が就任した。時政は伊豆に幽閉されていた頼家を暗殺し、実朝も亡き者にしようと機会を伺うようになった。
危機感を抱いた母の北条政子は、実朝を北条義時の館に匿った。武士たちは義時の館に集まり、観念した時政は伊豆へ流される。

身体が弱く武芸も得意ではなかった実朝は、京都の持つ高い文化の香りに惹かれ和歌を好んだ。実朝が詠んだ和歌は、藤原定家に認められ、後鳥羽上皇の前で披露された。
実朝は歌人としても知られるようになった。92首が勅撰和歌集に入集し、小倉百人一首にも選ばれている。家集として金槐和歌集がある。

実朝は、和歌を通じて知った朝廷政治を理想として実践しようとしていた。政治も合議制によって行い、武士たちの意見を積極的に取り入れようとした。一方で、朝廷との結びつきを深めるため、将軍領に対する納税にも積極的に応じた。
実朝は後鳥羽上皇との交流を深め、官位の昇進は早く、1218年(建保5年)12月、武士として初めて右大臣に任ぜられた。
しかし、せっかく朝廷から政権を奪い取った武士たちにしてみれば、こうした実朝のやり方に反感を抱くようになった。

1219年(建保6年)1月27日、右大臣就任を祝うため、実朝は鶴岡八幡宮を参拝した。その帰路、実朝は公暁に襲われ落命する。
この事件は、執権・北条義時が仕掛けたものだった。公暁はその場から逃げたものの、間もなく討ち取られる。実朝には子どもがいなかったため、源氏の将軍はここで絶えることになる。
義時は、4代将軍として、源氏より格上の皇子の下向を画策したが、これは失敗に終わり、代わりに摂関家九条家から九条頼経を迎え入れた。
頼家に代わって3代将軍の座についたのは、わずか12歳の弟の実朝だった。実朝を補佐する執権に時政が就任した。時政は伊豆に幽閉されていた頼家を暗殺し、実朝も亡き者にしようと機会を伺うようになった。
危機感を抱いた母の北条政子は、実朝を北条義時の館に匿った。武士たちは義時の館に集まり、観念した時政は伊豆へ流される。
身体が弱く武芸も得意ではなかった実朝は、京都の持つ高い文化の香りに惹かれ和歌を好んだ。実朝が詠んだ和歌は、藤原定家に認められ、後鳥羽上皇の前で披露された。
実朝は歌人としても知られるようになった。92首が勅撰和歌集に入集し、小倉百人一首にも選ばれている。家集として金槐和歌集がある。
実朝は、和歌を通じて知った朝廷政治を理想として実践しようとしていた。政治も合議制によって行い、武士たちの意見を積極的に取り入れようとした。一方で、朝廷との結びつきを深めるため、将軍領に対する納税にも積極的に応じた。
実朝は後鳥羽上皇との交流を深め、官位の昇進は早く、1218年(建保5年)12月、武士として初めて右大臣に任ぜられた。
しかし、せっかく朝廷から政権を奪い取った武士たちにしてみれば、こうした実朝のやり方に反感を抱くようになった。
1219年(建保6年)1月27日、右大臣就任を祝うため、実朝は鶴岡八幡宮を参拝した。その帰路、実朝は公暁に襲われ落命する。
この事件は、執権・北条義時が仕掛けたものだった。公暁はその場から逃げたものの、間もなく討ち取られる。実朝には子どもがいなかったため、源氏の将軍はここで絶えることになる。
義時は、4代将軍として、源氏より格上の皇子の下向を画策したが、これは失敗に終わり、代わりに摂関家九条家から九条頼経を迎え入れた。
北条義時の足跡

北条義時

源頼朝(足利直義とも)

北条時政

源義経
だが、大規模な戦闘が行なわれないまま追討軍は撤退する。『吾妻鏡』によると、追討軍は水鳥の羽音を源氏の大軍の来襲と誤認し、総崩れとなって壊走したという。

1180年(治承4年)11月、奥州から源義経が参戦し、源頼朝の軍勢が常陸佐竹氏が立てこもる金砂城を攻め落とす。1183年(寿永2年)、源頼朝は、源義広、足利忠綱らを破り、板東を平定する。
1183年(寿永2年)5月、源義仲(木曾義仲)は倶利伽羅峠の戦いで10万とも言われる平維盛率いる平氏の北陸追討軍を破り、7月、入京する。都の防衛を断念した平氏は安徳天皇を連れ、西国へ逃れる。
1180年(治承4年)11月、奥州から源義経が参戦し、源頼朝の軍勢が常陸佐竹氏が立てこもる金砂城を攻め落とす。1183年(寿永2年)、源頼朝は、源義広、足利忠綱らを破り、板東を平定する。
1183年(寿永2年)5月、源義仲(木曾義仲)は倶利伽羅峠の戦いで10万とも言われる平維盛率いる平氏の北陸追討軍を破り、7月、入京する。都の防衛を断念した平氏は安徳天皇を連れ、西国へ逃れる。

源義仲(木曾義仲)
頼朝の上洛を恐れる義仲は、後白河法皇を拘束して頼朝追討の宣旨を引き出す。頼朝は範頼・義経らを出陣させ、1184年(寿永3年)1月、宇治川の戦いで義仲を討つ。

源義経像(壇ノ浦)

中尊寺

毛越寺
9月3日、泰衡は郎従である河田次郎の裏切りにより討たれ、その首が頼朝へ届けられた。
奥州合戦には、関東のみならず全国各地の武士が動員された。また、捕虜となっていた武士も、この合戦に従って戦功を上げるという挽回の機会が与えられた。こうして武士たちと源頼朝の主従関係が強化された。
奥州合戦には、関東のみならず全国各地の武士が動員された。また、捕虜となっていた武士も、この合戦に従って戦功を上げるという挽回の機会が与えられた。こうして武士たちと源頼朝の主従関係が強化された。

後白河法皇
1190年(建久元年)10月、源頼朝は鎌倉を発ち上洛する。11月から12月にかけ京都に滞在した頼朝は、後白河法皇と会合を重ね、武家政権の地位を固める。

後鳥羽天皇

土御門天皇
1198年(建久9年)正月、後鳥羽天皇は土御門天皇に譲位して上皇となり院政を開始する。12月、頼朝は相模川で催された橋供養からの帰路で体調を崩し、1199年(建久10年)1月13日に死去する。
源頼家が、わずか18歳であとを継ぐが、訴訟を直接聞くなど失策が続いたため、北条時政ら宿老13人の合議により頼家に取り次ぐ体制が固まる。
源頼家が、わずか18歳であとを継ぐが、訴訟を直接聞くなど失策が続いたため、北条時政ら宿老13人の合議により頼家に取り次ぐ体制が固まる。

源頼家
13人の構成‥‥北条時政、北条義時、比企能員、和田義盛、梶原景時、足立遠元、八田知家、三浦義澄、安達盛長、大江広元、中原親能、二階堂行政、三善康信
1199年(正治元年)11月、鎌倉幕府侍所所司として御家人たちの取り締まりにあたっていた梶原景時が、御家人66名による連判状によって幕府から追放され、一族の多くが滅ぼされた。こうして、はやくも13人の一角が失われることになる。
1199年(正治元年)11月、鎌倉幕府侍所所司として御家人たちの取り締まりにあたっていた梶原景時が、御家人66名による連判状によって幕府から追放され、一族の多くが滅ぼされた。こうして、はやくも13人の一角が失われることになる。

梶原景時
1203年(建仁3年)7月に頼家が病に伏すと、時政は頼家の乳母父で舅である比企能員を謀殺し、比企氏を滅ぼした。さらに、頼家の将軍位を廃して伊豆国修善寺へ追放し、頼家の弟で阿波局が乳母を務めた12歳の実朝を3代将軍に擁立する。そして、大江広元と並んで政所別当に就任して実権を握った。
1204年(建仁4年)に、北条本家の後継者・政範が急死すると、翌年、義時は時政と牧の方を伊豆国に追放し、政所別当の地位に就いた。
1204年(建仁4年)に、北条本家の後継者・政範が急死すると、翌年、義時は時政と牧の方を伊豆国に追放し、政所別当の地位に就いた。

和田義盛
義時は政子と実朝を立てながら、御家人の要望に耳を貸すなど柔軟な姿勢をとりつつも、敵対する有力御家人を抑圧し、次第に独裁制を固め、執権と呼ばれるようになる。1213年(建暦3年)2月に、義時は、侍所別当の地位にあった和田義盛を滅ぼし、侍所別当となり、幕府の要職を独占する。

冒頭で述べたとおり、1219年(建保6年)正月27日、鶴岡八幡宮で実朝が公暁によって暗殺され、源氏の正統が絶える。
冒頭で述べたとおり、1219年(建保6年)正月27日、鶴岡八幡宮で実朝が公暁によって暗殺され、源氏の正統が絶える。

藤原頼経

北条政子
この時代の世界
参考書籍

|
北条氏の時代 | ||
| 著者 | 本郷 和人 | ||
| 出版社 | 文藝春秋 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2021年11月18日頃 | ||
| 価格 | 990円(税込) | ||
| ISBN | 9784166613373 | ||
| 鎌倉幕府150年の歴史をつくった謎の一族、北条氏。 名もなき一介の一族はなぜ、日本の歴史を変えることができたのかーー。 北条氏の時代を象徴する「七人の得宗(当主)」を中心に読み解く。 第一章 北条時政 敵をつくらない陰謀術 ・鎌倉幕府の誕生 ・曾我兄弟の仇討ち事件 ・13人の合議制 ・ライバル梶原氏、比企氏を次々と滅ぼす 第二章 北条義時 「世論」を味方に朝廷を破る ・幕府きっての武人、和田氏の滅亡 ・将軍実朝暗殺事件 ・後鳥羽上皇との直接対決、承久の乱 第三章 北条泰時 「先進」京都に学んだ式目制定 ・明恵との出会い ・御成敗式目の制定 ・天皇の即位に介入 第四章 北条時頼 民を視野に入れた統治力 ・「撫民」とは何か ・仏教を政治に生かす ・三浦氏の滅亡 ・将軍を次々と取り換える 第五章 北条時宗、貞時 強すぎた世襲権力の弊害 ・二度の元寇のもたらしたもの ・改革者、安達泰盛の登場 ・霜月騒動で安達氏が滅亡 ・御内人、平頼綱の専制 第六章 北条高時 得宗一人勝ち体制が滅びた理由 ・高時は本当に「暗愚」だったのか ・後醍醐天皇はなぜ倒幕を考えたのか ・幕府にもっとも近かった足利尊氏の裏切り ・全国で根絶やしにされた北条一族 | |||
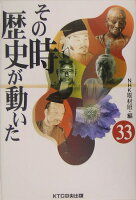
|
その時歴史が動いた 第33巻 | ||
| 著者 | 日本放送協会 | ||
| 出版社 | アノニマ・スタジオ | ||
| サイズ | 全集・双書 | ||
| 発売日 | 2005年06月 | ||
| 価格 | 1,760円(税込) | ||
| ISBN | 9784877583460 | ||
| 栄華と挫折、武士の時代の変革者たち。 | |||
(この項おわり)




鎌倉幕府を開いた源頼朝の嫡男・源頼家は、18歳で2代将軍となる。しかし、武士たちの領地を勝手に奪い、他の者に与えたり、土地を巡る武士同士の争いを不正に裁くという行為が絶えず、武士の不満は高まった。