二・二六事件

戒厳司令部が置かれた九段会館前
世界初の人工雪

人工雪誕生の地 - 北海道大学
1936年(昭和11年)3月12日、中谷宇吉郎が、北海道大学の低温実験室で、世界で初めて人工雪の製作に成功した。これを記念し、北海道大学 札幌キャンパスのメインストリート沿いに「人工雪誕生の地」の記念碑が建てられた。
中谷宇吉郎は、『雪』の中で、「雪の結晶は、天から送られた手紙である」と述べている。
中谷は東京帝国大学理学部で寺田寅彦に師事し、実験物理学を学んだ。大昔から雪の結晶の美しさは人々に知られているところであったが、その仕組みを科学によって解明し、人工雪を作ろうとした発想は、実験科学者ならではの発想だろう。

1932年(昭和7年)に北海道大学に赴任した中谷は、大学の廊下の片隅で、降ってくる雪をガラス板の上に受け取り、顕微鏡で観察することを始めた。約3千枚もの雪の結晶の写真をガラス乾板で撮り、結晶の種類を41に分類した。そして人工雪の製作に着手する。様々な形に結晶が成長する条件がわかれば、降る雪を観察することで、上空の気温や湿度の状態がわかると考えたからだった。さらに、当時、まだ不安定な乗り物だった飛行機の安全運行に資すると考えた。
人工雪を製作するには、空気中のチリのように核となる氷晶が必要だ。氷晶がなければ、どんなに気温が低くなっても、水蒸気は雪にならない。中谷は試行錯誤の結果、ウサギの毛を氷晶として人工雪を製作するのに成功した。
結晶成長の研究は、半導体やLEDの開発につながってゆく。

一方、スキー場の人工雪製造機が開発されるようになる。中谷の実験装置と原理は異なるが、1949年(昭和24年)にアメリカで初めて人工雪製造機(人工降雪機)が使用された。1950年代以降、アメリカで人工降雪機が開発・改良され、日本にも輸入された。
1961年(昭和36年)に営業を始めた晴山ホテルスキー場(現・軽井沢プリンスホテルスキー場)は、アメリカ製の人工降雪機を利用していたが、メンテナンスコストがかかることから、国産機を開発すべく、地元で真空ポンプなどを製造していた樫山工業に話を持ちかけた。樫山工業は中谷の実験を丁寧に調べあげ、1978年(昭和53年)に国産人工降雪機の開発に成功した。現在、軽井沢プリンスホテルスキー場にある195代の人工降雪機は、すべて樫山製だ。
中谷は東京帝国大学理学部で寺田寅彦に師事し、実験物理学を学んだ。大昔から雪の結晶の美しさは人々に知られているところであったが、その仕組みを科学によって解明し、人工雪を作ろうとした発想は、実験科学者ならではの発想だろう。
1932年(昭和7年)に北海道大学に赴任した中谷は、大学の廊下の片隅で、降ってくる雪をガラス板の上に受け取り、顕微鏡で観察することを始めた。約3千枚もの雪の結晶の写真をガラス乾板で撮り、結晶の種類を41に分類した。そして人工雪の製作に着手する。様々な形に結晶が成長する条件がわかれば、降る雪を観察することで、上空の気温や湿度の状態がわかると考えたからだった。さらに、当時、まだ不安定な乗り物だった飛行機の安全運行に資すると考えた。
人工雪を製作するには、空気中のチリのように核となる氷晶が必要だ。氷晶がなければ、どんなに気温が低くなっても、水蒸気は雪にならない。中谷は試行錯誤の結果、ウサギの毛を氷晶として人工雪を製作するのに成功した。
結晶成長の研究は、半導体やLEDの開発につながってゆく。
一方、スキー場の人工雪製造機が開発されるようになる。中谷の実験装置と原理は異なるが、1949年(昭和24年)にアメリカで初めて人工雪製造機(人工降雪機)が使用された。1950年代以降、アメリカで人工降雪機が開発・改良され、日本にも輸入された。
1961年(昭和36年)に営業を始めた晴山ホテルスキー場(現・軽井沢プリンスホテルスキー場)は、アメリカ製の人工降雪機を利用していたが、メンテナンスコストがかかることから、国産機を開発すべく、地元で真空ポンプなどを製造していた樫山工業に話を持ちかけた。樫山工業は中谷の実験を丁寧に調べあげ、1978年(昭和53年)に国産人工降雪機の開発に成功した。現在、軽井沢プリンスホテルスキー場にある195代の人工降雪機は、すべて樫山製だ。
この時代の世界
参考書籍
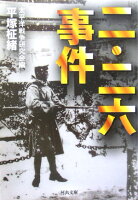
|
二・二六事件 | ||
| 著者 | 太平洋戦争研究会/平塚柾緒 | ||
| 出版社 | 河出書房新社 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 2006年02月 | ||
| 価格 | 825円(税込) | ||
| ISBN | 9784309407821 | ||
| 昭和十一(一九三六)年二月二六日未明、二十数名の帝国陸軍青年将校と彼らの思想に共鳴する民間人が、千五百名余の下士官兵を率い、時の首相・岡田啓介をはじめとする重臣たちを襲撃、殺害するというクーデター未遂事件が発生した!なぜ彼らは行動を起こし、何を夢見たのか。空前の事件の全経過と歴史の謎を今解き明かす。 | |||

|
雪 | ||
| 著者 | 中谷 宇吉郎 | ||
| 出版社 | 岩波書店 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 1994年10月17日頃 | ||
| 価格 | 627円(税込) | ||
| ISBN | 9784003112427 | ||
| 序 第一 雪と人生 第二 「雪の結晶」雑話 第三 北海道における雪の研究の話 第四 雪を作る話 附 記 附記 第十一刷に際して 解説 (樋口敬二) | |||
(この項おわり)



岡田啓介総理大臣は難を逃れるが、高橋是清大蔵大臣、斎藤実内大臣、渡辺錠太郎教育総監が殺害され、鈴木貫太郎侍従長が重傷を負った。神奈川県湯河原滞在中の牧野伸顕・前内大臣も襲われたが、危うく難を逃れた。
陸軍では統制派と皇道派の思想対立が激化しており、1935年(昭和10年)7月に林銑十郎陸相による皇道派の真崎甚三郎教育総監が更迭され、8月には、その更迭の推進者と目された永田鉄山軍務局長が相沢三郎中佐に斬殺されるなど、エスカレートの一途をたどっていた。そこに皇道派青年将校の牙城である第一師団の満州派遣が決定されたため、青年将校たちは武力蜂起を早め、首相官邸はじめ陸軍省、警視庁などを占拠し、川島義之陸相に「蹶起趣意書」を突きつけ、国家改造の断行を要求した。
股肱の重臣を殺傷された昭和天皇は激怒し、蜂起部隊の鎮圧を命じた。
2月27日、枢密院の審査を経て東京に戒厳令が敷かれた。戒厳令を推進した参謀本部作戦課長の石原莞爾大佐は青年将校の蜂起を逆利用して、軍事独裁体制の樹立を図ろうとしていた。
2月28日、ついに反乱鎮定の奉勅命令が香椎戒厳司令官に発せられ、蜂起部隊に占拠撤収を求めた。29日に戒厳司令部は約2万4000人の兵力で反乱軍を包囲して戦闘態勢をとったが、ラジオ放送や飛行機からのビラ、アドバルーンなどで「今カラデモ遅クナイカラ原隊ヘ帰レ」「抵抗スル者ハ全部逆賊デアルカラ射殺スル」などと、下士官・兵に帰順を呼びかけたところ、大部分の下士官・兵は帰順し、4日間で反乱は鎮圧された。
東京・牛込納戸町に暮らしていた思想家の北一輝は、日蓮宗と労働者の主権、社会主義を結び付けた独特の思想を発表しており、皇道派青年将校の理論的指導者として逮捕され、軍法会議で死刑判決を受けて刑死した。