ダーウィン『種の起源』

チャールズ・ダーウィン(1869年)

種の起源
『種の起源』では、すべての生物は一種あるいはほんの数種の祖先から分岐して進化してきたと述べているが、その祖先はどうやって誕生したのか、また具体的にどのように進化してきたのかについては触れられていない。当時はDNAはおろか、1865年に発見されたメンデルの遺伝法則の法則も1900年に“再発見”されるまで埋もれたままだったのだ。
にもかかわらず、『種の起源』は当時の科学者に指示され、さまざまな進化論が登場するきっかけとなった。
一方、『種の起源』は当時の宗教概念を覆す内容とみなされ、宗教的、哲学的論争を引き起こすことになる。現在でも、アメリカの一部の州などで、『種の起源』に基づく進化論は否定されている。
にもかかわらず、『種の起源』は当時の科学者に指示され、さまざまな進化論が登場するきっかけとなった。
一方、『種の起源』は当時の宗教概念を覆す内容とみなされ、宗教的、哲学的論争を引き起こすことになる。現在でも、アメリカの一部の州などで、『種の起源』に基づく進化論は否定されている。

ビーグル号
1835年9月から10月にかけ、ビーグル号はガラパゴス諸島のチャタム島(現・サンクリストバル島)に滞在した。この時点では、ダーウィンはまだ、進化や種の分化に気づいておらず、さまざまな動物とその変種をそのまま記録するにとどまっている。
ちなみに、ダーウィンが持ち帰ったとされるガラパゴスゾウガメ「ハリエット」は、2006年6月22日まで生き続けた。
ちなみに、ダーウィンが持ち帰ったとされるガラパゴスゾウガメ「ハリエット」は、2006年6月22日まで生き続けた。
1836年6月にはケープタウンへ寄港し、天王星を発見したウィリアム・ハーシェルの息子で天文学者のジョン・ハーシェルを訪ねている。
そして1836年10月、ファルマス港に帰着した。航海は当初3年の予定だったが、ほぼ5年が経過していた。

ダーウィンは、1837年3月、研究がしやすいロンドンに移住し、世界で初めてプログラム可能な計算機を考案したチャールズ・バベッジをはじめとする学者の輪に加わり、議論を深めあった。
ところが、1838年頃から原因不明の胃炎や頭痛、動悸などの症状に苦しめられるようになり、これは死ぬまで治癒しなかった。
そして1836年10月、ファルマス港に帰着した。航海は当初3年の予定だったが、ほぼ5年が経過していた。
ダーウィンは、1837年3月、研究がしやすいロンドンに移住し、世界で初めてプログラム可能な計算機を考案したチャールズ・バベッジをはじめとする学者の輪に加わり、議論を深めあった。
ところが、1838年頃から原因不明の胃炎や頭痛、動悸などの症状に苦しめられるようになり、これは死ぬまで治癒しなかった。

トマス・マルサス
ロンドンで研究を続けているときに、ダーウィンはトマス・マルサスの『人口論』を読んでいる。マルサスは『人口論』の中で、人類の人口は等比数列的に増加し、すぐに食糧供給を越え破局が起きると述べていた。
ダーウィンは、この考えを野生動物に拡大し、適者生存と自然選択という概念にたどりついた。
ダーウィンは、この考えを野生動物に拡大し、適者生存と自然選択という概念にたどりついた。

アルフレッド・ウォレス
南米や東南アジアを探検していた博物学者のアルフレッド・ウォレスは、ダーウィンとは別に自然選択に至り、1858年頃にダーウィンに手紙を送っている。ダーウィンはウォレスとの文通に触発され、『種の起源』の出版を決断したとも言われている。

ウォレスはダーウィンと異なり、自然選択は適者生存の結果ではなく、宇宙の存在意義であると考えた。彼はその後、心霊主義に傾倒し、コナン・ドイルやマーク・トウェインに影響を与えた。
ウォレスはダーウィンと異なり、自然選択は適者生存の結果ではなく、宇宙の存在意義であると考えた。彼はその後、心霊主義に傾倒し、コナン・ドイルやマーク・トウェインに影響を与えた。

メンデル
研究を続けていたダーウィンは、1859年11月24日、それまでの成果を集大成した著作『種の起源』を出版する。反響は大きかった。
ドイツの解剖学者エルンスト・ヘッケルらは進化論の普及に努めたが、解剖学者のリチャード・オーウェンや『昆虫記』で有名なアンリ・ファーブルは反対論者に回った。
1865年に遺伝の法則を発見したメンデルも『種の起源』を入手していたが、ほとんど読んでいなかったという。ダーウィンとメンデルの交流はなかったとみられる。
ドイツの解剖学者エルンスト・ヘッケルらは進化論の普及に努めたが、解剖学者のリチャード・オーウェンや『昆虫記』で有名なアンリ・ファーブルは反対論者に回った。
1865年に遺伝の法則を発見したメンデルも『種の起源』を入手していたが、ほとんど読んでいなかったという。ダーウィンとメンデルの交流はなかったとみられる。

ケルビン卿ウィリアム・トムソン
熱力学第二法則の発見者の1人であり、大西洋海底電子ケーブル敷設を指揮したイギリスのケルビン卿ウィリアム・トムソンは、進化論反対派の急先鋒であった。
ケルヴィンは、地球の年齢を計算した物理学の論文のなかで、地球が誕生したのはせいぜい1億年前だと主張した。ケルヴィンは、生物の多様性は進化の産物ではなく、創造主である神によるものだと信じて疑わなかった。
イギリス科学振興協会会長、王立教委会会長、グラスゴー大学学長などを歴任したケルヴィンは、多くの科学者、技術者を日本に派遣し、1901年、明治政府から勲一等瑞宝章を叙勲されている。
ケルヴィンは、地球の年齢を計算した物理学の論文のなかで、地球が誕生したのはせいぜい1億年前だと主張した。ケルヴィンは、生物の多様性は進化の産物ではなく、創造主である神によるものだと信じて疑わなかった。
イギリス科学振興協会会長、王立教委会会長、グラスゴー大学学長などを歴任したケルヴィンは、多くの科学者、技術者を日本に派遣し、1901年、明治政府から勲一等瑞宝章を叙勲されている。
病気がちだったダーウィンは、こうした議論に直接的に参加することはなかったが、兄や妻、子どもたちの助けを借り、科学者たちの反応や報道記事を小まめにチェックし、世界中の同僚と意見交換している。
たとえば、1871年に植物学者ジョセフ・ダルトン・フッカー宛ての手紙の中で、「さまざまな種類のアンモニアやリン酸塩が溶けた温かい小さな池に、光や熱や電気などが加えられたとしたら、タンパク質分子が化学的に合成され、より複雑なものへと変化したでしょう。今日ではそのような物質はすぐに食べ尽くされてしまうでしょうが、生命が誕生する前では、そうはならなかったでしょう」と記しており、現在、生命発生の仮説の1つとなっている「有機物のスープ」に近い考え方を示した。
たとえば、1871年に植物学者ジョセフ・ダルトン・フッカー宛ての手紙の中で、「さまざまな種類のアンモニアやリン酸塩が溶けた温かい小さな池に、光や熱や電気などが加えられたとしたら、タンパク質分子が化学的に合成され、より複雑なものへと変化したでしょう。今日ではそのような物質はすぐに食べ尽くされてしまうでしょうが、生命が誕生する前では、そうはならなかったでしょう」と記しており、現在、生命発生の仮説の1つとなっている「有機物のスープ」に近い考え方を示した。
ビーグル号での5年にわたる航海を終えて帰国したダーウィンは、1839年、ジョサイア2世の娘エマと結婚した。ダーウィン家からは1万ポンドの一時金と500ポンドの一時金を、ウェッジウッド家からは5000ポンドの一時金と400ポンドの年金が贈られた。ダーウィンに地質学の指導をしたケンブリッジ大学のセジウィック教授のの年棒は100ポンドであった。
ダーウィンは資産を株式運用に充て、『種の起源』が発表された頃の年収は5000ポンド、1870年以降は8000ポンドにもなったという。
ロンドン郊外のダウンの屋敷には常に10人前後の使用人を雇っており、何不自由ない暮らしを過ごしていたのである。
ダーウィンは資産を株式運用に充て、『種の起源』が発表された頃の年収は5000ポンド、1870年以降は8000ポンドにもなったという。
ロンドン郊外のダウンの屋敷には常に10人前後の使用人を雇っており、何不自由ない暮らしを過ごしていたのである。

ジョサイア・ウェッジウッド
ウェッジウッド家は、世界的に有名な陶磁器会社であり、ダーウィンの妻エマの祖父ジョサイア・ウェッジウッドが創業した。
ダーウィンの祖父エラズマス・ダーウィンは裕福な開業医で、ジョサイアと親交があった。エラズマスの息子ロバートも裕福な開業医であったが、その縁で、ジョサイアの娘スザンナと結婚した。この夫婦の間に生まれたのがダーウィンである。したがって、ダーウィンと妻エマはいとこ同士ということになる。
このように、当時のヨーロッパの富豪の間では、富を一族の中で守り、家系を安定させようとする傾向があった。
ダーウィンの祖父エラズマス・ダーウィンは裕福な開業医で、ジョサイアと親交があった。エラズマスの息子ロバートも裕福な開業医であったが、その縁で、ジョサイアの娘スザンナと結婚した。この夫婦の間に生まれたのがダーウィンである。したがって、ダーウィンと妻エマはいとこ同士ということになる。
このように、当時のヨーロッパの富豪の間では、富を一族の中で守り、家系を安定させようとする傾向があった。
たとえば、国際金融で財をなしたロスチャイルド家の始祖マイヤーの男の孫で結婚した者は12人いるが、そのうち9人がいとこを妻にしている。その後もロスチャイルド一族は血族結婚を繰り返している。
参考書籍

|
種の起源(上)改版 | ||
| 著者 | ダーウィン,C.R.(チャールズ・ロバート)/八杉 龍一 | ||
| 出版社 | 岩波書店 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 1990年02月16日頃 | ||
| 価格 | 1,353円(税込) | ||
| ISBN | 9784003391242 | ||
| 訳者まえがき 序 言 第一章 飼育栽培のもとでの変異 第二章 自然のもとでの変異 第三章 生存闘争 第四章 自然選択 第五章 変異の法則 第六章 学説の難点 第七章 本 能 第八章 雑 種 付 録 種の起原にかんする意見の進歩の歴史的概要 解 題 訳 者 注 | |||
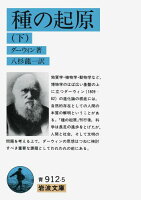
|
種の起源(下)改版 | ||
| 著者 | ダーウィン,C.R.(チャールズ・ロバート)/八杉 龍一 | ||
| 出版社 | 岩波書店 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 1990年02月16日頃 | ||
| 価格 | 1,276円(税込) | ||
| ISBN | 9784003391259 | ||
| 第九章 地質学的記録の不完全について 第一〇章 生物の地質学的遷移について 第一一章 地理的分布 第一二章 地理的分布(続) 第一三章 生物の相互類縁。形態学。発生学。痕跡器官。 第一四章 要約と結論 付 録 自然選択説にむけられた種々の異論 術語解説 索 引 訳 者 注 | |||
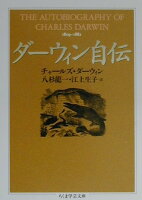
|
ダーウィン自伝 | ||
| 著者 | チャ-ルズ・ロバ-ト・ダ-ウィン/八杉龍一 | ||
| 出版社 | 筑摩書房 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 2000年06月07日頃 | ||
| 価格 | 1,320円(税込) | ||
| ISBN | 9784480085580 | ||
| 進化論によって近代思想に画期的な影響をおよぼしたチャールズ・ダーウィンの自伝。本書は孫娘ノラ・バーロウの編集による無削除決定版で、従来の版では削除されていた、彼の徹底した宗教否定の立場、当時の学者などに対する人物評、思想形成の過程など興味深い事実が語られている。また、19世紀イギリス思想史の貴重な史料にもなっている。 | |||

|
生命と非生命のあいだ | ||
| 著者 | 小林 憲正 | ||
| 出版社 | 講談社 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2024年04月18日頃 | ||
| 価格 | 1,210円(税込) | ||
| ISBN | 9784065356722 | ||
| 地球に生命が誕生したことは「奇跡」なのか? それとも「必然」なのか? たとえば天文学者のフレッド・ホイルは、生命ができる確率は「がらくた置き場の上を竜巻が通りすぎたあとにジャンボジェットが組み上がっている確率」にひとしく、それは10の4万乗分の1ほどであると言った。それほどできにくいものが、なぜ地球にはこんなに存在するのか? もしかしたら、生命とは本当に「神の仕業」なのか? 「生命の起源」についての仮説として圧倒的な支持を集める「RNAワールド」が説明できないこの問いに、アストロバイオロジーの第一人者が正面から向き合い、フラスコの中から宇宙空間にまで思索を広げて提唱する「がらくたワールド」と「生命スペクトラム」とは何か。非生命はいかにして生命になるのか、神に頼らない説明は、はたして可能なのか? 「生命の起源」研究の全貌と、何が論点なのかを類書にないわかりやすさで整理し、宇宙の開闢と並ぶ現代科学「究極の謎」に挑む、著者の代表作! (おもな内容) ◆生命の材料は「化学進化」で意外と簡単にできる ◆初めてフラスコ内でアミノ酸をつくったミラーの「罪」 ◆生命が誕生したのは海か陸か、それぞれの言い分は? ◆地球に大量のアミノ酸を持ち込んだ隕石と宇宙塵 ◆「RNAワールド仮説」はなぜ圧倒的に支持されているのか ◆生命の材料を正しくつなぎ合わせることがいかに難しいか ◆化学進化の「王道」を行くとRNAは「神のいたずら」になる ◆宇宙に目を向けることで「生命の起源探し」は「科学」になった ◆「地球生命」誕生の謎は「地球外生命」が見つかれば解ける ◆ダーウィン進化の正しい理解から導かれる「がらくたワールド」とは? ◆選ばれたわずかな分子を急激に増加させる「自己触媒反応」の威力 ◆「生命」と「非生命」のあいだに境界はあるのか? など 序 章 「生命」は奇跡か必然か 第1章 生命はどこから来たのか 生命は何者か 第2章 「RNAワールド」への道 第3章 「生命の起源」は宇宙にあるのか 第4章 いつ生まれたのか どこで生まれたのか 第5章 「がらくたワールド」という考え方 第6章 地球外生命から考える地球生命 第7章 生物進化から考える化学進化 第8章 生命のスペクトラム | |||
この時代の世界
(この項おわり)




ダーウィンは、自然選択によって生物は環境に適応するように変化し、その種が分岐して多様な種が生まれると述べた。生存競争に打ち勝った種は生き残る(適者生存)と説明している。
その後もダーウィンによる改版が続けられ、1872年ないし1876年まで内容が修正されていたという。