日本初の地下鉄


1927年(昭和2年)、大蔵大臣の片岡直温が衆議院予算委員会の場で、東京渡辺銀行が破綻したという発言をしたため、銀行の取り付け騒ぎが起こり、昭和金融恐慌に発展する。
金融恐慌の原因は第一次世界大戦に遡る。戦争で沸いたバブル景気の際に発生した不良債権の一部が、関東大震災の際に降り出した震災手形で隠され、結果として昭和に入るまで持ち越されてしまったのである。
時の田中義一総理は、ピンチヒッターとして高橋是清に大蔵大臣就任を要請した。
高橋は、ただちに日本全国の銀行を3日間休業とし、その間に紙幣を大増刷した。それまでの最高額紙幣は百円だったが、あらたに二百円紙幣を発行した。しかも、片面にしか印刷していないという急場しのぎの紙幣であった。
4月25日に銀行が再開された時には取り付け騒ぎは収まり、情勢は落ち着きを見せた。その後、政府は裏白二百円紙幣を回収していった。
5月8日には金融安定化のための法案を可決し、6月2日、役目を終えた高橋は大蔵大臣を辞任する。
高橋は、ただちに日本全国の銀行を3日間休業とし、その間に紙幣を大増刷した。それまでの最高額紙幣は百円だったが、あらたに二百円紙幣を発行した。しかも、片面にしか印刷していないという急場しのぎの紙幣であった。
4月25日に銀行が再開された時には取り付け騒ぎは収まり、情勢は落ち着きを見せた。その後、政府は裏白二百円紙幣を回収していった。
5月8日には金融安定化のための法案を可決し、6月2日、役目を終えた高橋は大蔵大臣を辞任する。
ところが、1929年(昭和4年)、今度はアメリカを発端にした世界恐慌が起きる。

この年に成立した民政党の浜口雄幸内閣は、為替相場の安定と輸出拡大を目論見、1917年(大正6年)以来禁止していた金の輸出を解禁した。金本位制に戻そうとするこの政策は世界情勢を楽観視したもので、実際には欧米各国が日本の金を買い漁る結果となり、輸出は伸びず、日本の不況はより深刻化した。町には失業者があふれ、農村部では娘の身売りが行われるほどひどいものであった。

こうした政策の失敗を嫌われ、1930年(昭和5年)11月14日、浜口首相は東京駅で狙撃される。浜口は一命を取り留めるが、この時の傷が原因で翌年8月に死去する。
1931年(昭和6年)12月、政府は再び金の輸出を禁止する。
この年に成立した民政党の浜口雄幸内閣は、為替相場の安定と輸出拡大を目論見、1917年(大正6年)以来禁止していた金の輸出を解禁した。金本位制に戻そうとするこの政策は世界情勢を楽観視したもので、実際には欧米各国が日本の金を買い漁る結果となり、輸出は伸びず、日本の不況はより深刻化した。町には失業者があふれ、農村部では娘の身売りが行われるほどひどいものであった。
こうした政策の失敗を嫌われ、1930年(昭和5年)11月14日、浜口首相は東京駅で狙撃される。浜口は一命を取り留めるが、この時の傷が原因で翌年8月に死去する。
1931年(昭和6年)12月、政府は再び金の輸出を禁止する。
この時代の世界
参考書籍

|
昭和金融恐慌史 | ||
| 著者 | 高橋亀吉/森垣淑 | ||
| 出版社 | 講談社 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 1993年03月10日頃 | ||
| 価格 | 1,265円(税込) | ||
| ISBN | 9784061590663 | ||
| 日本中の銀行が預金取付の大津波に襲われ、異例の支払猶予令が断行された昭和金融恐慌。東京渡辺銀行などの倒産、破産が続出し、休業銀行の多くは預金の4〜5割を切捨てた。この大異変の背景には銀行の前近代性と、熱狂的投機ブームの反動で膨れた莫大な不良債権があった。在野の経済評論家として名高い高橋亀吉を主執筆者とし、金融恐慌の原因と実態を豊富なデータを駆使して解明した注目の書。 | |||
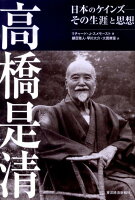
|
高橋是清 ―日本のケインズ その生涯と思想 | ||
| 著者 | リチャード・J.スメサースト/鎮目雅人 | ||
| 出版社 | 東洋経済新報社 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2010年10月 | ||
| 価格 | 5,500円(税込) | ||
| ISBN | 9784492395387 | ||
| 幼くして渡航、後に海外の財界人たちと厚い友情を築き上げた「日本のケインズ」の開かれた思想の形成に迫る。 | |||

|
昭和恐慌と経済政策 | ||
| 著者 | 中村 隆英 | ||
| 出版社 | 講談社 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 1994年06月 | ||
| 価格 | 924円(税込) | ||
| ISBN | 9784061591301 | ||
| 大戦景気の反動、金融恐慌などが続いた昭和初期、浜口内閣の大蔵大臣・井上準之助は、為替変動の安定化をめざし金輸出の解禁を断行。念願の金本位制復帰を図ったが、そのための緊縮財政は折からの世界恐慌の波をうけ、未曾有の大不況を到来させた。この昭和恐慌を引き起こした経済政策をめぐる政党間の抗争、財界の思惑、投機的行動など、秘められた歴史を明らかにした昭和経済史の泰斗による力作。 1 金解禁まで 1.金本位の意味するもの 2.日本の金本位制 3.海外の金本位復帰 4.金解禁是か非か 5.金融恐慌 6.田中内閣から浜口内閣へ 2 金解禁の実施 1.井上準之助 2.解禁の準備 3.金解禁賛成論 4.金解禁反対論 5.解禁の実施 6.世界恐慌 3 恐慌下の日本 1.産業合理化 2.農村の窮乏 3.中小企業の危機 4.失業の増大 5.政治的動揺 4 危機の切迫 1.井上の政策 2.財閥の動向 3.ドイツの金融恐慌とイギリスの金本位離脱 4.満州事変の勃発 5 金輸出再禁止 1.ドル買い問題 2.陸軍の圧力と協力内閣運動 3.井上の抵抗 4.第2次若槻内閣の倒壊 5.金輸出の再禁止と井上の死 6.高橋財政の方向 | |||

|
昭和恐慌の研究 | ||
| 著者 | 岩田規久男 | ||
| 出版社 | 東洋経済新報社 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2004年04月 | ||
| 価格 | 3,960円(税込) | ||
| ISBN | 9784492371022 | ||
| 1930年の金解禁をきっかけに、日本は恐慌に陥った。そのとき経済学者たちは、いかなる論戦を繰り広げたのか?何が恐慌からの脱出を可能にしたのか?70年前、日本を襲った未曽有の経済危機、われわれは今、何を学ぶべきか。 | |||
参考サイト
- 地下鉄博物館:ぱふぅ家のホームページ
(この項おわり)



一方、東京高速鉄道株式会社は1939年(昭和14年)に新橋~渋谷間6.3キロを開業。こうして銀座線が全通する。
さらに1941年(昭和16年)には両社が合併し、帝都高速度交通営団(現・東京メトロ)が誕生した。