
1970年(昭和45年)2月11日、東京大学宇宙航空研究所は、ラムダロケットを使って日本初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げに成功する。ロケット打ち上げ場である内之浦宇宙空間観測所のある大隅半島にちなんで名付けられた。ソ連、アメリカ、フランスに次いで、世界で4番目の人工衛星打ち上げ国となった。

近地点350km 遠地点5140km、地球を1周するのに145分かかる楕円軌道に乗ったおおすみは、発射後約2時間半を経過した15時56分10秒から16時06分54秒までの間、内之浦で信号電波を受信することができ、地球を1周してきたことが確認された。
だが、受信レベルは徐々に下がり、7周目で受信できなくなってしまった。衛星本体が高温になり、電源容量が急速に低下したものと考えられている。
おおすみは、その後も地球周回を続け、打ち上げから33年半後の2003年(平成15年)8月2日05時45分(日本標準時)、大気圏に突入し、消滅した。
だが、受信レベルは徐々に下がり、7周目で受信できなくなってしまった。衛星本体が高温になり、電源容量が急速に低下したものと考えられている。
おおすみは、その後も地球周回を続け、打ち上げから33年半後の2003年(平成15年)8月2日05時45分(日本標準時)、大気圏に突入し、消滅した。
ペンシルロケットから「おおすみ」まで

日本の宇宙開発は、糸川英夫・東京大学教授が、1955年(昭和30年)4月に国分寺市で長さ23cm、直径1.8cmのペンシルロケットの水平発射実験を行ったのが始まりである。
戦時中、「九七式」「隼」「鍾馗」といった航空機開発に携わった糸川であったが、戦後はGHQによって航空機開発が禁止された。渡米した糸川は、アメリカのロケット技術が未熟であることを見抜き、これなら日本でも勝てると考え、ロケット開発に転向したという。
だが、当時の日本のレーダー技術は貧弱なもので、ロケットの軌道を追跡できない。そこで、ペンシルロケットは水平発射し、途中、吸い取り紙を置いて、それを破った時刻によって加速度などを計測した。まさに『逆転の発想』(糸川の名著)である。
だが、当時の日本のレーダー技術は貧弱なもので、ロケットの軌道を追跡できない。そこで、ペンシルロケットは水平発射し、途中、吸い取り紙を置いて、それを破った時刻によって加速度などを計測した。まさに『逆転の発想』(糸川の名著)である。

そして、IGYが終わろうとしている1958年(昭和33年)9月、高度60kmまで届くようになった。100kmには届かなかったが、高層大気を観測できる高さに届いた。IGYでロケットを打ち上げられたのは、アメリカ、ソ連、イギリス、日本の4カ国だけだった。

ところで、道川海岸を打ち上げ実験場として選定したとき、もうひとつ佐渡島という候補地があった。だが、船に弱い糸川は、佐渡島の視察の際にひどい船酔いにかかった。上陸するやいなや、佐渡島を却下したという。

1963年(昭和38年)に後継のラムダ・ロケットの打ち上げが始まり、1966年(昭和41年)に誕生したL-4Sロケットによっておおすみは打ち上げられた。
L-4Sは、4段式のロケットで、全長16.5m、直径0.735m、総重量は9.4トン。低軌道に第4段と合わせた26kgのペイロードを投入する能力がある。国立科学博物館の外庭には、発射ランチャに乗ったL-4Sロケットが展示されている。
1966年(昭和41年)、ミュー・ロケットの開発が始まった。1970年(昭和45年)に打ち上げられたM-4Sロケットは、低軌道に180kgのペイロードを打ち上げることが可能である。
1997年(平成9年)にはM-Vロケットが打ち上げられた。3段式のロケットで、全長30.8m、直径2.5m、総重量は140.4トン。低軌道に1.85トンのペイロードを投入する能力がある。
2006年(平成18年)9月23日のSOLAR-Bの打ち上げを最後に現役を退き、完全国産固体燃料ロケットの時代は終わった。
ミュー・ロケットで培われた技術は、H-IIロケットの固体ロケットブースターや、イプシロンロケットなどに活用されている。
ところで、道川海岸を打ち上げ実験場として選定したとき、もうひとつ佐渡島という候補地があった。だが、船に弱い糸川は、佐渡島の視察の際にひどい船酔いにかかった。上陸するやいなや、佐渡島を却下したという。
1963年(昭和38年)に後継のラムダ・ロケットの打ち上げが始まり、1966年(昭和41年)に誕生したL-4Sロケットによっておおすみは打ち上げられた。
L-4Sは、4段式のロケットで、全長16.5m、直径0.735m、総重量は9.4トン。低軌道に第4段と合わせた26kgのペイロードを投入する能力がある。国立科学博物館の外庭には、発射ランチャに乗ったL-4Sロケットが展示されている。
1966年(昭和41年)、ミュー・ロケットの開発が始まった。1970年(昭和45年)に打ち上げられたM-4Sロケットは、低軌道に180kgのペイロードを打ち上げることが可能である。
1997年(平成9年)にはM-Vロケットが打ち上げられた。3段式のロケットで、全長30.8m、直径2.5m、総重量は140.4トン。低軌道に1.85トンのペイロードを投入する能力がある。
2006年(平成18年)9月23日のSOLAR-Bの打ち上げを最後に現役を退き、完全国産固体燃料ロケットの時代は終わった。
ミュー・ロケットで培われた技術は、H-IIロケットの固体ロケットブースターや、イプシロンロケットなどに活用されている。
この時代の世界
参考書籍
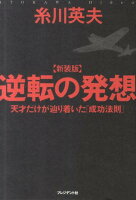
|
新装版 逆転の発想 | ||
| 著者 | 糸川英夫 | ||
| 出版社 | プレジデント社 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2011年07月 | ||
| 価格 | 1,571円(税込) | ||
| ISBN | 9784833419642 | ||
| 最近、ビジネスマンの方々と話していると、これからの日本はどうなるのか?企業はどうしたらいいのかといった質問をやたらと受ける。そこで、本書ではこうした“危機感”がいったいどこから生じているのか?その処方箋は何か?著者なりの考えを具体的に述べたものである。 | |||

|
ニッポン宇宙開発秘史 | ||
| 著者 | 的川泰宣 | ||
| 出版社 | NHK出版 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2017年11月 | ||
| 価格 | 858円(税込) | ||
| ISBN | 9784140885338 | ||
| 敗戦国が始めた宇宙開発は、いまや世界トップレベルの技術を持つに至った。本書は、笑いあり涙ありの舞台裏をまじえて、その道のりを活写。逆境と克服を繰り返した歴史を辿ると、日本が持つ真の力と今後の行く末が見えてきた!なぜ私たちは宇宙をめざすのか?民間ロケットや「みちびき」は何をもたらすのか?「宇宙教育の父」が書き下ろす、一気読み間違いなしの決定版。 | |||
(この項おわり)


