
1971年(昭和46年)、ビジコン社の社員としてインテルに赴いた嶋正利、インテルのフェデリコ・ファジン、テッド・ホフらによって世界初のマイクロプロセッサ「Intel 4004」が開発される。
ビジコンは1966年(昭和41年)に30万円を切る電卓を投入して業界に衝撃を与えた中堅の電卓メーカーである。ビジコンは、多品種展開のためにストアドプログラム方式に基づく電卓を開発しようとしていた。その際に、LSIの開発を委託したのがまだ創業間もないインテルだった。
そこでインテルのテッド・ホフは、マイクロ命令を採用した汎用的に使える4ビット・マイクロプロセッサを提案した。これが4004である。

ただ4004の開発は一筋縄ではいかなかった。
1969年(昭和44年)12月、テッド・ホフと嶋正利らは基本アーキテクチャを完成した。この時点で嶋らをビジコンの技術者は一度日本に戻った。1970年(昭和45年)4月に再渡米したとき、4004の回路設計はまったく進んでいなかった。回路技術者としてフェデリコ・ファジンを採用したばかりで、ホフからファジンへの引き継ぎもなかったという。そこで嶋は論理設計を担当し、ファジンと協力して4004を開発した。
このときの働きが評価された嶋は、のちに「Intel 8080」の開発を手がけることになる。
そこでインテルのテッド・ホフは、マイクロ命令を採用した汎用的に使える4ビット・マイクロプロセッサを提案した。これが4004である。
ただ4004の開発は一筋縄ではいかなかった。
1969年(昭和44年)12月、テッド・ホフと嶋正利らは基本アーキテクチャを完成した。この時点で嶋らをビジコンの技術者は一度日本に戻った。1970年(昭和45年)4月に再渡米したとき、4004の回路設計はまったく進んでいなかった。回路技術者としてフェデリコ・ファジンを採用したばかりで、ホフからファジンへの引き継ぎもなかったという。そこで嶋は論理設計を担当し、ファジンと協力して4004を開発した。
このときの働きが評価された嶋は、のちに「Intel 8080」の開発を手がけることになる。
この時代の世界
参考書籍
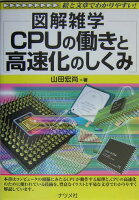
|
CPUの働きと高速化のしくみ | ||
| 著者 | 山田宏尚 | ||
| 出版社 | ナツメ社 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2004年04月 | ||
| 価格 | 1,540円(税込) | ||
| ISBN | 9784816336959 | ||
| CPU(Central Processing Unit「中央処理装置」と訳される)は、パソコンだけでなく、エアコンや炊飯器など、驚くほど身近な機器に搭載されています。そのような機器になぜ、CPUが必要なのか。それは、CPUに仕事(処理)をする能力があるからだ。ただの石のように見えるCPUにどうして仕事ができるのか。本書ではその原理を解説している。はじめは簡単なことしかできなかったCPUが、いろいろなことができるようになった。その発展の歴史も掲載。そして、CPUがより高速に処理を行えるように考えられた、驚くべき技術についてもしっかり解説。 | |||
(この項おわり)


