同志社英学校が開校

新島八重
新島襄は同志社英学校を開校する直前の10月、新島八重と婚約している。
八重は、悪妻、烈婦、元祖ハンサムウーマンなどと呼ばれるほど明治の時代にあってエネルギッシュに生き、皇族以外の女性としてはじめて政府より叙勲を受けた先進的な女性である。
八重は、悪妻、烈婦、元祖ハンサムウーマンなどと呼ばれるほど明治の時代にあってエネルギッシュに生き、皇族以外の女性としてはじめて政府より叙勲を受けた先進的な女性である。
新島八重の足跡
参考書籍

|
新島八重 (学習漫画 世界の伝記NEXT) | ||
| 著者 | 柊 ゆたか/三上 修平/本井 康博 | ||
| 出版社 | 集英社 | ||
| サイズ | 全集・双書 | ||
| 発売日 | 2012年12月14日頃 | ||
| 価格 | 1,210円(税込) | ||
| ISBN | 9784082400590 | ||
| 2013年NHK大河ドラマの主人公 会津を救いたいと城にこもって戦った八重に、維新後の日本は別の人生を与えた。夫・新島襄を助けて、まだ偏見の残るキリスト教の学校を設立。そして晩年は看護師を育てるなど、まさに波瀾の生涯。 | |||

|
新島八重 ハンサムな女傑の生涯 | ||
| 著者 | 同志社同窓会 | ||
| 出版社 | 淡交社 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2012年10月 | ||
| 価格 | 1,320円(税込) | ||
| ISBN | 9784473038395 | ||
| その個性から、「幕末のジャンヌ・ダルク」「ハンサムウーマン」「悪妻」など、さまざまに語られる新島八重。夫・新島襄をして、「ハンサム」と言わしめた自立した一個の個性の生涯を、7つのテーマで追う。 | |||
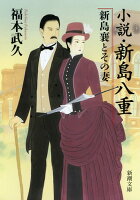
|
小説・新島八重 新島襄とその妻 | ||
| 著者 | 福本 武久 | ||
| 出版社 | 新潮社 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 2012年08月28日頃 | ||
| 価格 | 649円(税込) | ||
| ISBN | 9784101366128 | ||
| 故郷・会津を離れた八重は兄が生き延びていたという京都へ向かう。その地で英語を学んで西洋文化に触れ、キリスト教の洗礼を受けるに至る。そして兄の友人・新島襄と出会い、結婚。二人はキリスト教への偏見、政府の無理解、資金難など幾多の困難と闘いながら、同志社の礎を築く。また女性の自立を目指し奔走した。激動の明治維新を生きたある男と女の物語。 | |||
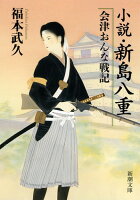
|
小説・新島八重 会津おんな戦記 | ||
| 著者 | 福本武久 | ||
| 出版社 | 新潮社 | ||
| サイズ | 文庫 | ||
| 発売日 | 2012年09月 | ||
| 価格 | 539円(税込) | ||
| ISBN | 9784101366111 | ||
| 時は戊辰戦争終盤、新政府軍が会津・鶴ヶ城を攻めたてる。同藩砲術指南役の家に生まれた山本八重は、女だてらにスペンサー銃を担ぎ、砲術隊を率いて敵を迎え撃つ。しかし戦い破れ会津藩は消滅、八重は父と弟を喪い、夫とも離別することとなる。日本近代に押し寄せる大波のなかで、のちに同志社大学を創立した新島襄の妻となる女性の若き激動の日々を描く。 | |||

|
新島八重 愛と闘いの生涯 | ||
| 著者 | 吉海 直人 | ||
| 出版社 | KADOKAWA | ||
| サイズ | 全集・双書 | ||
| 発売日 | 2012年04月23日頃 | ||
| 価格 | 1,760円(税込) | ||
| ISBN | 9784047035058 | ||
| 新島襄の妻・八重。女性でありながら戊辰戦争に参加、日清・日露戦争で篤志看護婦を務め、「日本のナイチンゲール」と称賛された。著者発見の新史料を活かし、エピソードで綴る、新島八重伝の決定版。 〈目次〉 はじめに 第一章 八重の生涯 初期 幕末のジャンヌ・ダルクあるいは会津の巴御前──会津若松時代 コラム1 什のおきて 中期 ハンサム・ウーマンあるいはクリスチャン・レディ──新島襄との夫婦時代 コラム2 徳富蘆花の見た八重 コラム3 八重は警察官 後期 日本のナイチンゲール 会津魂再び──未亡人時代 コラム4 新島の名前について 第二章 八重をめぐるエピソード 1 八重と「板かるた」 2 「明日の夜は」の歌をめぐって コラム5 八重は「荒城の月」のモデル? 3 八重歌集抄 4 前夫・川崎尚之助の新事実 5 偉大な兄・山本覚馬 6 日向ユキとの交流 7 やんちゃな満坊──教科書に載った新島夫妻 8 大久保真次郎・久布白落実の見た新島夫妻 9 八重と裏千家茶道 第三章 懐古談 1 男装して會津城に入りたる當時の苦心──懐古談一 2 家庭の人としての新島襄先生の平生──懐古談二 3 新島八重子刀自の談片──懐古談三 4 新島八重子刀自懐古談──懐古談四 5 懐古談集成──懐古談五 コラム6 同志社は方言の寄り合い所帯 コラム7 八重のお雛様と対面! コラム8 八重を演じた女優 参考文献一覧 図版所蔵・出典一覧 おわりに | |||
木村安兵衛は常陸国の下級武士出身だったが、明治時代に入り、食い扶持を失ってしまった。そこで上京し、政府が設けた職業訓練施設「授産所」に入り、ここでパンに出会った。
安兵衛は家族でパン屋を営むことを決意し、1869年(明治2年)3月、新橋に東京で最初のパン屋「文英堂」をオープンした。現在の木村屋總本店の創始である。

しかし米食中心の日本人はパンの味、食感に馴染めず、なかなか売上が伸びなかった。さらに不幸なことに、1872年(明治5年)2月、東京を襲った大火事で店を失ってしまう。
安兵衛は諦めることなく、1ヶ月後には焼け残ったパン窯を使って店を再開した。

東京医学校付属病院に脚気で入院中の桂弥一の担当医でドイツ人のホフマンは、治療食としてパンを勧めた。文英堂からパンを買った弥一は、みるみる回復していった。
いまでは、小麦の杯に含まれるビタミンB1が脚気を治療する効果があることが分かっている。
この噂を聞きつけて、安兵衛の文英堂は繁盛した。

しかし安兵衛は、パンを治療食として見られていることに不満だった。どうしたらパンが日本に受け入れられるのか考え抜いた安兵衛は、パンを日本風の味付けにすることを思いつく。饅頭は、本国の中国では肉や野菜を入れたものだが、日本では甘いあんを入れることで普及したことにヒントを得た。

1873年(明治6年)の暮れ、安兵衛はあんパンの開発に成功。
1874年(明治7年)4月、満を持して銀座煉瓦街にパン屋を出店する。
これが、明治天皇の家庭教師であった山岡鉄舟の目に止まり、鉄舟はあんパンのファンになる。

1875年(明治8年)、明治天皇が花見のために隅田川に行幸し、途中、水戸徳川家の屋敷に立ち寄ることになった。水戸徳川家が天皇接待の内容を山岡鉄舟に質問したところ、あんパンを出すことを提案。
4月4日、徳川家の屋敷を訪問し、あんパンを食した天皇は、「ひきつづき納めるように」と命じたという。
また、鉄舟は、静岡で隠退生活を送っていた最後の将軍、徳川慶喜にもあんパンを送り続けている。
安兵衛は家族でパン屋を営むことを決意し、1869年(明治2年)3月、新橋に東京で最初のパン屋「文英堂」をオープンした。現在の木村屋總本店の創始である。
しかし米食中心の日本人はパンの味、食感に馴染めず、なかなか売上が伸びなかった。さらに不幸なことに、1872年(明治5年)2月、東京を襲った大火事で店を失ってしまう。
安兵衛は諦めることなく、1ヶ月後には焼け残ったパン窯を使って店を再開した。
東京医学校付属病院に脚気で入院中の桂弥一の担当医でドイツ人のホフマンは、治療食としてパンを勧めた。文英堂からパンを買った弥一は、みるみる回復していった。
いまでは、小麦の杯に含まれるビタミンB1が脚気を治療する効果があることが分かっている。
この噂を聞きつけて、安兵衛の文英堂は繁盛した。
しかし安兵衛は、パンを治療食として見られていることに不満だった。どうしたらパンが日本に受け入れられるのか考え抜いた安兵衛は、パンを日本風の味付けにすることを思いつく。饅頭は、本国の中国では肉や野菜を入れたものだが、日本では甘いあんを入れることで普及したことにヒントを得た。
1873年(明治6年)の暮れ、安兵衛はあんパンの開発に成功。
1874年(明治7年)4月、満を持して銀座煉瓦街にパン屋を出店する。
これが、明治天皇の家庭教師であった山岡鉄舟の目に止まり、鉄舟はあんパンのファンになる。
1875年(明治8年)、明治天皇が花見のために隅田川に行幸し、途中、水戸徳川家の屋敷に立ち寄ることになった。水戸徳川家が天皇接待の内容を山岡鉄舟に質問したところ、あんパンを出すことを提案。
4月4日、徳川家の屋敷を訪問し、あんパンを食した天皇は、「ひきつづき納めるように」と命じたという。
また、鉄舟は、静岡で隠退生活を送っていた最後の将軍、徳川慶喜にもあんパンを送り続けている。
参考書籍
参考サイト
- 同志社大学のはじまり:同志社大学
- 木村屋總本店
この時代の世界
木村屋總本店 銀座本店付近の地図

(この項おわり)





建学精神はキリスト教精神に基づく「良心」である。「智育」(頭の教育)だけでなく、「徳育」(心の教育)をもあわせて行う所に最大の特色がある。
課程は5年制の普通科で、授業料は月50銭、寄宿生は月3円だった。最初の生徒はわずか8人、すべて男子だった。