
1881年(明治14年)、松方正義が大蔵卿に就任すると、紙幣整理や増税、政府予算の圧縮によってデフレ政策(松方デフレ)をとった。
秩父郡一帯は養蚕製糸が盛んで比較的豊かな暮らしをしていたが、松方デフレによって生糸の価格は大暴落し、多くの農家が破産の危機に瀕した。
1884年(明治17年)2月、秩父に結成された自由党を中心に、負債に悩む秩父の農民たちは、各地で山林集会を開き、困民党と呼ばれる集団が組織されていった。間もなく武装蜂起の準備を進めていった。

10月29日、板垣は自由党を解散する。
その2日後の10月31日に秩父の困民党が武装蜂起する。翌11月1日に吉田町の椋神社に集まり、田代栄助を総理として、無血蜂起を進めた。
当初、困民党軍による占拠が進んだが、政府は憲兵隊や東京鎮台を動員し、徹底的な武力弾圧を図った。困民党軍は長野県南佐久まで転戦したが、ついに11月9日に壊滅する。この暴動による死者は、困民党側が二十数名、政府側は3名とされている。
蜂起に参加した人数は8千人とも1万人とも言われるが、死刑7名を含む約4千名が処罰された。
秩父郡一帯は養蚕製糸が盛んで比較的豊かな暮らしをしていたが、松方デフレによって生糸の価格は大暴落し、多くの農家が破産の危機に瀕した。
1884年(明治17年)2月、秩父に結成された自由党を中心に、負債に悩む秩父の農民たちは、各地で山林集会を開き、困民党と呼ばれる集団が組織されていった。間もなく武装蜂起の準備を進めていった。
10月29日、板垣は自由党を解散する。
その2日後の10月31日に秩父の困民党が武装蜂起する。翌11月1日に吉田町の椋神社に集まり、田代栄助を総理として、無血蜂起を進めた。
当初、困民党軍による占拠が進んだが、政府は憲兵隊や東京鎮台を動員し、徹底的な武力弾圧を図った。困民党軍は長野県南佐久まで転戦したが、ついに11月9日に壊滅する。この暴動による死者は、困民党側が二十数名、政府側は3名とされている。
蜂起に参加した人数は8千人とも1万人とも言われるが、死刑7名を含む約4千名が処罰された。
この時代の世界
参考書籍
参考サイト
椋神社付近の地図
【鉄道+バス】
- 西武秩父線「西武秩父駅」から西武観光バス「吉田元気村行き」で40分、龍勢会館前下車、徒歩12分
(この項おわり)
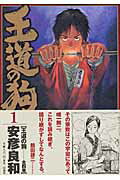




自由民権運動の先鋭化に伴って発生した激化事件の代表例とされている。