
板垣退助
1873年(明治6年)、征韓論が受け入れられず下野した板垣退助らは、選挙で選ばれた議員による議会をつくることを政府に求め、自由民権運動がはじまる。

1874年(明治7年)、板垣は政治結社「愛国公党」を結成する。
イギリスの議会制度を研究していた板垣は、明治政府に国会設立の建白書を提出する。しかし、政府は耳を貸さなかった。
国会をつくるには国民の理解と協力が不可欠だと感じた板垣は故郷・土佐に戻り、政治結社「立志社」を立ち上げ、在野からの活動に身を投じる。
1877年(明治10年)9月、西南戦争の終結により、武力での反政府運動は難しいことを悟った板垣は、地方での演説会を頻繁に開くようになる。
しかし、1878年(明治11年)7月から、政府は板垣の演説会に警官を立ち会わせるようになった。言論弾圧の始まりである。
にもかかわらず、板垣は全国の政治結社に団結を呼びかけ、9月には46人が大阪に終結した。
1874年(明治7年)、板垣は政治結社「愛国公党」を結成する。
イギリスの議会制度を研究していた板垣は、明治政府に国会設立の建白書を提出する。しかし、政府は耳を貸さなかった。
国会をつくるには国民の理解と協力が不可欠だと感じた板垣は故郷・土佐に戻り、政治結社「立志社」を立ち上げ、在野からの活動に身を投じる。
1877年(明治10年)9月、西南戦争の終結により、武力での反政府運動は難しいことを悟った板垣は、地方での演説会を頻繁に開くようになる。
しかし、1878年(明治11年)7月から、政府は板垣の演説会に警官を立ち会わせるようになった。言論弾圧の始まりである。
にもかかわらず、板垣は全国の政治結社に団結を呼びかけ、9月には46人が大阪に終結した。
1881年(明治14年)7月、北海道開発の長官、黒田清隆の汚職事件が発覚。板垣は演説会でこれを糾弾した。
やむなく明治政府は、10月12日、9年後の1890年(明治23年)に国会を開設すると発表した。
議会選挙を見据えた板垣は、自らが総裁となり、自由党を立ち上げる。

1882年(明治15年)4月6日、板垣は岐阜での遊説から宿舎に帰る途中、暴漢に刺される。板垣は7つの傷を負いながらも一命は取り留め、「板垣死すとも自由は死せず」と言ったと伝えられている。
このとき板垣を診察した医者は、後に満鉄総裁、外務大臣、東京市長を歴任することになる後藤新平であった。板垣は後藤の才を見抜き、「彼を政治家にできないのが残念だ」と語ったという。
やむなく明治政府は、10月12日、9年後の1890年(明治23年)に国会を開設すると発表した。
議会選挙を見据えた板垣は、自らが総裁となり、自由党を立ち上げる。
1882年(明治15年)4月6日、板垣は岐阜での遊説から宿舎に帰る途中、暴漢に刺される。板垣は7つの傷を負いながらも一命は取り留め、「板垣死すとも自由は死せず」と言ったと伝えられている。
このとき板垣を診察した医者は、後に満鉄総裁、外務大臣、東京市長を歴任することになる後藤新平であった。板垣は後藤の才を見抜き、「彼を政治家にできないのが残念だ」と語ったという。
1882年(明治15年)11月、板垣は後藤を伴いヨーロッパ視察に出かける。これに先立つ3月、伊藤博文らが憲法調査のためにヨーロッパに渡っている。
板垣が日本を留守にしている間、自由党急進派は貧農と結びついて、福島県令の圧政に反抗する福島事件など様々な事件を起こす。このため政府は自由党に対する弾圧を強化し、これに対して自由党は反抗するという悪循環に陥っていった。
帰国した板垣はこの現状を見て、党の先行きに不安を感じた。そこで、党再建のために10万円の政治資金を調達しようとするが、大蔵卿・松方正義によるデフレ政策のため、頼みの綱であった豪農層の没落が相次ぎ、資金集めに失敗した。
1884年(明治17年)3月には総理権限を強化して、党員の結集を図ろうとするが、地方の急進派の活動を抑えることができなかった。9月に入ると、福島事件を起こしたグループが中心となり、栃木県令・三島通庸らに対する暗殺未遂事件(加波山事件)が起きる。
このため、10月29日、板垣は自由党を解散する。

だが、自由民権運動の嵐は収まらず、解散から間もない10月31日から11月9日にかけ、埼玉県秩父郡の農民が政府に対して起こした武装蜂起するという秩父事件が発生する。

1890年(明治23年)7月1日、約束通り、第1回総選挙が行われる。
板垣ら民権派の政党は300議席中173議席を獲得した。
板垣が日本を留守にしている間、自由党急進派は貧農と結びついて、福島県令の圧政に反抗する福島事件など様々な事件を起こす。このため政府は自由党に対する弾圧を強化し、これに対して自由党は反抗するという悪循環に陥っていった。
帰国した板垣はこの現状を見て、党の先行きに不安を感じた。そこで、党再建のために10万円の政治資金を調達しようとするが、大蔵卿・松方正義によるデフレ政策のため、頼みの綱であった豪農層の没落が相次ぎ、資金集めに失敗した。
1884年(明治17年)3月には総理権限を強化して、党員の結集を図ろうとするが、地方の急進派の活動を抑えることができなかった。9月に入ると、福島事件を起こしたグループが中心となり、栃木県令・三島通庸らに対する暗殺未遂事件(加波山事件)が起きる。
このため、10月29日、板垣は自由党を解散する。
だが、自由民権運動の嵐は収まらず、解散から間もない10月31日から11月9日にかけ、埼玉県秩父郡の農民が政府に対して起こした武装蜂起するという秩父事件が発生する。
1890年(明治23年)7月1日、約束通り、第1回総選挙が行われる。
板垣ら民権派の政党は300議席中173議席を獲得した。
参考書籍
この時代の世界
(この項おわり)
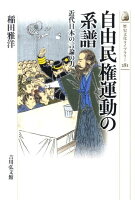



翌年には、大隈重信が立憲改進党を結成する。
自由党は自由民権運動の担い手として全国に組織を広げるが、政府との間に軋轢が生じるようになった。