
1898年(明治31年)10月10日、俳人の正岡子規は新しい文芸誌「ホトトギス」を発行し、一般読者に写生文による日記の投稿を呼びかけた。
1883年(明治16年)6月、正岡子規は故郷の松山から上京し、翌年9月、東京大学に入学する。大学時代は西洋文学にひかれ、ベースボールに熱中した。打者、走者、四球などの野球用語は子規によって発明され、2002年(平成14年)、子規は野球殿堂入りを果たしている。

1889年(明治22年)5月9日、子規は大量に喀血する。当時は不治の病とされる結核だった。
ホトトギスの口の中が赤いことから、その姿を喀血する自分に重ね、ホトトギスをあらわす「子規」という俳号を決めた。

1892年(明治25年)12月、生活のために東大を中退した子規は、日本新聞社に入社。文芸記者になる。
1895年(明治28年)4月10日、子規は日清戦争の従軍記者として中国へ渡るが、4月17日に下関講和条約が結ばれ、すぐに帰国の途につく。しかし船上で激しい喀血に襲われ、5月23日に神戸港に帰ってすぐに入院した。
故郷の松山で静養することになった子規は、教師として赴任していたかつての同級生、夏目漱石に再開する。二人はお互いの豊富を語り明かした。

正岡子規は再び上京し仕事を再開するが、やがて結核菌が骨を冒し、立ち上がることも困難になってしまう。そんな逆境にもめげず、子規は、見たままを文章にする「写生文」という文学を生み出す。
そんなときの1897年(明治30年)1月、松山の仲間が発行していた俳句雑誌「ほとゝぎす」が休刊の危機に立たされていた。
子規は、この雑誌を引き取り、俳句だけでなく文芸全般を扱う雑誌「ホトトギス」として新生し、一般読者に写生文による日記の投稿を呼びかけた。
1889年(明治22年)5月9日、子規は大量に喀血する。当時は不治の病とされる結核だった。
ホトトギスの口の中が赤いことから、その姿を喀血する自分に重ね、ホトトギスをあらわす「子規」という俳号を決めた。
1892年(明治25年)12月、生活のために東大を中退した子規は、日本新聞社に入社。文芸記者になる。
1895年(明治28年)4月10日、子規は日清戦争の従軍記者として中国へ渡るが、4月17日に下関講和条約が結ばれ、すぐに帰国の途につく。しかし船上で激しい喀血に襲われ、5月23日に神戸港に帰ってすぐに入院した。
故郷の松山で静養することになった子規は、教師として赴任していたかつての同級生、夏目漱石に再開する。二人はお互いの豊富を語り明かした。
正岡子規は再び上京し仕事を再開するが、やがて結核菌が骨を冒し、立ち上がることも困難になってしまう。そんな逆境にもめげず、子規は、見たままを文章にする「写生文」という文学を生み出す。
そんなときの1897年(明治30年)1月、松山の仲間が発行していた俳句雑誌「ほとゝぎす」が休刊の危機に立たされていた。
子規は、この雑誌を引き取り、俳句だけでなく文芸全般を扱う雑誌「ホトトギス」として新生し、一般読者に写生文による日記の投稿を呼びかけた。
この時代の世界
参考書籍
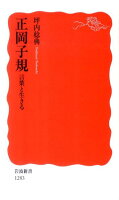
|
正岡子規 言葉と生きる | ||
| 著者 | 坪内稔典 | ||
| 出版社 | 岩波書店 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2010年12月 | ||
| 価格 | 836円(税込) | ||
| ISBN | 9784004312833 | ||
| 幕末に生れた子規は明治という時代と共に成長した。彼は俳句・短歌・文章という三つの面で文学上の革新を起こし、後世に大きな影響を与える。子規の言葉は新しくなろうとする近代日本の言葉でもあった。そのみずみずしい俳句・短歌・文章などを紹介しながら、三十四年という短い人生を濃く溌刺と生きぬいた子規の生涯を描きだす。 | |||
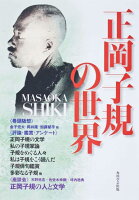
|
正岡子規の世界 | ||
| 著者 | 『俳句』編集部 | ||
| 出版社 | 角川学芸出版 | ||
| サイズ | 単行本 | ||
| 発売日 | 2010年06月 | ||
| 価格 | 1,980円(税込) | ||
| ISBN | 9784046214294 | ||
(この項おわり)


