
ルイス・エッセン(右)と原子時計
1955年、イギリス国立物理学研究所のルイス・エッセンらがセシウム133原子時計を開発した。誤差は300年に1秒で、エッセンは、3年間、当時の標準時だった暦表時と比較を行い、その狂いがないことを確認し、1958年1月1日から国際原子時(TAI)としてカウントを始めた。
ところが、絶対的に正確なものと信じられていた地球の自転と原子時計の間に、誤差やブレが発生することが分かった。観測を続けた結果、地球の自転軸に3~5ミリほどのブレがあることが突き止められた。
そして、1967年の国際度量衡総会で、「セシウム133原子が基底状態で91億9263万1770回振動する時間を1秒とする」という、あらたな秒の定義が定まった。

世界で最初の原子時計を製作したのは、ワシントンにある米国海軍天文台のウィリアム・マルコビッツで、1946年、アンモニアの吸収線を用いたメーザー型のものだった。ところが、クオーツ時計より誤差が大きかったことから、実用には至らなかった。

セシウム原子時計は、まず、真空タンクの中でセシウム原子を熱し、原子ビームを作る。このビームに、2回マイクロ波を照射し、共鳴(ラムゼー共鳴)現象が起こる値を確認し、セシウム原子の周波数を測定する。
2回の測定間隔が長いほど、干渉効果により特定すべき周波数の幅が狭まり、測定の効率と精度が上がる。だが、原子時計の大きさには限界があるため、原子ビーム絶対零度近くに冷却することで、その動きを秒速1cm程度まで遅くする。これを冷却原子泉式と呼ぶ。
現在の日本標準時は、ベースの時間を水素メーザー式で作り、セシウムを使った冷却原子泉式で、微細な誤差を修正して作っており、誤差は3億年に1秒と言われる。

2001年、東京大学大学院工学系研究科の香取秀俊教授が発表した光格子時計は、レーザー光線でつくる100万の格子に、ストロンチウムの原子を1つずつトラップして計測するもので、300億年に1秒の誤差の時計が作れるという。
そして、1967年の国際度量衡総会で、「セシウム133原子が基底状態で91億9263万1770回振動する時間を1秒とする」という、あらたな秒の定義が定まった。
世界で最初の原子時計を製作したのは、ワシントンにある米国海軍天文台のウィリアム・マルコビッツで、1946年、アンモニアの吸収線を用いたメーザー型のものだった。ところが、クオーツ時計より誤差が大きかったことから、実用には至らなかった。
セシウム原子時計は、まず、真空タンクの中でセシウム原子を熱し、原子ビームを作る。このビームに、2回マイクロ波を照射し、共鳴(ラムゼー共鳴)現象が起こる値を確認し、セシウム原子の周波数を測定する。
2回の測定間隔が長いほど、干渉効果により特定すべき周波数の幅が狭まり、測定の効率と精度が上がる。だが、原子時計の大きさには限界があるため、原子ビーム絶対零度近くに冷却することで、その動きを秒速1cm程度まで遅くする。これを冷却原子泉式と呼ぶ。
現在の日本標準時は、ベースの時間を水素メーザー式で作り、セシウムを使った冷却原子泉式で、微細な誤差を修正して作っており、誤差は3億年に1秒と言われる。
2001年、東京大学大学院工学系研究科の香取秀俊教授が発表した光格子時計は、レーザー光線でつくる100万の格子に、ストロンチウムの原子を1つずつトラップして計測するもので、300億年に1秒の誤差の時計が作れるという。
この時代の世界
参考書籍
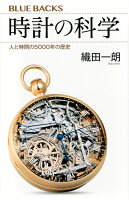
|
時計の科学 人と時間の5000年の歴史 | ||
| 著者 | 織田 一朗 | ||
| 出版社 | 講談社 | ||
| サイズ | 新書 | ||
| 発売日 | 2017年12月14日頃 | ||
| 価格 | 1,078円(税込) | ||
| ISBN | 9784065020418 | ||
| 人類が「時間」の存在に気付いたのは、いまから5000年以上も前のことです。太陽の動き利用した「日時計」から始まり、周期を人工的につくりだす「機械時計」の誕生、精度に革命を起こした「クオーツ時計」、そして時間の概念を変えた「原子時計」まで、時代の最先端技術がつぎ込まれた時計の歴史を余すところなく解説します。 人類が「時間」の存在に気付いたのは、いまから5000年以上も前のことです。 太陽の動き利用した「日時計」から始まり、周期を人工的につくりだす「機械時計」の誕生、精度に革命を起こした「クオーツ時計」、そして時間の概念を変えた「原子時計」まで、時代の最先端技術がつぎ込まれた時計の歴史を余すところなく解説します。 はじめに 第1章 時間の発見 第2章 機械式時計の発明 第3章 腕時計の誕生 第4章 電子技術で誕生したクオーツ、デジタル時計 第5章 超高精度時計と未来 あとがき 参考資料 | |||
参考サイト
- 国際原子時と協定世界時:ぱふぅ家のホームページ
(この項おわり)


